複数人で共有している空き家を手放すには?役所との連携方法
共有名義の空き家は手放しにくい理由とは?
日本では親から相続した空き家が兄弟姉妹など複数人の共有名義となっているケースが多くあります。
一人で自由に売却や処分ができないという問題が生じ、結果的に長年放置されてしまうことも少なくありません。
法律上の「共有」とは?
共有名義とは、複数人が1つの不動産を共同で所有している状態です。
民法第249条により、原則として処分行為(売却・贈与など)には全員の同意が必要とされており、1人でも反対すれば進めることができません。
放置によるリスク
空き家を長期間放置すると、以下のようなリスクが発生します:
-
倒壊・老朽化による近隣トラブル
-
固定資産税・管理費の負担が続く
-
特定空家に指定されると税額が最大6倍に増加
-
家庭裁判所の調停など、法的手続きが必要になることも

共有名義では全員の同意が基本ですが、例外的に一部持分のみの売却や譲渡も可能です。行政の支援も受けられますよ。
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
空き家を手放すためにまず確認すべきこと
共有名義の空き家を売却・処分するには、事前に状況整理が必要です。以下のステップで確認を進めましょう。
名義人の確認
まずは法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、共有者全員の持分を確認しましょう。相続登記が未了であれば、まず名義変更が必要です。
共有者の意思確認
次に、全共有者に空き家の扱いについての意思確認を行います。
1人でも反対すれば売却は進められないため、早期の話し合いがカギとなります。
テーブル:共有空き家の初期確認ステップ
| ステップ | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| ① | 登記簿謄本の取得 | 法務局で手続き。共有者と持分を確認 |
| ② | 相続登記の完了 | 未了であればまず所有者名義を整理 |
| ③ | 共有者全員の意思確認 | 売却・活用・放棄などの方針をすり合わせ |
| ④ | 管理状況と固定資産税の確認 | 管理者の有無、税負担者の明確化 |
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
共有者の合意が得られない場合の選択肢
全員の合意が得られない場合でも、手放す方法が全くないわけではありません。
一部持分の売却
自身の持分だけを第三者に売却することは可能です。
ただし市場での売却は難しいため、専門の不動産会社や共有持分買取業者に相談するとよいでしょう。
家庭裁判所による共有物分割請求
話し合いが平行線の場合は、**家庭裁判所へ「共有物分割請求」**を行うことで、
強制的に売却または持分の分離を進めることが可能になります。
ただし、調停・審判には時間と費用がかかる点も踏まえて検討しましょう。
行政との連携で空き家の手放しをスムーズに
地方自治体が実施する「空き家バンク」とは?
近年、各自治体では空き家の利活用や流通促進を目的とした「空き家バンク」の仕組みを整備しています。
これは、売却したい空き家を自治体の運営するWebサイトに登録し、購入希望者とのマッチングを促進する制度です。
空き家バンクの特徴
-
費用負担が少ない(無料または格安)
-
不動産会社を介さずに利用できる
-
購入希望者が「地域に根付いた人材」に絞られる
-
地方創生と絡めた補助制度の対象にもなりやすい
ただし、空き家バンクは全共有者の同意が前提です。事前に方針をまとめておきましょう。
行政が提供する支援制度とは?
空き家の解体や処分には費用がかかるため、各自治体では補助金や支援制度を用意していることがあります。
代表的な行政支援の例
| 支援制度名 | 内容 | 補助上限金額の例(自治体による) |
|---|---|---|
| 解体費用補助制度 | 老朽化空き家の解体費用を一部補助 | 最大100万円〜150万円 |
| 空き家活用リフォーム助成金 | 活用を前提とした改修に対する助成 | 最大50万円〜100万円 |
| 仲介手数料補助 | 空き家バンク経由で売却時の仲介手数料を補助 | 最大5万円〜10万円 |
| 寄附・無償譲渡相談窓口 | 空き家を自治体や法人へ無償譲渡する相談支援 | ケースバイケース |
事前に自治体の公式HPまたは窓口で確認しておくと、手続きがスムーズです。
寄附や無償譲渡という選択肢
共有名義の空き家が売れない場合や修繕費が重荷な場合、行政やNPOなどへの**無償譲渡(寄附)**という選択肢もあります。
寄附の対象になりやすいケース
-
防災・地域活性化の拠点として活用できる物件
-
立地が良好(駅近・公道沿いなど)
-
利用希望団体(NPOや自治会など)がある
ただし、受け取りを拒否されることも多いため、早めに交渉を開始することが重要です。
所有者不明土地管理制度の活用
共有者の一部が所在不明、または同意が得られない場合に有効なのが「所有者不明土地管理制度」です。
裁判所に申立てることで、共有持分の一部が「管理人」によって処分可能となります。
この制度が有効なケース
-
他の共有者が死亡・行方不明で連絡が取れない
-
名義が旧姓のままで相続登記が未完了
-
話し合いに応じない「不明確な反対者」がいる
制度の利用には弁護士や司法書士の支援が必要ですが、長年放置された物件の出口戦略として注目されています。
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
共有持分を専門業者に売却する方法も
共有者との合意が得られず、行政支援も難航する場合には、共有持分を専門の買取業者に売却する方法もあります。
メリット
-
他の共有者の同意不要
-
現金化が早い(最短即日)
-
管理責任・税負担から解放される
デメリット
-
市場価格より安くなる可能性が高い
-
売却後も共有者との関係性に注意が必要
「どうしても手放したい」「相続トラブルをこれ以上増やしたくない」という方には、有効な選択肢となります。
複数人で共有している空き家を手放すには、全員の同意を得ることが理想ですが、合意形成が難しいケースも少なくありません。
その場合は、「空き家バンク」「行政支援制度」「無償譲渡」「家庭裁判所制度」などを活用し、出口戦略を多角的に検討することが大切です。
放置すれば税金やトラブルのリスクも高まるため、早期の対策と専門家への相談を心がけましょう。

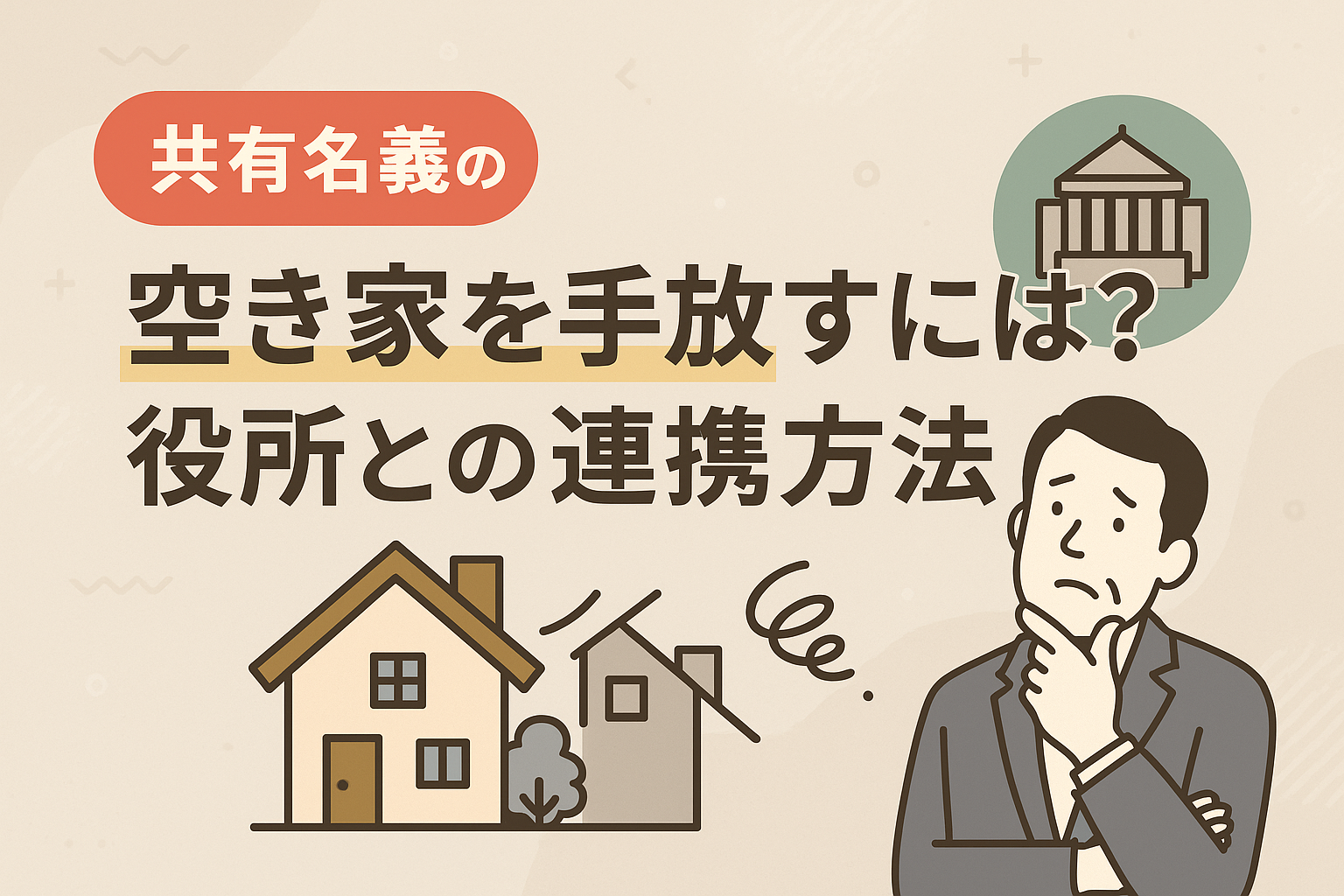







兄弟で相続した実家が空き家のまま…売りたいけど1人だけ反対していて困っています。