共有持分は遺言書で指定できる?相続トラブルを防ぐ方法
遺言書で共有持分を指定できるのか?
共有持分とは、1つの不動産を複数人で所有している状態を指します。たとえば相続により兄弟で実家を受け継いだ場合などが該当します。このような共有持分を「誰に相続させたいか」は、生前にしっかりと意思表示しておかないと思わぬトラブルにつながりかねません。
では、遺言書でこの共有持分を特定の人に渡すことは可能なのでしょうか?
結論から言えば、遺言書で共有持分の相続先を指定することは可能です。ただし、法的に有効な遺言書とするためには、形式や内容に厳密なルールがあるため注意が必要です。
相続で共有状態になるリスクとは?
遺言書を残さずに被相続人が亡くなった場合、不動産は法定相続分に応じて自動的に分割されるため、結果として「共有」状態になりやすいのが実情です。
特に以下のようなケースでは、遺産分割協議が難航し、資産の有効活用ができない状態に陥る可能性があります。
-
相続人が複数いて仲が悪い
-
一部の相続人が遠方にいて連絡が取れない
-
被相続人の意向が明確でなかった
このような状況では、不動産を売却したくても共有者全員の同意が得られず、処分が進まないという問題が発生します。
スムーズな相続を実現するための工夫
相続トラブルを回避するためには、被相続人が生前に共有持分の行方を明確にすることが最も有効です。その手段のひとつが「遺言書」です。
遺言書に盛り込むべき要素
-
どの不動産の共有持分を誰に相続させるか
-
他の相続人との調整として、代償分割の方法(現金などで調整)も明記
-
法定相続人以外に共有持分を渡す場合の理由

そのようなケースでは、生前に「特定の人へ共有持分を相続させる」という遺言があればトラブルは防げたかもしれません。
スクロールできます →
| 相続トラブルの原因 | 解説 |
|---|---|
| 被相続人の意思が不明 | 遺言書がなく、分割方針が決まらない |
| 相続人同士の関係が悪い | 感情的な対立が協議を長期化させる |
| 共有者の所在不明 | 連絡が取れず、登記や売却が進まない |
遺言書の有無が相続後のスムーズな処理を大きく左右するため、可能であれば公正証書遺言などの法的効力が強い形で残すのが理想です。
遺言書での指定がもたらす効果とは?
遺言書によって共有持分の分配先を明確に指定することで、相続トラブルの予防だけでなく、その後の不動産活用にも大きな影響を与えます。
たとえば、以下のようなケースでは、遺言書が存在することでスムーズな処理が可能になります。
-
実家を長男に単独で相続させたい
-
土地の持分を売却予定の子どもに集約したい
-
家族ではない第三者に渡したい(例:事業用パートナーなど)
これらは、明文化された「意思」がなければ実現困難です。口頭での伝達だけでは、法的に意味を持たず、他の相続人の同意がなければ進められません。
遺言書に加えて考えておきたい制度
遺言書だけでは補えないケースもあるため、状況に応じて以下の制度も活用することで、より強固な相続対策が可能になります。
家族信託
-
財産の管理・運用・処分を信頼できる家族に任せる制度
-
共有持分を「どのように活用するか」を柔軟にコントロール可能
生前贈与
-
相続発生前に持分を贈与して整理する方法
-
税制面での優遇措置を受けられるケースもある

親から「この土地はあんたに任せたい」と言われていたけど、遺言書はなかったから結局兄弟で共有に…

そのような場合、家族信託や生前贈与を併用していれば、意思通りに資産を渡すことができた可能性が高いです。
実際にあったトラブル事例とその教訓
ケース1:意思が不明確でトラブルに発展
被相続人が「長男に実家を任せたい」と話していたものの、遺言書がないまま他界。結果、3人の兄弟が全員持分を持つ共有状態となり、処分に合意できず不動産は数年間も放置され、税金と維持費だけがかさみました。
ケース2:遺言書が形式不備で無効に
自筆証書遺言を作成していたが、日付の記載ミスや訂正の方法に問題があり、家庭裁判所で無効と判断されたケースもあります。これにより、他の相続人からの異議が入り、トラブルへ発展しました。
法的に有効な遺言書を作成するには、公証人による「公正証書遺言」の活用が安全です。
スクロールできます →
| 対策方法 | 特徴・メリット |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証人が作成。形式不備がなく、安全性が高い |
| 家族信託 | 信頼できる人に財産管理を委託できる。柔軟な活用が可能 |
| 生前贈与 | 相続前に資産整理。贈与税の非課税枠活用も検討 |
専門家に相談する重要性
遺言書や信託の設計には法律・税務の知識が欠かせません。「なんとなく」で作った文書では、相続トラブルを防ぎきれない可能性があります。
-
司法書士や弁護士と相談しながら、遺産分割の意図を明文化する
-
相続人全体にとって不公平感が出ないよう、代償分割や遺留分への配慮も検討する
共有持分を遺言書で指定することは法的に可能であり、相続トラブルのリスクを大きく下げる手段となります。ただし、形式や内容に不備があると逆に紛争の火種となるため、公正証書遺言の活用や専門家との相談が重要です。家族信託や生前贈与などの選択肢も含め、複合的に対策を講じておくことが賢明です。

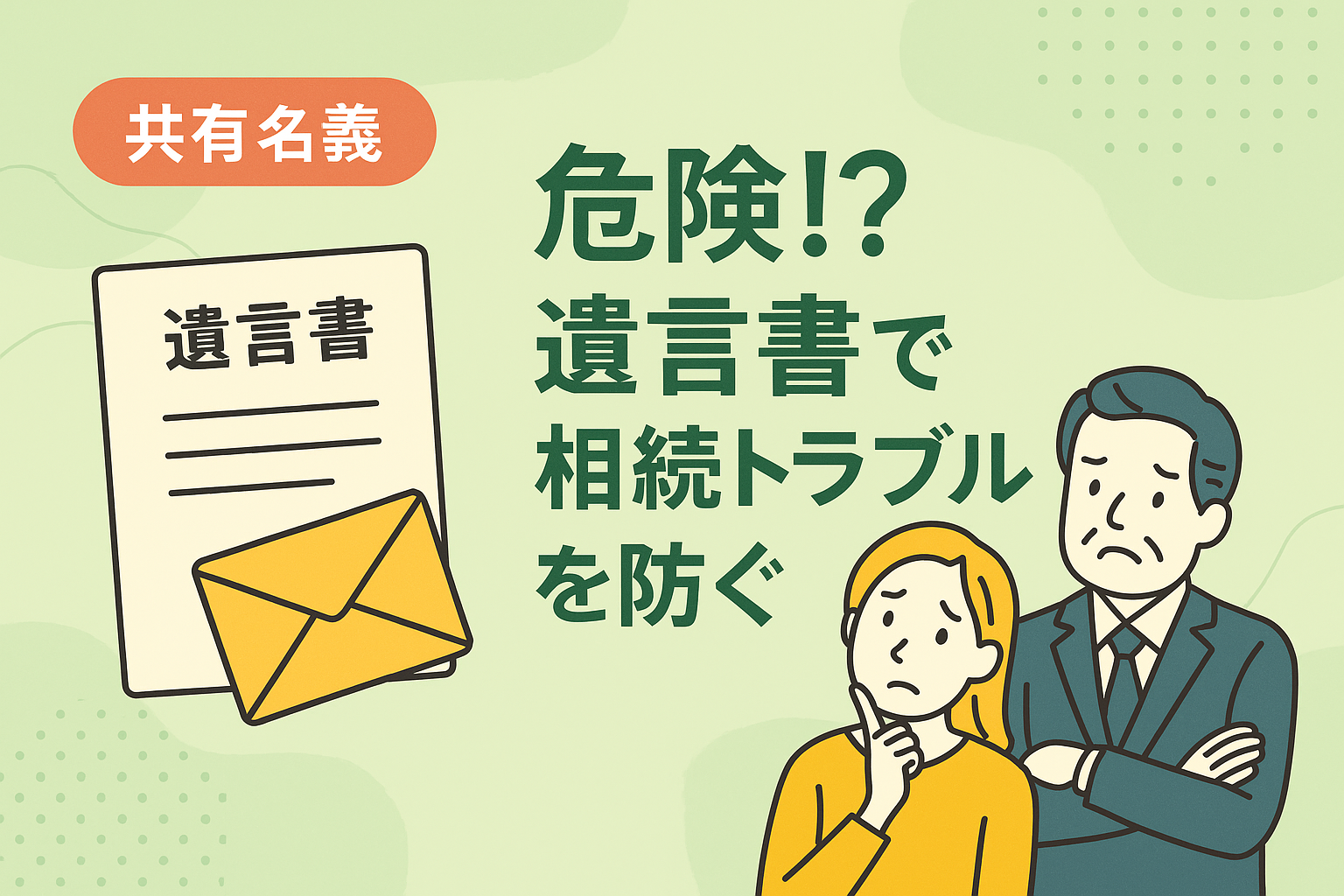

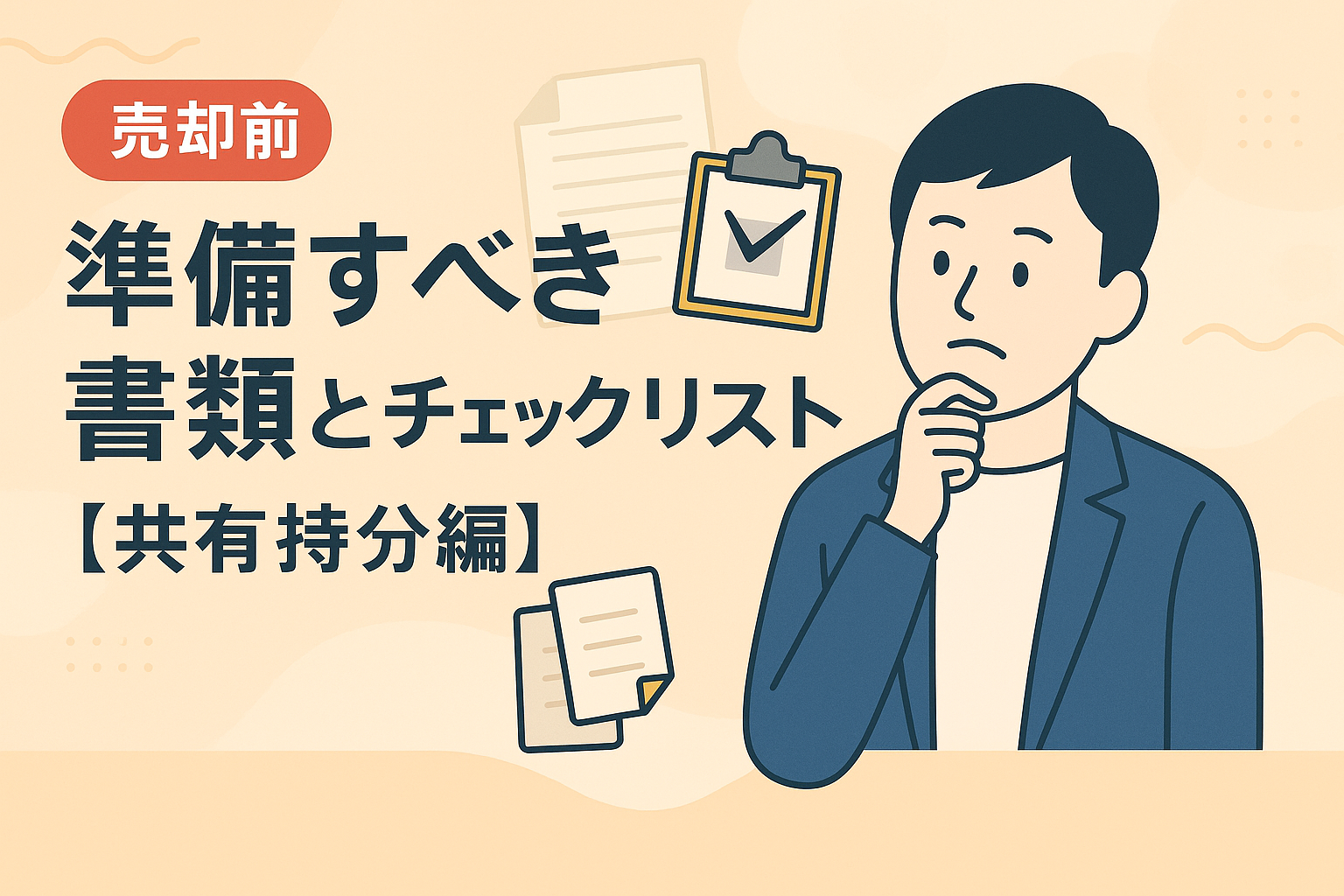



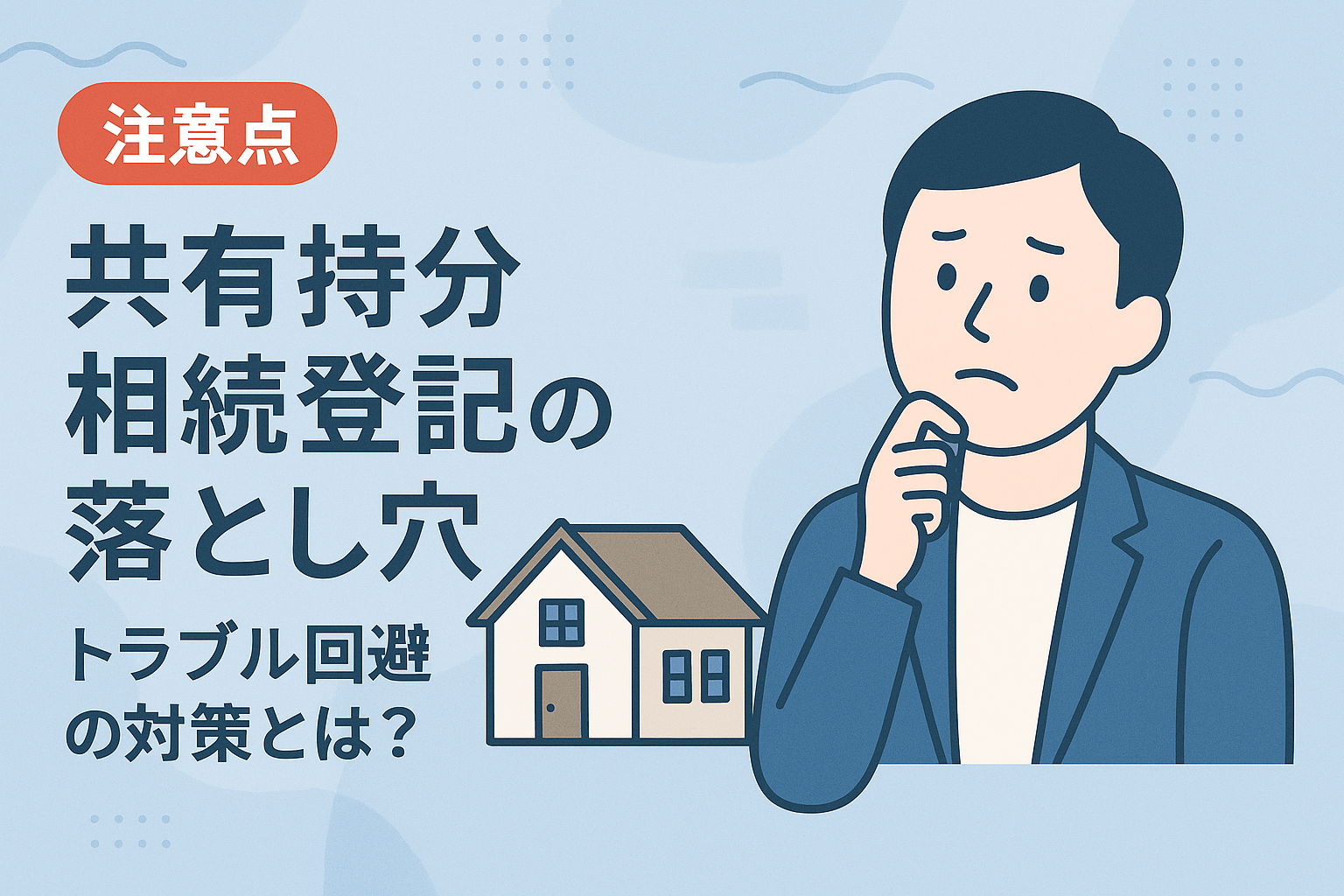
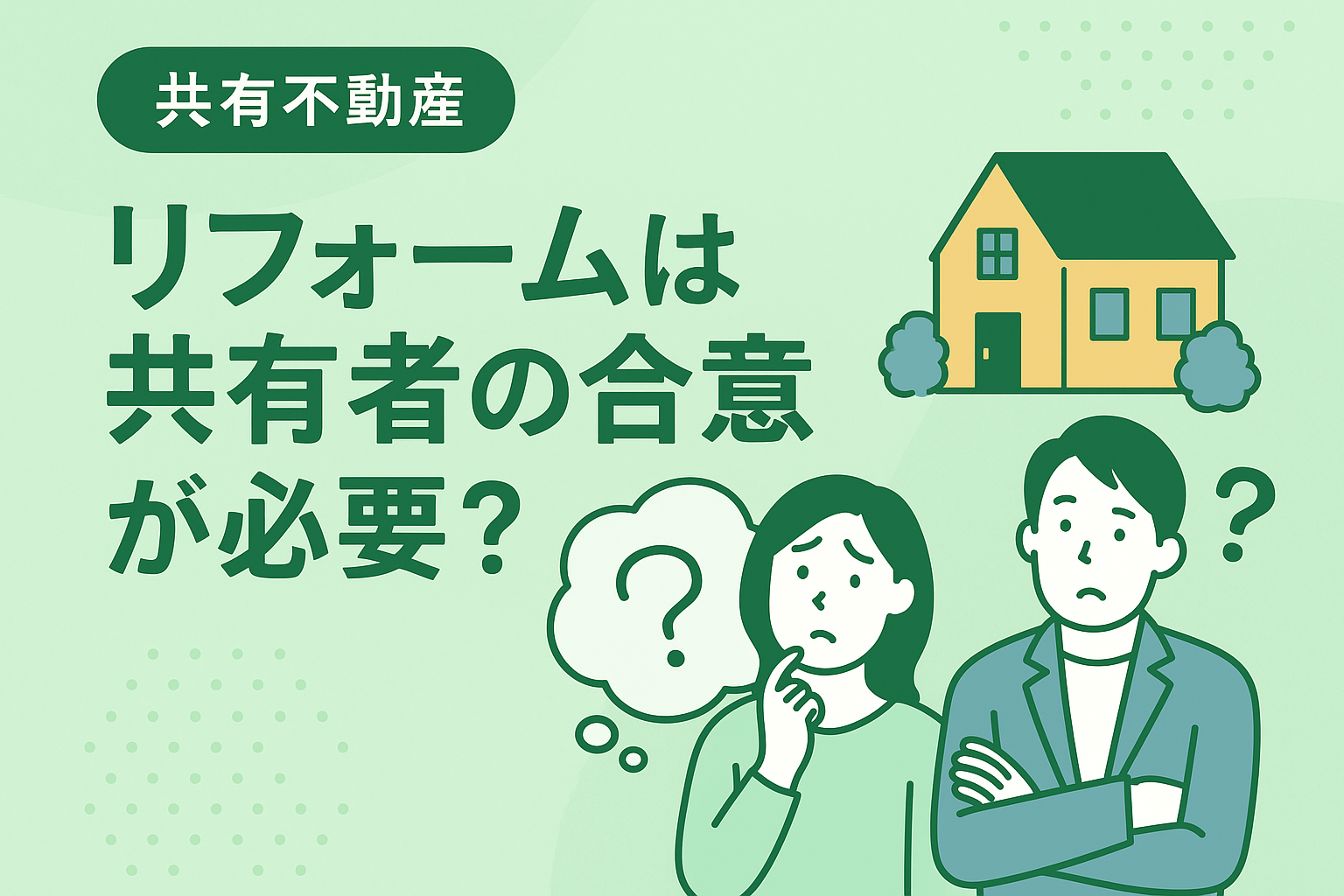

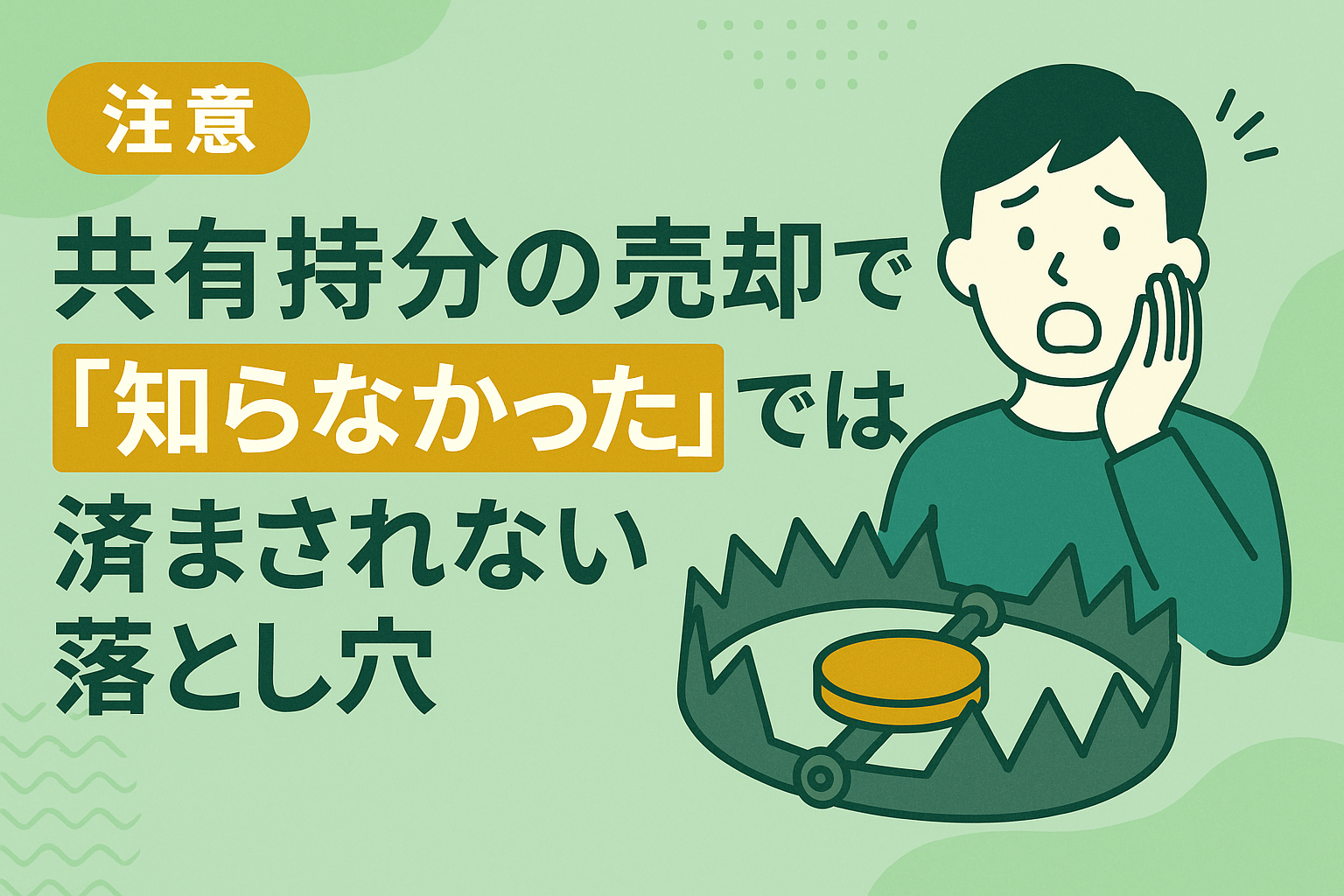





父の死後、実家の土地が兄弟3人の共有になりました。でもひとりが住み続けていて売却の話が進みません…。