共有持分の価格はどうやって決まるのか?
共有名義でも「価値」は存在する
「共有持分は売っても安いだけ」と思い込んでいませんか?
実際には共有名義であっても“持分”としての価値が評価され、市場で取引されることが可能です。
不動産全体の価値をもとに、持分割合を加味した価格が算出されますが、それだけではなく以下のようなさまざまな要素が価格に影響を与えます。
-
売却可能性(単独売却が困難かどうか)
-
他共有者との関係性
-
使用実態(誰が利用しているか)
-
接道・用途地域などの不動産要因
共有持分の査定が難しい理由とは?
不動産全体の価格から持分割合をかけた金額が「理論上の価格」となりますが、実際の売却価格はそこから調整が入ることが一般的です。

理論価格と実勢価格は異なります。共有持分の市場性・交渉余地などを考慮した上で価格が決まるのが通常です
査定で見られる主な評価ポイントとは?
共有持分の価格を算出する際には、不動産そのものの査定とは異なり、「制約の大きさ」や「買い手のリスク」などを考慮するため、査定基準はより複雑になります。
以下は主な評価ポイントの一覧です。
スクロールできます →
| 評価項目 | 内容 |
|---|---|
| 法的制限 | 再建築不可や借地権付き物件は評価が下がる |
| 他共有者の関係 | 他共有者が売却に非協力的だと価値は低下 |
| 使用状況 | 現況で居住中や貸出中の場合は価格が上下 |
| エリア性 | 需要の高い地域であれば持分でも高く売れる |
| 実勢取引事例 | 過去の類似事例と比較して相場を算出 |
「価格の根拠」を提示する査定書が重要です。専門業者によっては、法的リスクや取引履歴を含めた詳細なレポートを作成してくれるところもあります。
一般査定と専門査定の違い
共有持分は通常の不動産会社では正確に査定できない場合があります。なぜなら、一般的な不動産取引と異なり、購入者側に特有のリスクがあるためです。
-
一般査定: 通常の相場から単純に持分割合をかけるのみ
-
専門査定: 売却困難性や共有トラブルの有無を加味し、売却実績やリスクを踏まえて価格を算出
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
専門家が語る「適正価格」で売るための工夫とは?
共有持分の売却においては、「高すぎず安すぎず」の適正価格の見極めが非常に重要です。
ただしその“適正”も、査定方法や買主の属性によって変動するため、戦略的な価格設定が求められます。
高く売るための3つの工夫
実際に高値売却に成功した事例に共通するポイントは以下の3つです。
スクロールできます →
| 工夫 | 内容 |
|---|---|
| 専門業者を活用 | 通常の不動産会社ではなく、共有持分専門の買取業者へ依頼 |
| 状況を整理 | 利用状況・他共有者との合意有無などを整理しておく |
| タイミングを見極め | 不動産需要が高まる時期(春・秋)に合わせて売却 |

売るタイミングや相談先によって、そんなに価格が変わるんですね…。

はい。共有持分の売却では「誰に売るか」が価格を大きく左右します。買い手とのマッチングが非常に重要です。
「安く買い叩かれる」原因とその回避策
共有持分は一般的に「トラブルの種」や「使いづらい物件」として扱われることがあり、安く買い叩かれてしまうケースも少なくありません。
しかし、それには原因があります。
以下に「安く売ってしまう人の共通点」とその対策を整理します。
-
他の共有者と話し合っていない
-
→ 単独で動かず、できる範囲で共有者と合意形成を
-
-
査定を1社にしか頼んでいない
-
→ 複数業者に依頼し、価格の妥当性を確認
-
-
情報を曖昧にしたまま売却を進めた
-
→ 利用実態や法的状況など、整理して伝える準備が必要
-
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
専門業者による無料査定の活用法
現在は無料で共有持分を査定してくれる専門業者も増えています。
無料とはいえ、以下のような内容まで評価してもらえることが多く、活用する価値は大きいです。
-
持分のみの売却価格(単独査定)
-
他共有者との協議状況を加味した調整査定
-
複雑な物件(再建築不可・底地権など)の評価対応
加えて、売却以外の解決策(リースバックや権利整理など)を提案してくれるケースもあります。
持分売却=「最後の手段」ではありません。
適切なアドバイスを得ることで、納得のいく価格での売却や資産整理が実現可能です。
共有持分の価格は、不動産全体の価値や持分割合だけでは決まりません。他共有者との関係性や物件の法的制約、使用状況、買主のリスク判断まで考慮されるため、正しい査定と価格交渉が成功の鍵となります。一般の不動産会社ではなく、専門知識を持つ業者に相談することで、納得できる価格での売却が可能になります。

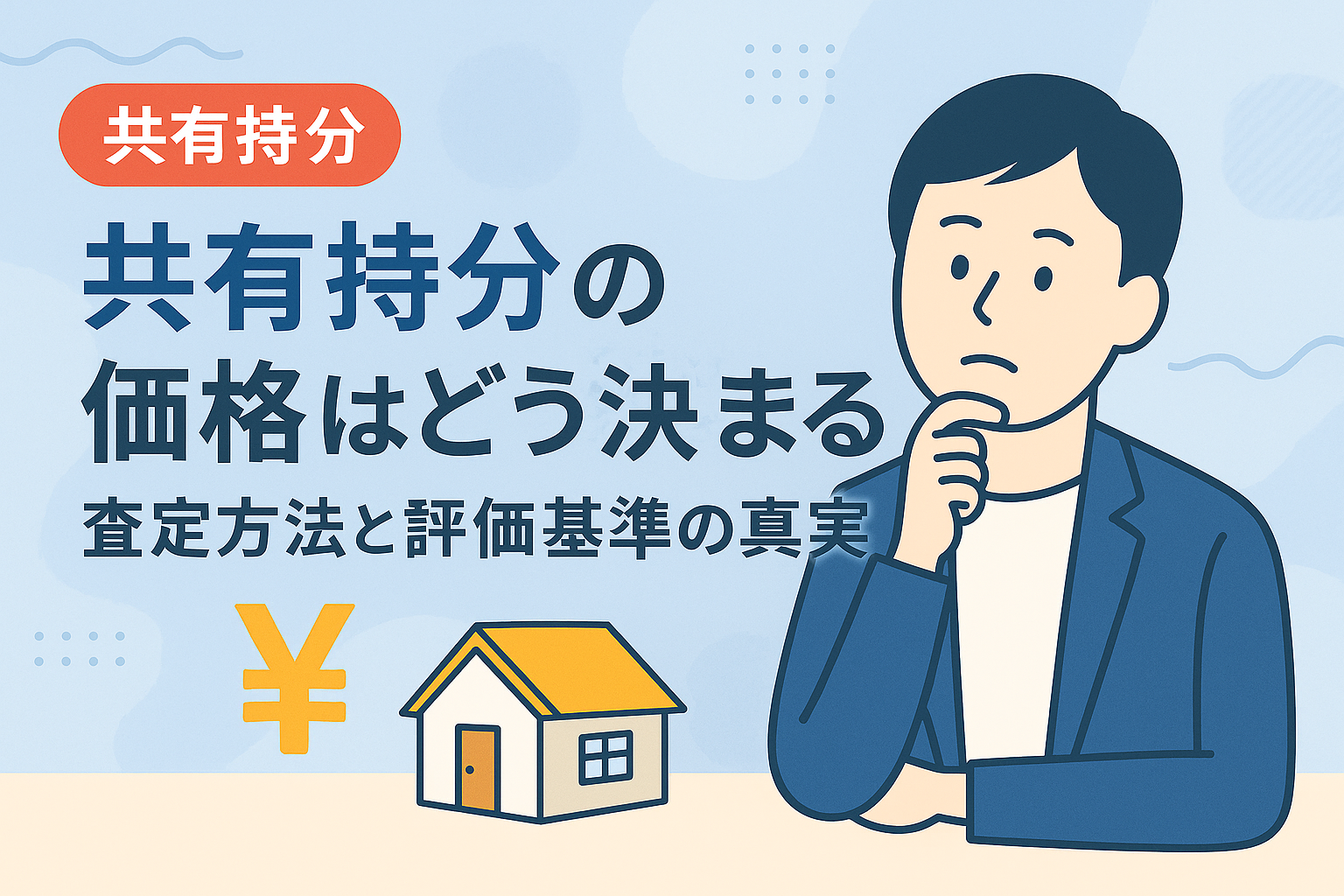

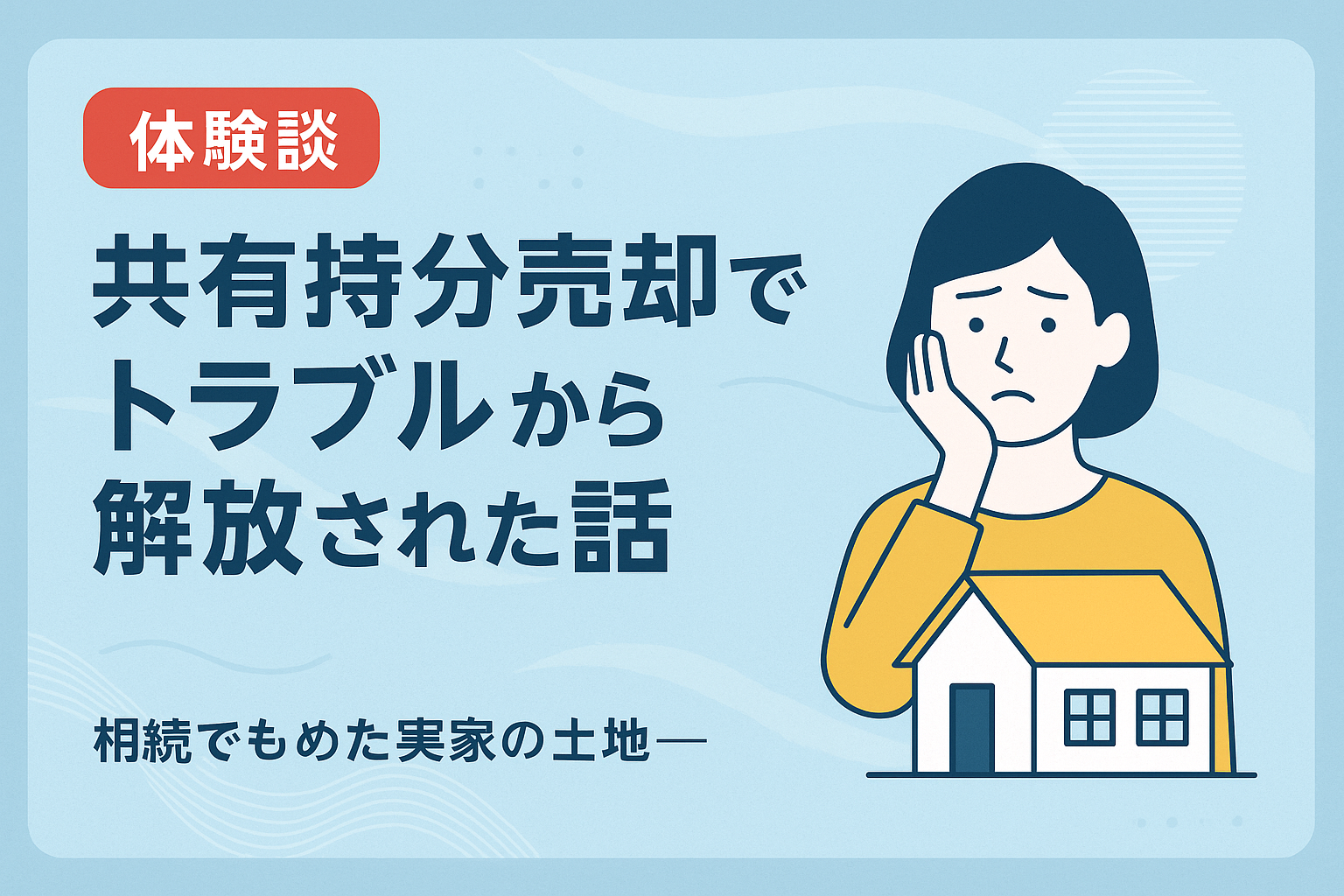



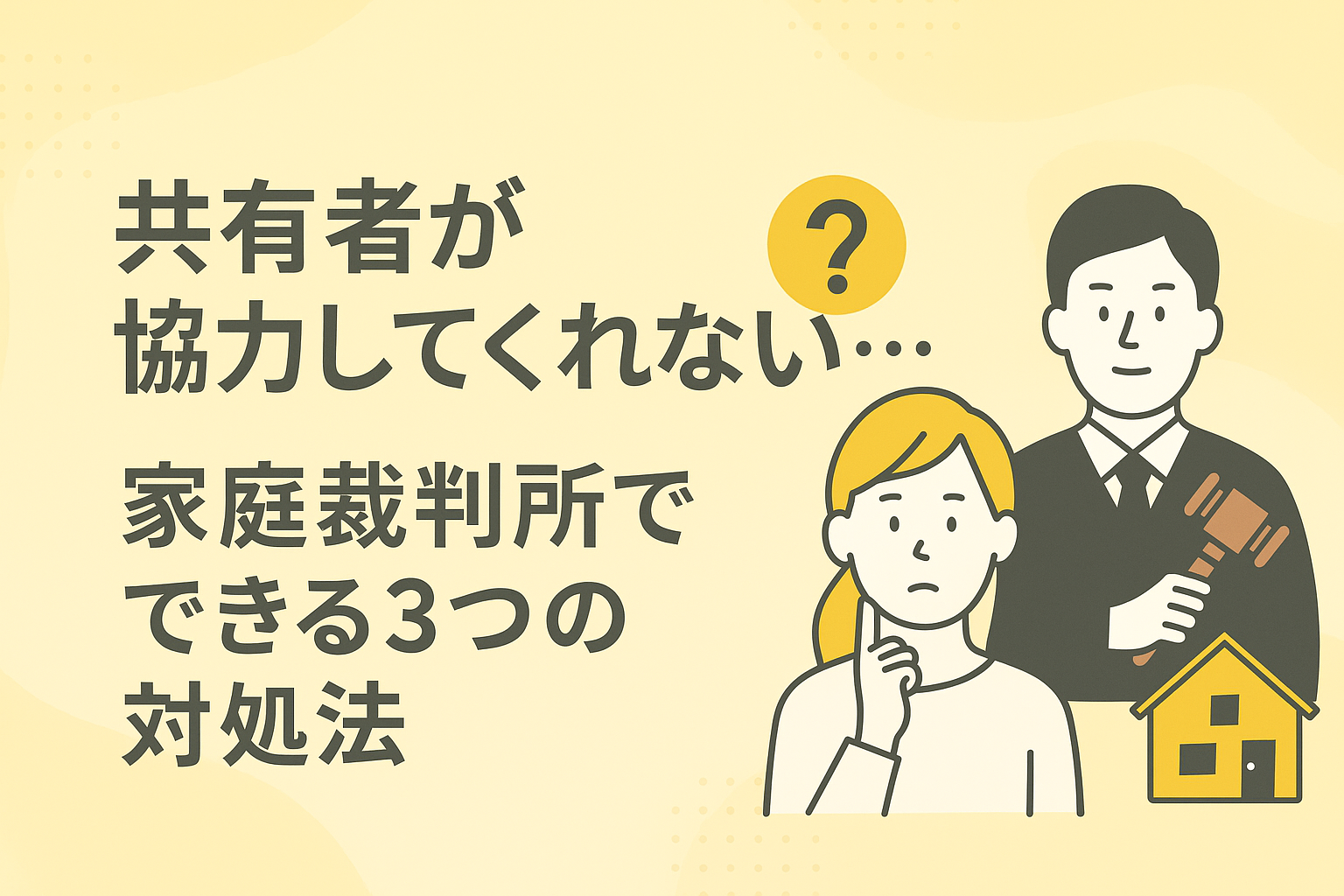
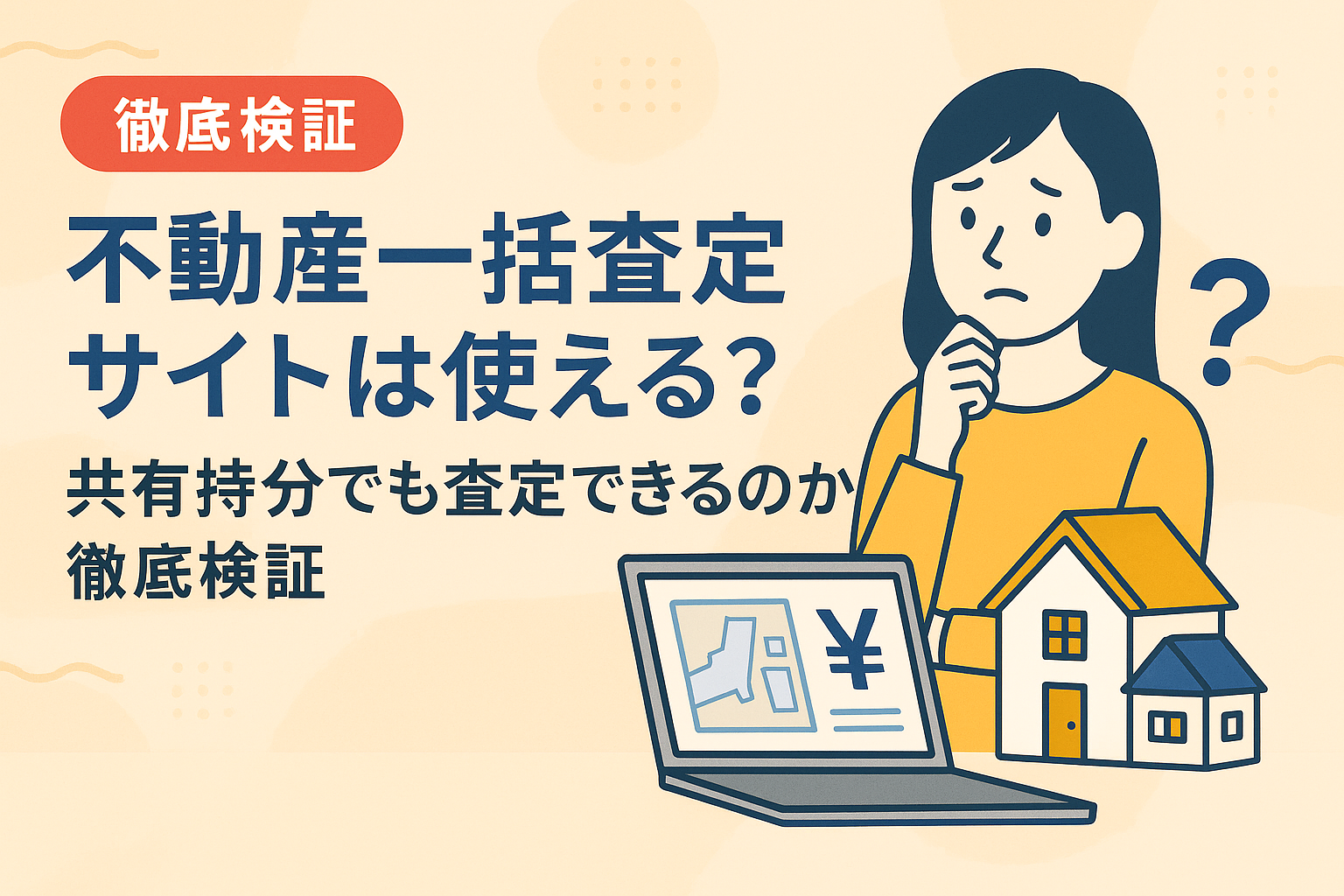







持分2分の1を持っているから、相場の半額で売れると思っていたのに全然違っていて驚きました…