共有名義の不動産を贈与する方法とは?税金と登記の注意点
共有名義の不動産を贈与するケースは意外と多い
親から子へ、あるいは兄弟間で不動産を贈与する際、共有名義のまま贈与するというケースは少なくありません。とくに、以下のようなケースが代表的です。
-
親が所有する不動産の一部持分を子に贈与する
-
兄弟で共有している不動産の持分を、誰か1人にまとめるための贈与
-
夫婦間での資産整理による持分移転
しかし、共有名義不動産の贈与には、単独所有とは異なる注意点が存在します。とくに税金と登記においてトラブルになりやすいため、事前の理解が不可欠です。
【前提】贈与とは何か?相続との違いを確認
まず、贈与とは「生前に無償で財産を譲り渡すこと」です。一方で、相続は「死亡によって財産を承継すること」です。
| 区分 | 贈与 | 相続 |
|---|---|---|
| 発生時期 | 生前 | 死亡後 |
| 課税対象 | 贈与税 | 相続税 |
| 基礎控除 | 年間110万円(贈与税) | 3000万円+600万円×法定相続人(相続税) |
| 登記義務 | 贈与契約と所有権移転登記が必要 | 相続登記(2024年4月から義務化) |
贈与の場合、110万円を超える部分には贈与税がかかり、加えて登記費用や登録免許税も発生します。
贈与できるのは「自分の持分」だけ
共有名義であっても、自分の持分に限って贈与することは可能です。たとえば、3分の1ずつ持分を持っている兄弟のうち、AがBに自分の持分を贈与したい場合、その3分の1を贈与する契約を結ぶことができます。

ご自身の持分であれば、贈与契約書を作成し、登記手続きをすれば譲渡可能です。ただし、贈与税の対象になるので注意が必要です。
なお、他人の持分を勝手に贈与することはできません。たとえ親子・兄弟間であっても、必ず贈与者本人の意思が必要です。
贈与税の負担を抑えるための方法
共有持分の贈与において問題になるのが贈与税の負担です。課税対象額は、基本的に「贈与した不動産の時価(評価額)」となります。そこで活用したいのが以下の特例制度です。
贈与税の特例制度一覧
| 特例名 | 内容 | 適用条件 |
|---|---|---|
| 暦年課税制度 | 年間110万円まで非課税 | 毎年少額ずつ分割贈与 |
| 配偶者控除(2,000万円) | 20年以上の婚姻関係がある配偶者への贈与 | 持家とその敷地が対象 |
| 相続時精算課税制度 | 最大2,500万円まで非課税に | 将来の相続時に精算 |
たとえば「相続時精算課税制度」を使えば、贈与時には税金がかからず、相続時にまとめて課税対象に含めることが可能です。
所有権移転登記と登録免許税の注意点
贈与によって持分を移転するには、贈与契約書の作成と登記申請が必要です。とくに登記において注意すべきポイントは以下の2点です。
-
登録免許税は不動産評価額の2%(贈与の場合)
-
贈与契約書は必ず書面で作成すること
登録免許税は高額になるケースもあり、贈与する不動産の評価額が1,000万円であれば、20万円の税金がかかります。
贈与契約書の作成は必須。口約束では登記できない
不動産の贈与を行う場合、必ず書面による贈与契約書が必要です。これは民法上のルールでもあり、登記の際にも添付書類として必要になります。
とくに共有不動産の場合は、次のような内容を明記した契約書を作成しておきましょう。
-
贈与する人(贈与者)と受け取る人(受贈者)の氏名・住所
-
不動産の所在・地番・種類・構造など
-
持分割合(例:3分の1を贈与)
-
贈与の時期(いつから持分を移転するか)
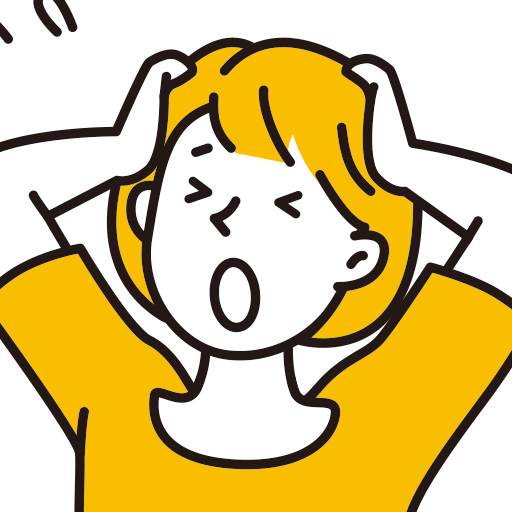
父が「お前に土地をやる」と言ってくれたのですが、口頭だけでも贈与って成立するんですか?

贈与自体は口頭でも成立しますが、不動産登記には書面(契約書)が必須です。あとで「言った言わない」のトラブル防止のためにも、必ず契約書を作りましょう。
他の共有者の同意は原則不要だが、事前通知が望ましい
共有名義の持分を贈与する際、他の共有者の同意は原則不要です。つまり、自分の持分だけを贈与する分には、他の共有者が反対していても登記手続きは進められます。
ただし、贈与後の持分構成が変わることにより、将来的な不動産の使用・売却・分割協議に支障が出ることもあります。
そのため、以下のような場合には、事前に共有者へ通知・相談しておくのがベターです。
-
不動産の利用方法が変わる可能性がある
-
共有者との関係性が希薄または悪化している
-
贈与により共有者の構成が増える(相手が配偶者や子どもなど)
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
トラブル回避のための3つの実務ポイント
贈与によってトラブルや税務上の誤認識を招かないため、以下の3点を必ず押さえておきましょう。
① 不動産の評価額を事前に確認
固定資産税評価額ではなく、実勢価格や路線価ベースで贈与税が算出されるケースもあります。不安がある場合は、税理士や不動産鑑定士に相談を。
② 登録免許税・登記費用の準備を
贈与による登記は自己負担が原則です。登録免許税に加え、司法書士へ依頼する場合は報酬(3〜10万円程度)が必要です。
③ 税務署への申告漏れに注意
贈与税の申告は翌年の2月1日〜3月15日までに行う必要があります。申告漏れがあると追徴課税や延滞税が課せられるリスクがあるため要注意です。
贈与か売買か?選択肢としての比較も重要
共有持分を譲渡する場合、贈与ではなく売買という方法も選択肢の一つです。以下のような比較表を参考に、どちらが最適かを検討しましょう。
| 区分 | 贈与 | 売買 |
|---|---|---|
| 取得者の負担 | 贈与税+登記費用 | 購入代金+登記費用+登録免許税(2%) |
| 登録免許税 | 2%(固定) | 2%(同様) |
| 譲渡所得税 | 発生しない | 売主に発生する可能性あり |
| 手続き | 贈与契約書+登記 | 売買契約書+登記 |
税負担や親族間の意図を総合的に考慮し、適切な手法を選ぶことが、結果的にリスク回避につながります。
共有名義の不動産を贈与する際には、自分の持分に限り贈与可能であり、登記や税務面での手続きが必要です。贈与契約書の作成と登記申請、そして贈与税の申告が基本的な流れとなります。
また、他の共有者の同意は原則不要ですが、今後のトラブルを防ぐためにも事前の相談が望ましいです。贈与か売買かの選択肢についても、税負担や目的に応じて慎重に比較検討してください。


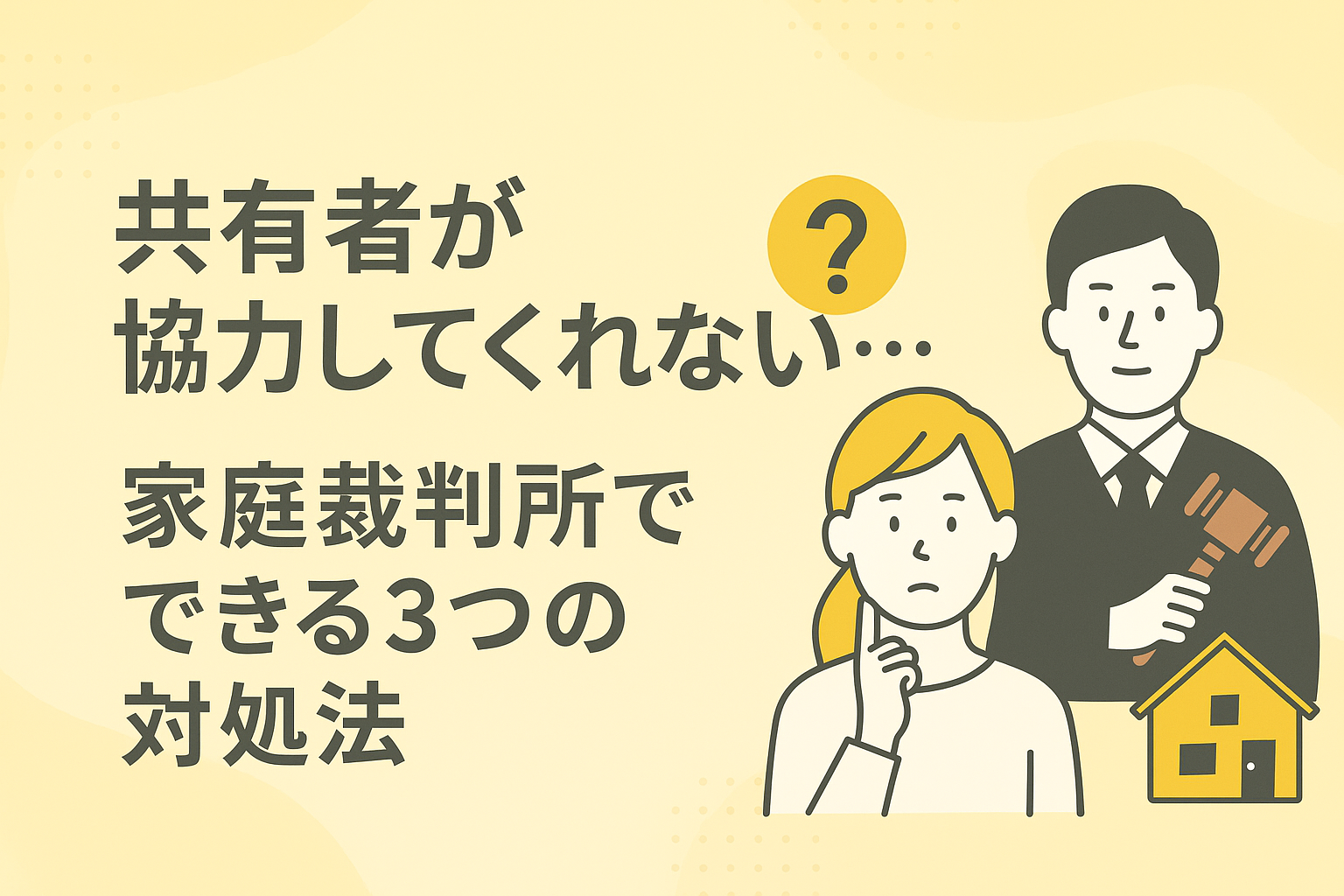






父から相続した土地を兄弟3人で共有していますが、兄に持分を譲りたいんです。