【Q&A】共有持分の売却でよくある質問10選
Q1. 共有持分だけ売却することは本当に可能ですか?
はい、可能です。
共有持分は不動産全体の「一部の権利」に過ぎないため、自分の持分だけを第三者に売却することが法律上認められています。
ただし、次のような注意点があります。
-
買い手は「共有物件の一部」を購入することになるため、一般の不動産より買い手が限定されやすい
-
不動産会社によっては、共有持分だけの取り扱いをしていないケースがある
-
売却後も他の共有者とのトラブルが残ることがある

他の共有者が住んでいても、法的には持分の売却は可能です。ただし事前に意思疎通を図ることで後々のトラブルを回避できます。
Q2. 相場よりも安く買い叩かれると聞きましたが本当?
共有持分は「利用制限」があるため、通常より安く評価されがちです。
買主側からすると、単独利用できず、他の共有者との交渉・リスクを抱えるため、相場より30〜60%程度安くなるのが一般的です。
実際の価格差は下記のような要因で変動します。
| 要因 | 影響度 |
|---|---|
| 他共有者との関係性 | 高 |
| 持分の割合 | 中 |
| 対象不動産の流動性 | 高 |
| 地域の需要 | 中 |
Q3. 他の共有者の同意がなくても売却できますか?
自分の持分であれば、共有者の同意は不要です。
ただし注意点もあります。
-
売却によって共有者間の関係悪化が起こる可能性がある
-
他の共有者が買主に対して利用制限や抵抗を示すケースも
-
名義変更手続き(登記)自体は単独で可能
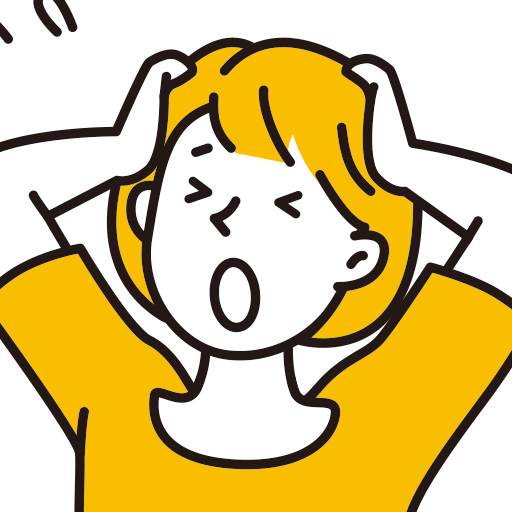
兄に内緒で売却したら、すごく怒られて…後からトラブルになるとは思いませんでした。

法律上問題なくても、感情的な対立が残るケースは多いです。事前相談が結果的にスムーズな解決に繋がります。
Q4. 税金はどれくらいかかるのですか?
売却時には譲渡所得税(20.315%)がかかる可能性があります。
【譲渡所得の簡易計算式】
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 諸経費)
取得費が不明な場合、**概算で売却価格の5%**とするケースが多く、その分課税額が大きくなるので注意が必要です。
また、相続した不動産であれば「取得費加算の特例」や「空き家特例」などの節税対策が可能な場合もあります。
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
Q5. 売却しないで「他の共有者に譲渡」する選択肢はありますか?
はい、贈与や持分譲渡契約により、家族や他共有者に持分を移すことが可能です。
-
譲渡(売買)の場合 → 譲渡所得税が発生
-
贈与の場合 → 贈与税(最大55%)がかかることも
なお、同居の親族間などで無償移転をする場合は、登記上でも**原因「贈与」**となるため、贈与税の申告が必要です。

兄にタダで譲ったら税金がすごいって言われて…どういうこと?

贈与は税務署にしっかり見られます。譲渡ではなく、贈与だと判断されると高額の贈与税が発生するため注意が必要です。
Q6. 共有持分を高く売るコツはありますか?
高く売却するには、「売却対象の見せ方」と「相手選び」が重要です。
特に有効な工夫は以下のとおりです。
-
不動産専門の弁護士やコンサルタントに相談する
-
共有状態でも購入希望が多いエリアであれば需要を見込める
-
収益物件(賃貸中)として売り出すことで投資家に訴求できる
-
買取業者よりも一般投資家に直接売るルートを探す

安くなると聞いて焦ってましたが、収益物件として出したら予想以上の金額で売れました!

所有物件が「利回りのある賃貸」として訴求できる場合、一般より高く売れることがあります。
Q7. 売却先の相手は誰が多いですか?
実際に共有持分を購入する相手は以下のようなパターンが主流です。
| 買主のタイプ | 特徴 |
|---|---|
| 他の共有者 | 話がまとまればスムーズ、感情面の配慮も必要 |
| 不動産業者 | 現金化は早いが価格は抑えられる傾向 |
| 投資家 | 収益性があれば高額売却も見込める |
| 任意の第三者 | 利用が制限されるため慎重に動く |
中でも最近は「共有持分買取専門業者」の数が増えており、即現金化したいニーズに対応可能です。
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
Q8. 売却後に共有者とトラブルになることは?
あります。
特に下記のようなケースで感情的な対立に発展しやすくなります。
-
無断で売却したことに対する不満
-
買主が業者で、共有状態をビジネス的に扱ってくる場合
-
他の共有者の生活空間を侵害されたと感じるとき

売ったらその後、元共有者から無視されてしまって…親族なのに辛かったです。

法的には問題がなくても、共有関係には感情面の配慮が必要です。円満に進めるためには、事前の説明が効果的です。
Q9. 売却にかかる時間はどれくらい?
ケースによって異なりますが、以下が一般的な目安です。
-
専門買取業者に依頼した場合:最短1〜2週間
-
一般投資家への売却:1〜2ヶ月
-
他の共有者との交渉含む場合:3ヶ月以上かかることも
スピードを重視する場合は、買取業者への一括相談が効率的です。
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
Q10. 相談するならどこに連絡すべき?
まずは共有持分に詳しい専門家に相談しましょう。
以下のような相談先があります。
-
司法書士・不動産弁護士:法的観点から整理
-
不動産会社(共有持分専門):売却価格や流れの説明
-
行政書士や税理士:贈与や相続絡みのアドバイス
複数の専門家に無料相談できるサービスもあるため、まずは見積・意見を集めることから始めましょう。

何から手をつけていいかわからなかったけど、無料相談で道筋が見えました!

一人で悩まず、経験豊富な専門家に早めに相談するのがスムーズな解決への第一歩です。
共有持分の売却には、法的なルールだけでなく、人間関係や相場価格の落差など、複数の要素が絡み合います。
疑問を一つずつ解消しながら、最適な売却方法を選ぶことが重要です。無料相談や専門家の知見を活用し、後悔のない手続きを目指しましょう。




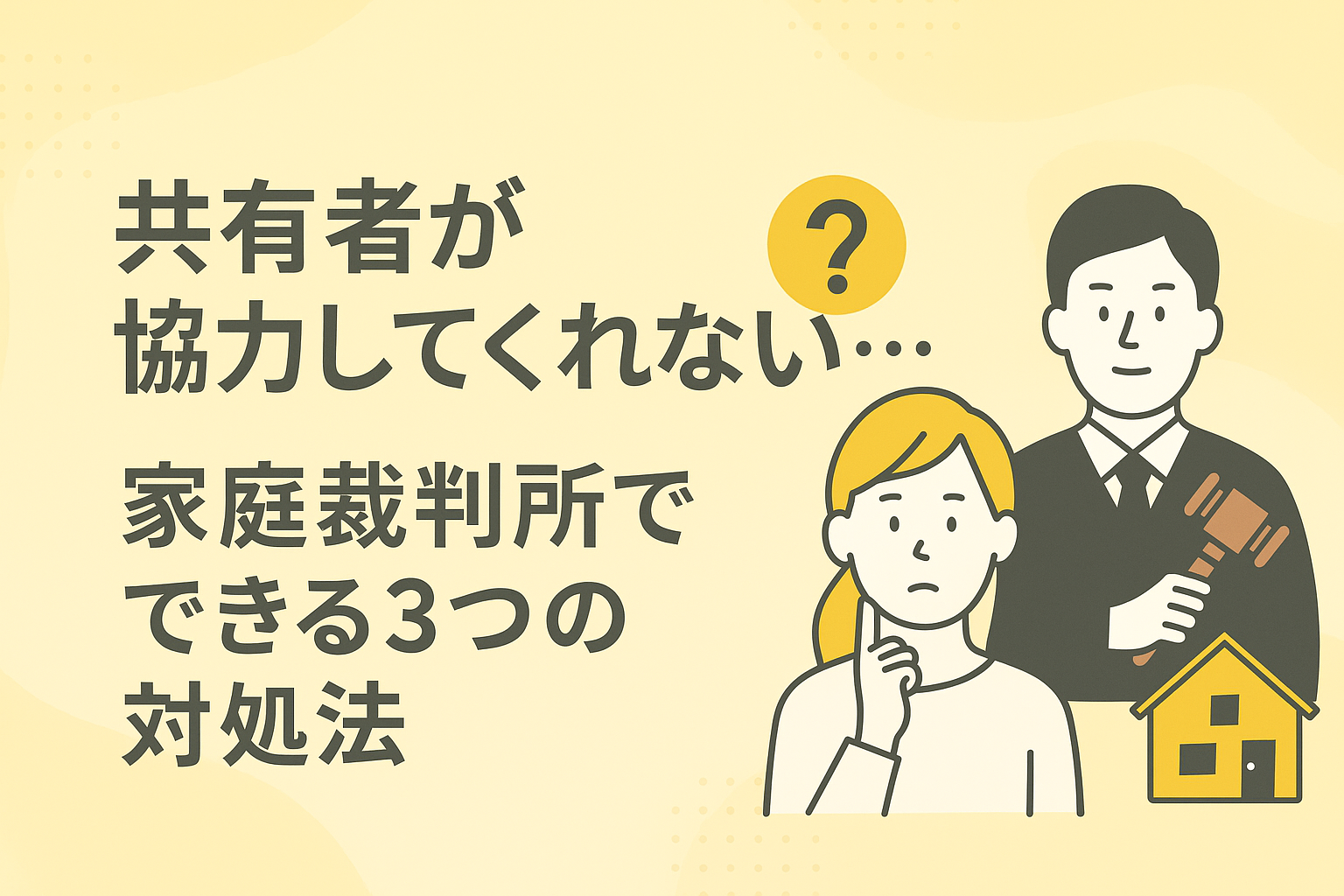
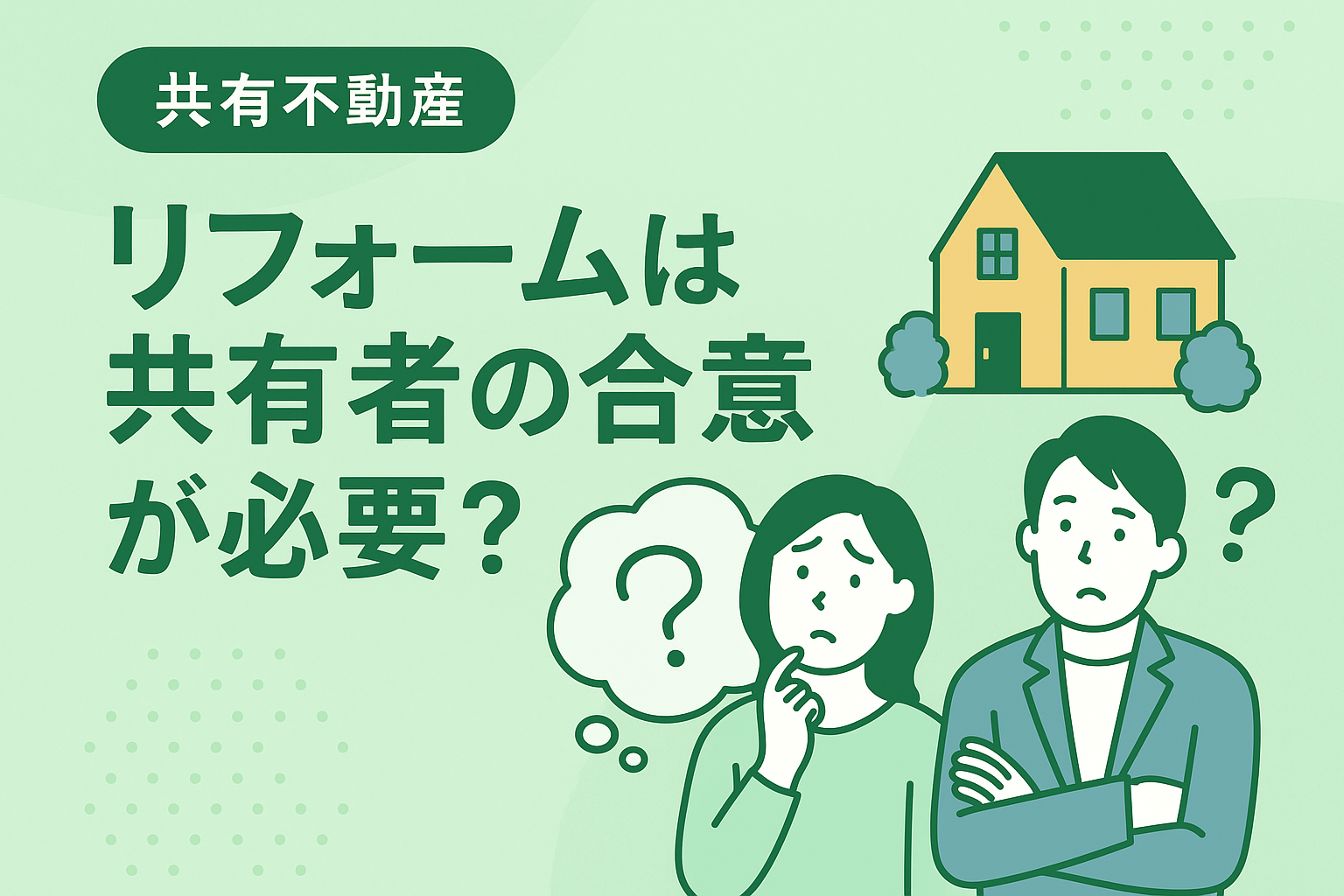

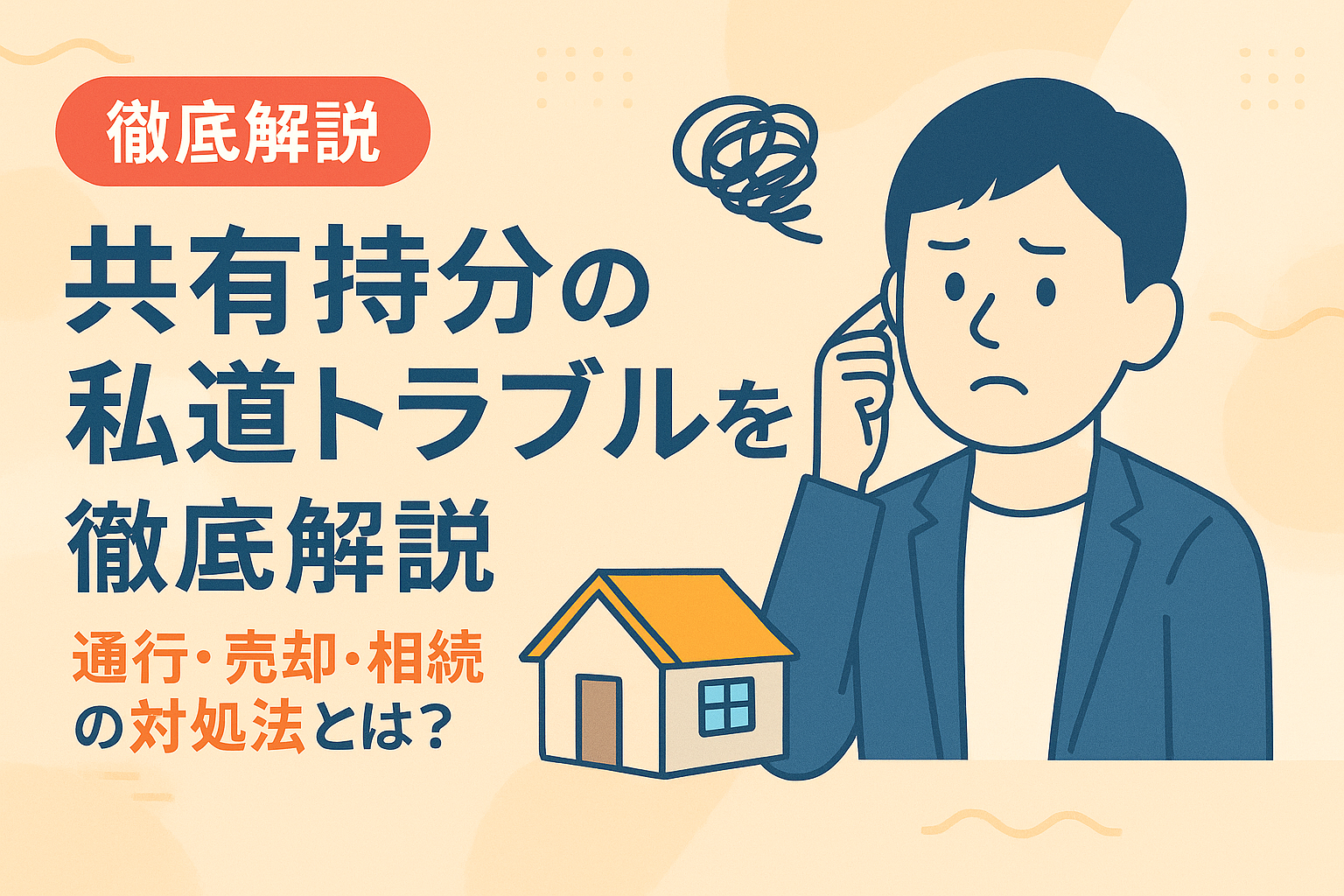


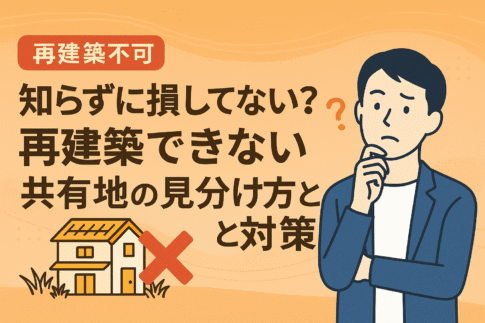
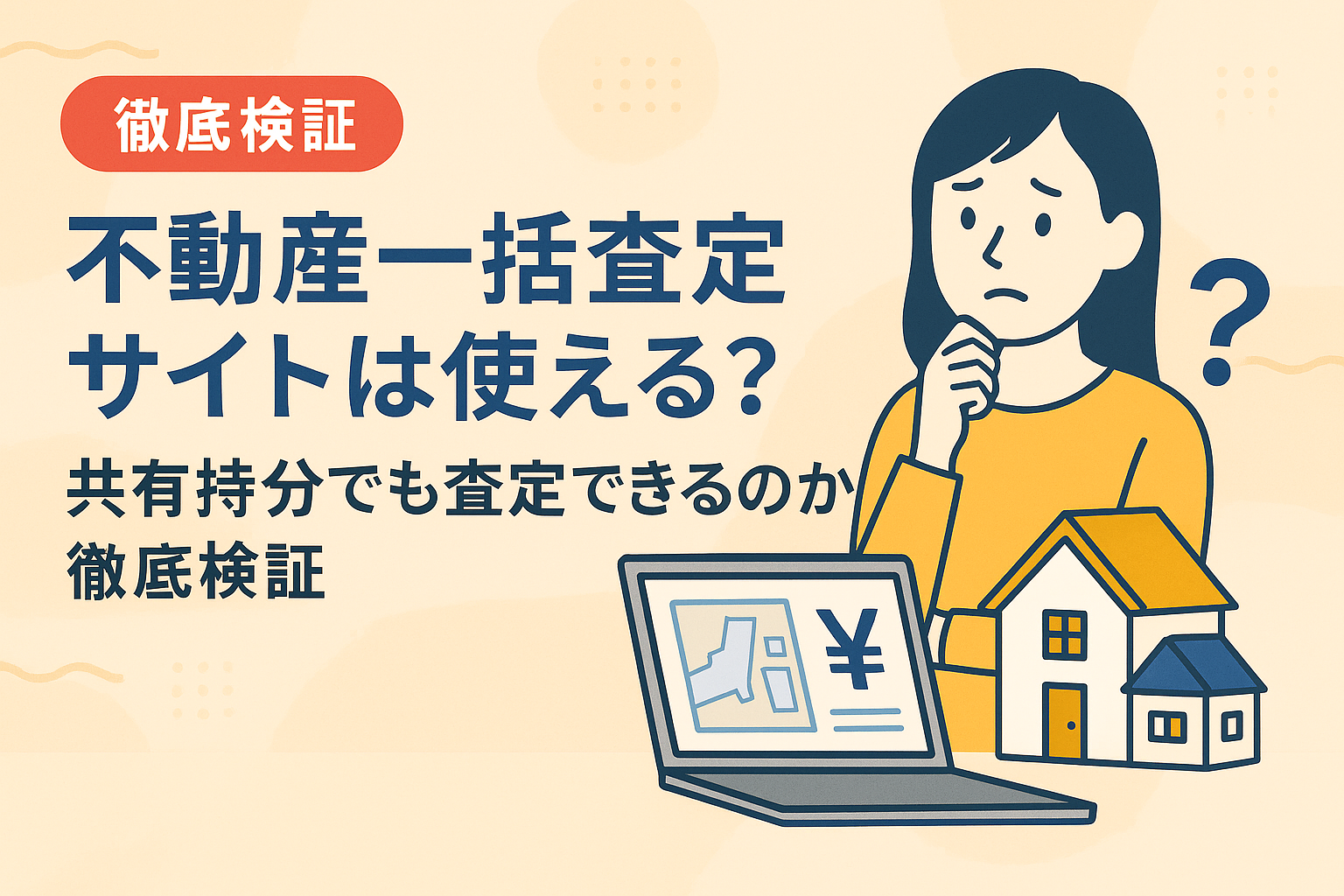




兄弟と相続した実家の持分を売りたいのですが、他の共有者が住んでいて迷惑になりませんか?