持分トラブルで裁判に?訴訟リスクと回避方法をわかりやすく
持分とはそもそも何か?トラブルが起きる背景を理解しよう
共有持分とは、複数人で不動産を共同所有している場合の各人の所有権割合のことを指します。たとえば、兄弟3人で1つの空き家を相続した場合、それぞれが1/3ずつの持分を持っている状態です。
このような「共有状態」は以下のような場面で発生します。
-
親族間の相続
-
離婚時の財産分与
-
投資目的での共同購入
-
親が子に名義を分け与える贈与
特に相続などで自然発生的に共有関係が生じるケースでは、「不仲」や「放置」によってトラブルに発展することが少なくありません。
どんなときに裁判に発展するのか?
共有持分のトラブルがこじれると、最終的に訴訟(裁判)に発展することがあります。以下はその代表例です。
よくある裁判に発展するケース
| トラブルの内容 | 裁判になる主な理由 |
|---|---|
| 売却したいが他の共有者が反対 | 持分売却の同意が得られない |
| 自費でリフォーム後に費用負担を拒否された | 費用負担の割合・合意の有無 |
| 賃貸収入の分配でもめている | 収益分配に関する合意不成立 |
| 勝手に建物を取り壊された | 所有権侵害・損害賠償請求 |
| 相手が行方不明で連絡が取れない | 不在者財産管理人の選任申立て |
こうしたトラブルは、感情的なもつれも加わって話し合いでは解決困難になることが多く、やむを得ず訴訟へ…というケースが増えています。
訴訟になった場合のリスクとは?
裁判は法的に問題解決を図る有効な手段ではありますが、それに伴うリスクやデメリットも無視できません。
1. 時間と費用の負担
裁判には平均して半年〜1年以上かかるケースもあり、その間に精神的・金銭的負担が増します。弁護士費用はケースによっては数十万円〜100万円を超えることも。
2. 人間関係の破綻
共有関係が続いている限り、裁判後も同じ物件を持つ関係が続くため、裁判で関係が悪化すると将来的な処理がさらに難航します。
3. 判決が想定外になることも
たとえばリフォーム費用の請求訴訟では、「共有者全員の事前同意がなかった」として、費用が認められない判決になることもあり得ます。

訴訟は最終手段です。交渉や第三者の介入、法的支援制度なども検討しましょう。
訴訟リスクを回避するためにできること
訴訟を避けるには、「トラブルを未然に防ぐ視点」と「発生しても拡大させない工夫」の両方が必要です。
合意形成のプロセスを丁寧に
・口頭ではなく書面で合意を残す
・費用負担や利用方法を共有契約書に明記
・定期的なミーティングや連絡手段を確保
専門家を介した話し合い
・司法書士や弁護士など第三者を交えて協議
・不動産会社や共有持分買取業者を仲介に活用
・家族信託や遺言書の活用も有効
自分の持分だけを売却するという選択肢
もし合意形成が難航する場合は、自分の持分だけを売却することも選択肢の一つです。これは合法的に可能であり、近年は「共有持分専門の買取業者」も増えてきました。
誰に相談すべき?無料相談や支援制度の活用を
裁判を回避しつつ、専門的な判断やサポートが必要な場面では、公的な相談窓口や士業の力を借りることが有効です。
無料で相談できる主な窓口一覧
| 窓口 | 内容 |
|---|---|
| 法テラス | 弁護士相談・費用立替制度など |
| 各市区町村の法律相談 | 市役所や区役所の定期相談会 |
| 不動産トラブル相談センター | 共有持分や相続関連の相談に対応 |
| 公証役場 | 遺言・契約書作成の相談 |
| 家庭裁判所 | 相続放棄や不在者管理などの申立てが可能 |
これらは多くの場合、初回無料相談が利用できます。自治体によっては予約制や曜日が限られているため、事前確認が必要です。

誰に相談したらよいのか分からなくて、つい後回しにしてしまいます…

まずは市役所の無料相談や法テラスがおすすめです。相談内容に応じて最適な窓口を紹介してくれますよ。
裁判を避けるために知っておきたい法律のポイント
民法の基本ルールを理解する
持分に関するルールは民法で定められており、以下のような原則があります。
-
【共有物の変更】共有者全員の同意が必要
-
【保存行為】1人でも可能(例:修繕、登記)
-
【持分の譲渡】他共有者の同意は不要
-
【分割請求】いつでも可能(ただし相手にとっては負担)
上記を知らずに行動すると、結果的にトラブルの原因となるケースが多く見られます。
持分売却や解消の選択肢
「共有関係に疲れた」「話し合いが成立しない」といった場合には、以下のようなアクションが現実的です。
-
自分の持分のみを第三者へ売却
-
他の共有者に持分を譲渡(贈与・売買)
-
家庭裁判所に共有物分割請求を行う(強制分割)
特に最近では、共有持分を専門に扱う買取業者に依頼して、他の共有者と交渉する代行まで含めて委託するケースも増えています。
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
トラブルを避けるには「持分を整理」するのがベスト
長期的に見て、持分のまま所有し続けることで発生するリスクは以下の通りです。
-
自分の意向で売却・利用ができない
-
修繕費や固定資産税の負担だけが残る
-
他共有者の動き次第でトラブルに発展
-
将来的に相続が重なりさらに関係者が増える
共有関係がこじれる前に、**「単独所有」や「売却による関係の解消」**を考えておくことは、法的にも感情的にも良い選択です。
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
共有持分のトラブルは、感情面だけでなく法的にも複雑化しやすく、放置すると裁判沙汰に発展するリスクがあります。
特に相続や兄弟間の共有では、話し合いが難航しやすく、時間や費用の負担が大きくなりがちです。
裁判に至る前にできる対策として、第三者を交えた交渉や専門機関の相談、自分の持分だけを売却する方法なども視野に入れましょう。
法的知識を正しく持つことが、トラブル回避への第一歩となります。






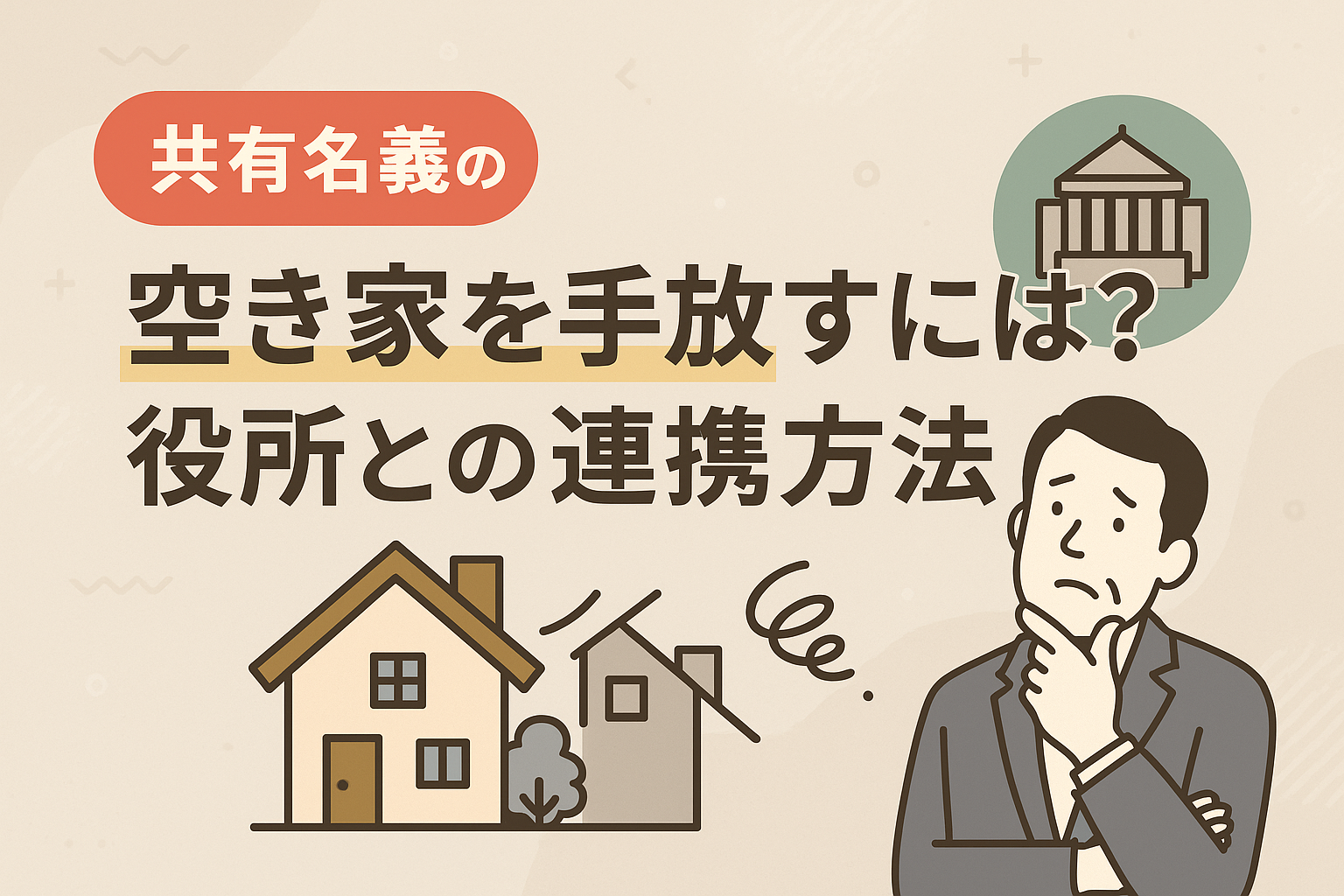



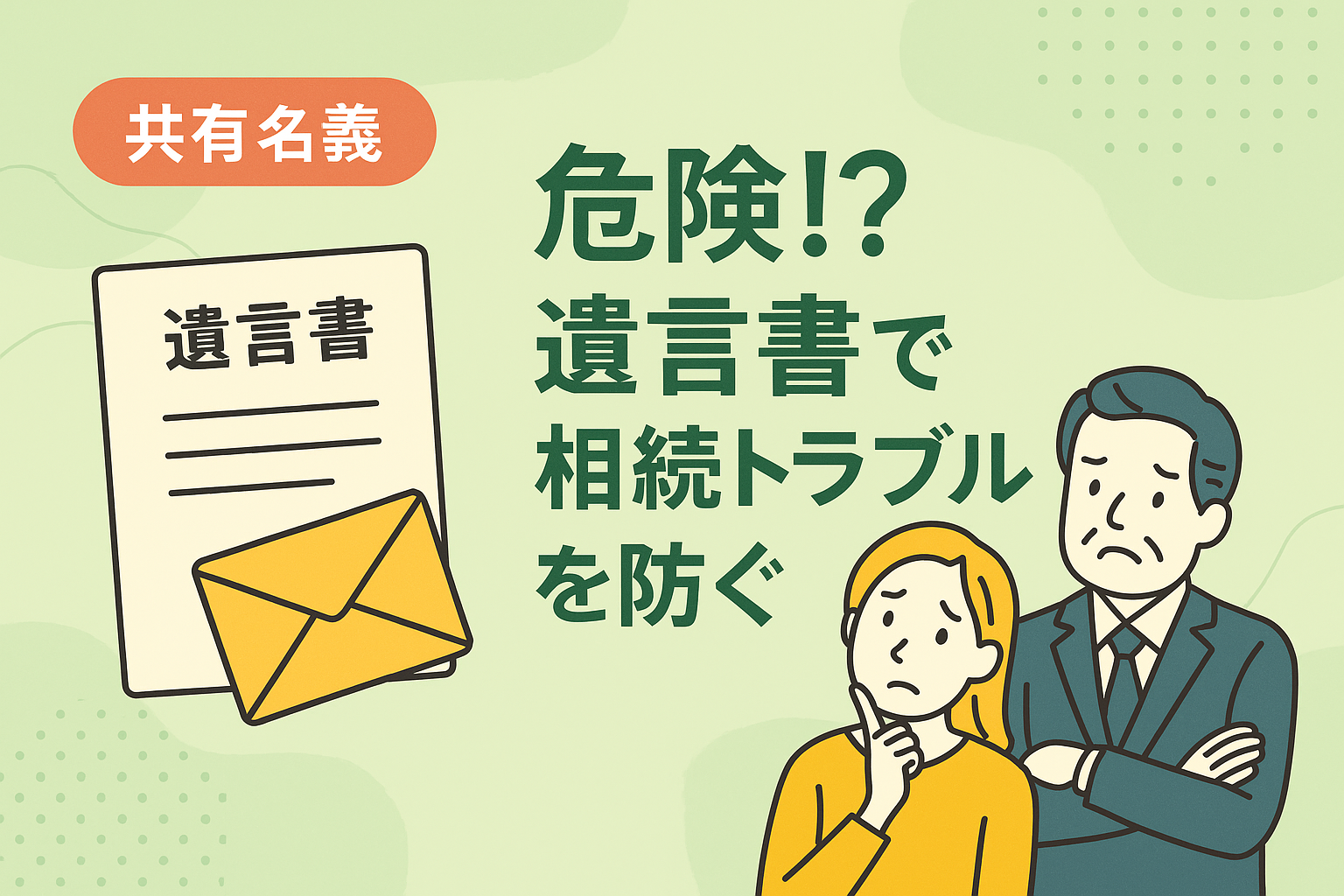








他の共有者が何を考えているかわからないし、話し合いもうまく進まないから裁判するしかないのかな…?