共有持分を巡って家庭裁判所に頼るとどうなる?調停・審判の流れを解説
共有不動産における持分トラブルは、親族間や相続人同士など感情の対立を伴うケースが多く、話し合いだけでは解決が難航することも少なくありません。そうした場合に選択肢となるのが、家庭裁判所による「調停」や「審判」です。
ここでは、共有持分に関する調停・審判の基本的な流れと、それぞれの違いや注意点について解説します。
共有持分トラブルで家庭裁判所を利用するケースとは?
相続や売却、使用方法での対立が中心
共有持分トラブルで裁判所に相談する代表的なケースは以下の通りです。
-
他の共有者が売却に同意しない
-
自分だけが固定資産税を支払っている
-
空き家のまま放置されていて管理負担が大きい
-
相続人の一人が行方不明で処分ができない
特に、「全員の合意が必要」という共有のルールがネックとなり、話し合いが難航しやすいのが実情です。
家庭裁判所に申し立てる2つの方法
共有持分に関する紛争解決のために、家庭裁判所では主に以下の2つの手続きが用意されています。
1. 調停(共有物分割調停)
調停は、裁判所の調停委員を交えて当事者間の話し合いを行い、合意による解決を目指す手続きです。
-
調停委員(法律や不動産の専門家など)が中立的に仲介
-
原則として非公開
-
合意が成立すれば、法的拘束力を持つ「調停調書」が作成される
2. 審判(共有物分割審判)
調停で合意に至らなかった場合、または相手方が出席しない場合などは、自動的に審判へ移行します。
-
裁判官が証拠や主張を踏まえて一方的に判断
-
審判には強制力があり、共有者の同意がなくても分割が可能
-
審判に不服がある場合は即時抗告が可能

そのような場合は、家庭裁判所に「共有物分割調停」や「不在者財産管理人選任」の申立てを行うことで、売却が可能になるケースもありますよ。
家庭裁判所の手続きの基本的な流れ
共有物の分割調停・審判の流れは以下のようになります。
| 手続きの段階 | 内容 |
|---|---|
| 申立て | 管轄の家庭裁判所へ「共有物分割調停」などを申立て |
| 書類審査 | 申立書の内容確認、受理通知 |
| 第1回調停期日 | 調停委員との話し合い開始(1回で終わらないことも多い) |
| 合意不成立 | 合意ができなければ自動的に審判へ移行 |
| 審判の決定 | 裁判所が分割方法を決定し、強制的に執行される |
審判で決定される分割方法の種類
家庭裁判所の審判で共有不動産を分割する際には、状況に応じて3つの方法が選択されます。
現物分割
物理的に不動産を分けて、それぞれの持分に応じた形で所有権を分ける方法です。土地や建物が広い場合に有効ですが、実務上は難しいケースが大半です。
代償分割
1人が不動産全体を取得し、他の共有者には金銭で精算する方法です。住宅ローンがある場合や売却を前提としないケースで利用されます。
換価分割
不動産を売却して、その売却代金を共有持分に応じて分け合う方法です。最も現実的で多く選ばれる方法とされています。
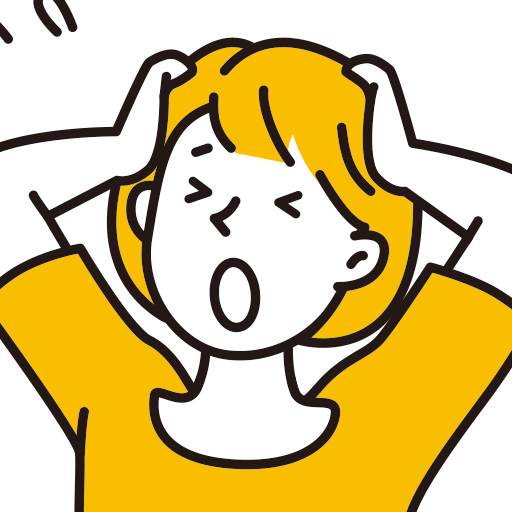
私が家を出ていったあとも兄が勝手に使い続けているのに、売却にも応じてくれません…

その場合、家庭裁判所で換価分割を求めれば、兄の同意がなくても売却を実現できる可能性があります。
家庭裁判所を利用する際の注意点
申立書類や資料の準備が必要
共有者の情報や不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書など、多くの書類を用意する必要があります。これらの準備には時間がかかるため、早めの着手が重要です。
手続きには時間と費用がかかる
調停は数ヶ月〜1年以上かかることもあり、審判へ移行した場合はさらに長期化します。費用についても、弁護士報酬や申立てにかかる印紙代などが発生します。
心理的ストレスや関係悪化のリスク
家庭裁判所を利用すると、共有者間の対立が深まり、親族間の関係悪化に繋がることもあるため、注意が必要です。
弁護士など専門家への相談が有効
共有持分トラブルは複雑で感情的な問題が絡みやすいため、専門家のサポートが重要です。
-
調停や審判の申立書作成
-
適切な分割方法のアドバイス
-
不在者がいる場合の財産管理人選任の手続き
こうした支援を受けることで、スムーズで適法な解決が可能になります。
共有持分を巡るトラブルで話し合いが難航した場合、家庭裁判所への「調停」や「審判」の申立てが有効な手段となります。調停では話し合いによる解決を、審判では裁判所による強制力ある判断を受けることができます。換価分割や代償分割などの方法で、共有不動産の問題を法的に解決することが可能です。煩雑な手続きやリスクを避けるためにも、弁護士などの専門家への相談を早期に検討することをおすすめします。

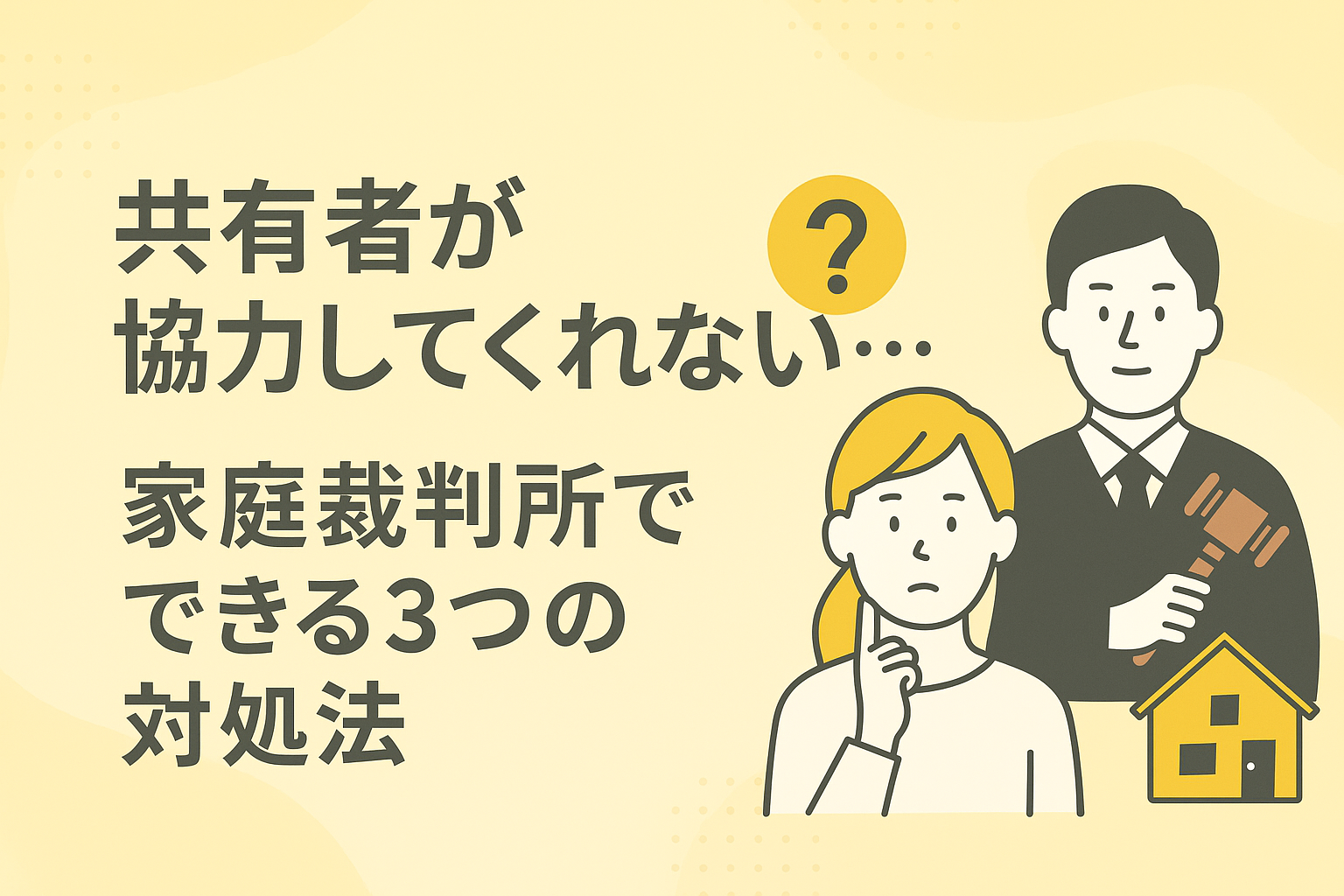



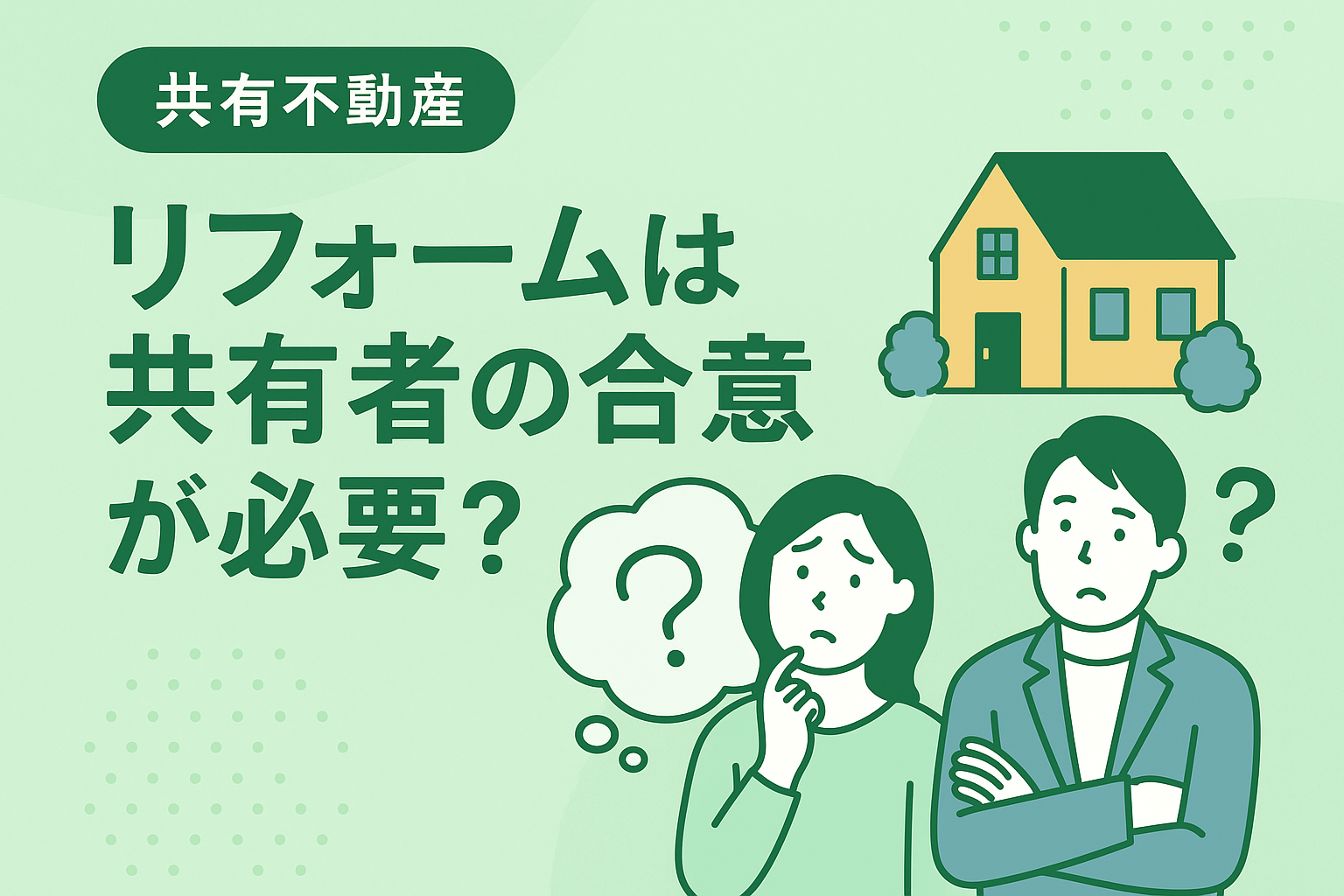









空き家の共有者の一人が音信不通で、どうやって売却すればいいか分かりません…