売却代金はどう分ける?共有者が複数いる場合の配分方法
複数人で所有する不動産を売却したとき、どう分ける?
共有名義の不動産を売却したとき、**最も重要なポイントのひとつが「売却代金の分配」**です。
兄弟姉妹や夫婦、親戚同士など、複数の共有者が関わる場合には、金銭の配分を巡ってトラブルになることも少なくありません。
そもそも「どのような割合で分けるのが正しいのか?」「名義と出資が違う場合はどうするのか?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、不動産売却時における共有持分ごとの代金配分の仕組みや注意点、トラブル防止の方法を具体的に解説します。
共有名義の不動産と売却時の基本ルール
不動産が「共有名義」になっている場合、登記簿に持分割合が明記されています。
たとえば、以下のような登記内容です。
-
甲:1/2(50%)
-
乙:1/4(25%)
-
丙:1/4(25%)
このような場合、原則として売却代金も持分の割合に応じて分けることが基本となります。

原則は登記された持分割合に基づいて分配します。もし実際の出資や事情が異なる場合は、事前に合意書を交わしておくと安全です。
登記上の持分と実際の出資割合が違う場合
実務上は「登記上の持分割合」と「実際の出資割合」が一致していないケースが多く見られます。
たとえば、以下のようなケースです。
-
Aさんが物件価格の70%を出資
-
Bさんが30%を出資
-
しかし登記は1/2ずつ(50%)になっている
この場合、登記上は50%ずつなので、売却代金も半々に分配されるのが原則です。
しかし、Aさんが「自分のほうが多くお金を出したのに」と不満を持つようなケースでは、トラブルに発展する可能性があります。
こうした事態を避けるためには、あらかじめ**「共有合意書」や「金銭授受の記録」**を残しておくことが重要です。
スムーズに分配するための3つの準備ポイント
スクロールできます →
| 準備内容 | 解説 |
|---|---|
| 登記簿謄本の確認 | 各共有者の正式な持分割合を明確にしておく |
| 出資額と持分の一致確認 | 出資と登記割合がズレている場合は協議と記録が必要 |
| 口座情報の事前共有 | 売却代金の振込先を全員分まとめて不動産会社に伝える |
不動産会社の役割と注意点
多くのケースでは、売却を仲介した不動産会社が代金の分配もサポートしてくれます。
売買契約時に、**売主が複数人いる場合の配分指示書(配分依頼書)**を作成し、それに従って代金を送金します。
ただし、配分のトラブルは仲介会社が介入できないケースもあるため、全員の合意が前提です。
複雑なケースでの配分方法とトラブル回避策
名義変更がされていない相続持分の売却
共有者の一人が亡くなっていた場合、売却の前提として相続登記(名義変更)が完了していることが必要です。
しかし、実務では「相続登記が未了のまま売却を進めようとする」ケースが非常に多くあります。
この場合、代金の配分どころか、そもそも売却契約そのものが成立しないリスクがあるため要注意です。

父が亡くなって登記はそのまま…。その共有名義の一部を今すぐ売りたいのですが可能ですか?

相続登記が済んでいないと、法的には売却できません。名義変更後、共有者の間で合意が必要になります。
売却代金が一時的に1人に支払われるときの注意点
契約の都合や、共有者の数が多い場合などには、いったん代表者の口座に全額を入金してから他の共有者に分配するという形式がとられることがあります。
しかしこの方法は、後の金銭トラブルや贈与税リスクの引き金となる場合があるため、避けるか、合意書・覚書の作成が必須です。
特に、税務署から「贈与」とみなされると、思わぬ課税が発生する可能性があるため要注意です。
贈与税リスクを避けるには?
以下のような状況では、贈与とみなされる可能性があります。
-
登記持分が1/3なのに、売却代金の50%を受け取った
-
口約束だけで配分比率を変えてしまった
-
第三者(例:親族外)が代金の一部を受け取った
こうしたケースでは、**「本来の持分を超えて金銭を得た」**とされ、贈与税の課税対象になる可能性があります。
スクロールできます →
| 状況 | 贈与税リスク | 対応策 |
|---|---|---|
| 登記と異なる配分 | 高 | 合意書を公正証書で作成する |
| 親族間で不均等な配分 | 中 | 納得のうえ事前協議・説明を徹底 |
| 売却益の一部を譲渡 | 高 | 立証が困難な場合は避ける |
トラブルを未然に防ぐ3つの対策
-
事前に合意書を作成
-
配分方法・金額を明記し、共有者全員が署名
-
-
司法書士や税理士への相談
-
専門家に間に入ってもらうことで公平性・信頼性を担保
-
-
配分の証拠を残す
-
銀行送金履歴・LINEなどのやり取りも保存しておく
-
共有持分の売却代金は、原則として登記された持分割合に応じて分配されます。ただし、実際の出資割合や親族間の合意内容によっては異なる分配となることもあります。トラブルや税務上のリスクを避けるには、事前の協議・合意書の作成・専門家の介入が有効です。後悔のない売却を実現するために、慎重な準備が欠かせません。




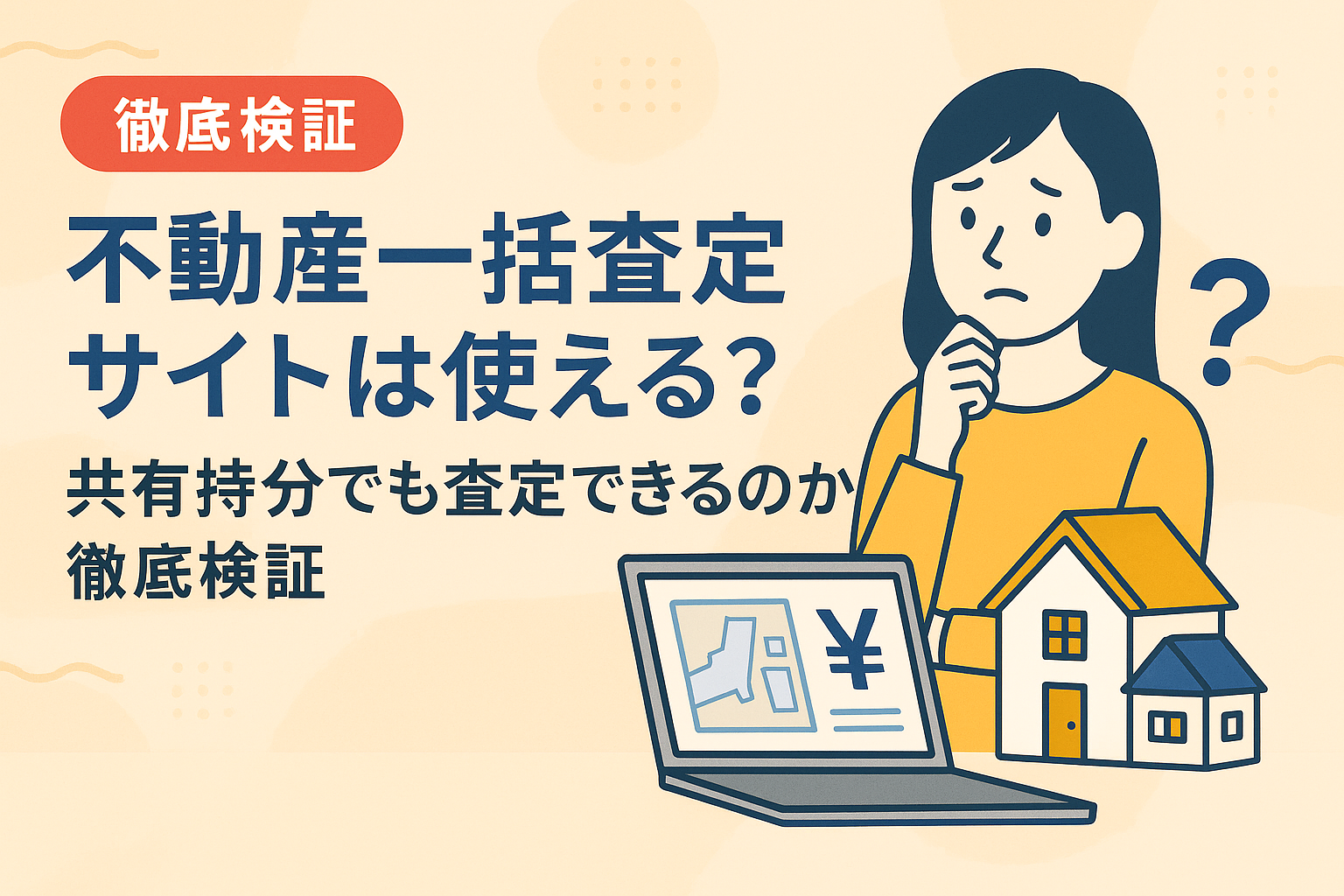

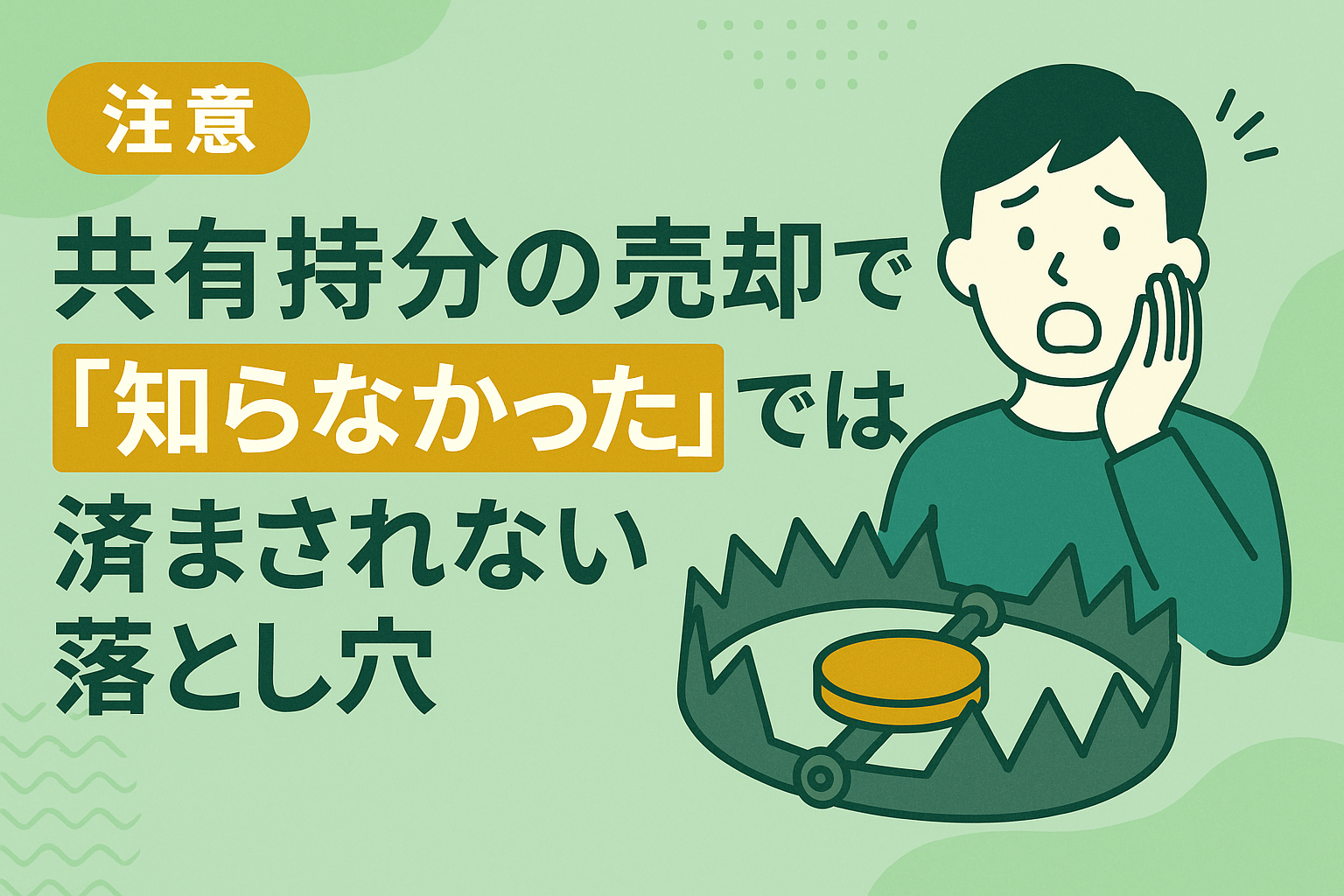


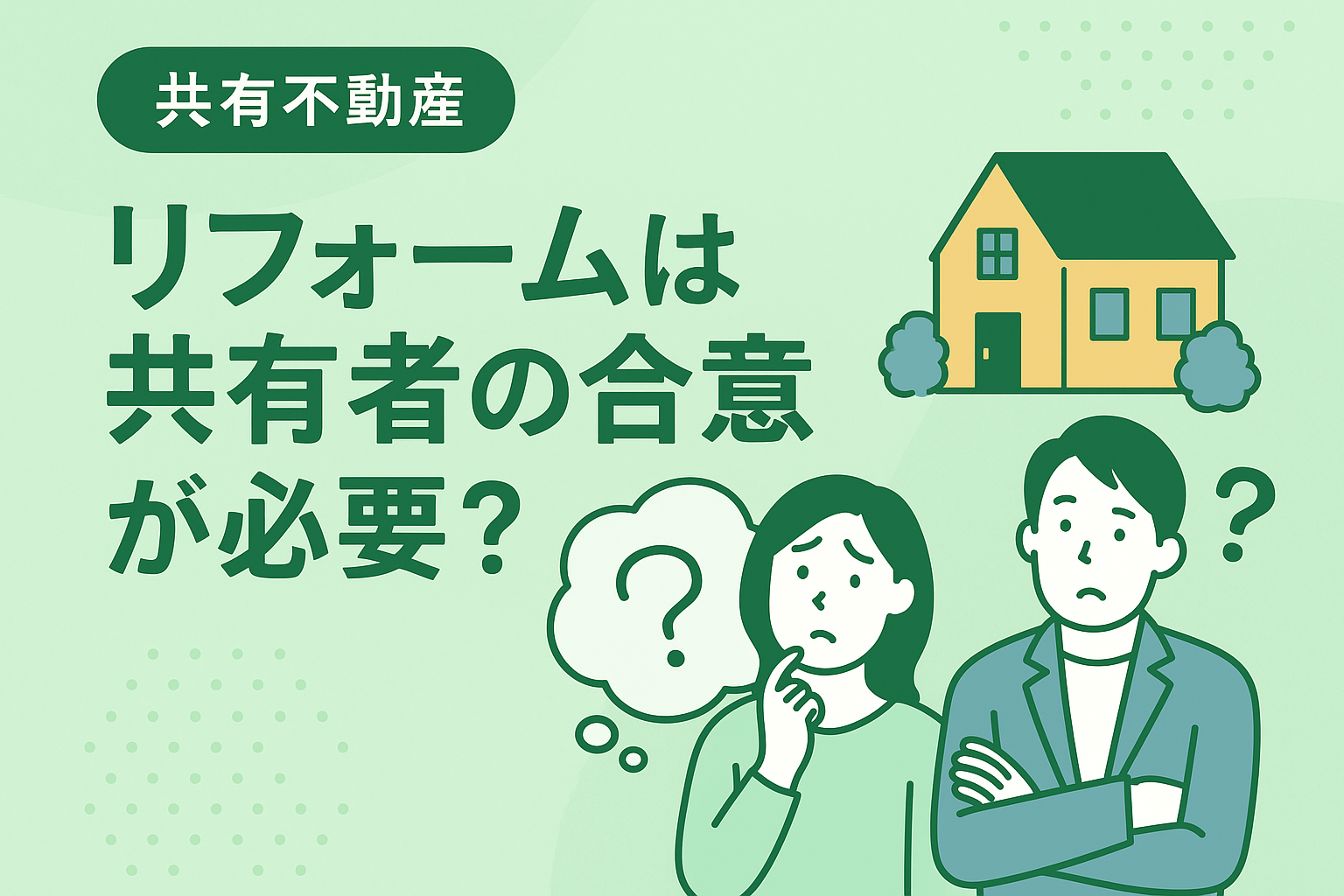

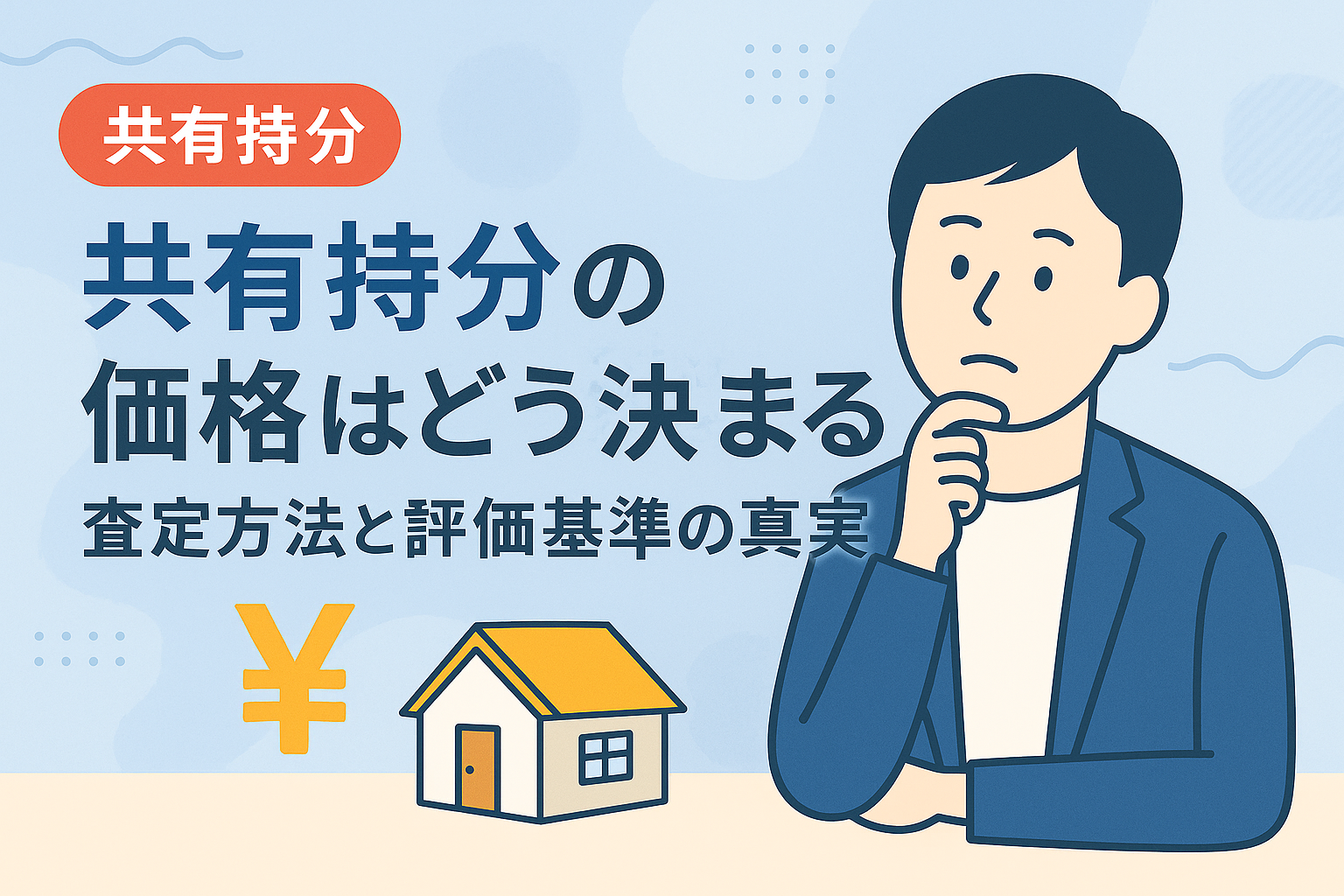

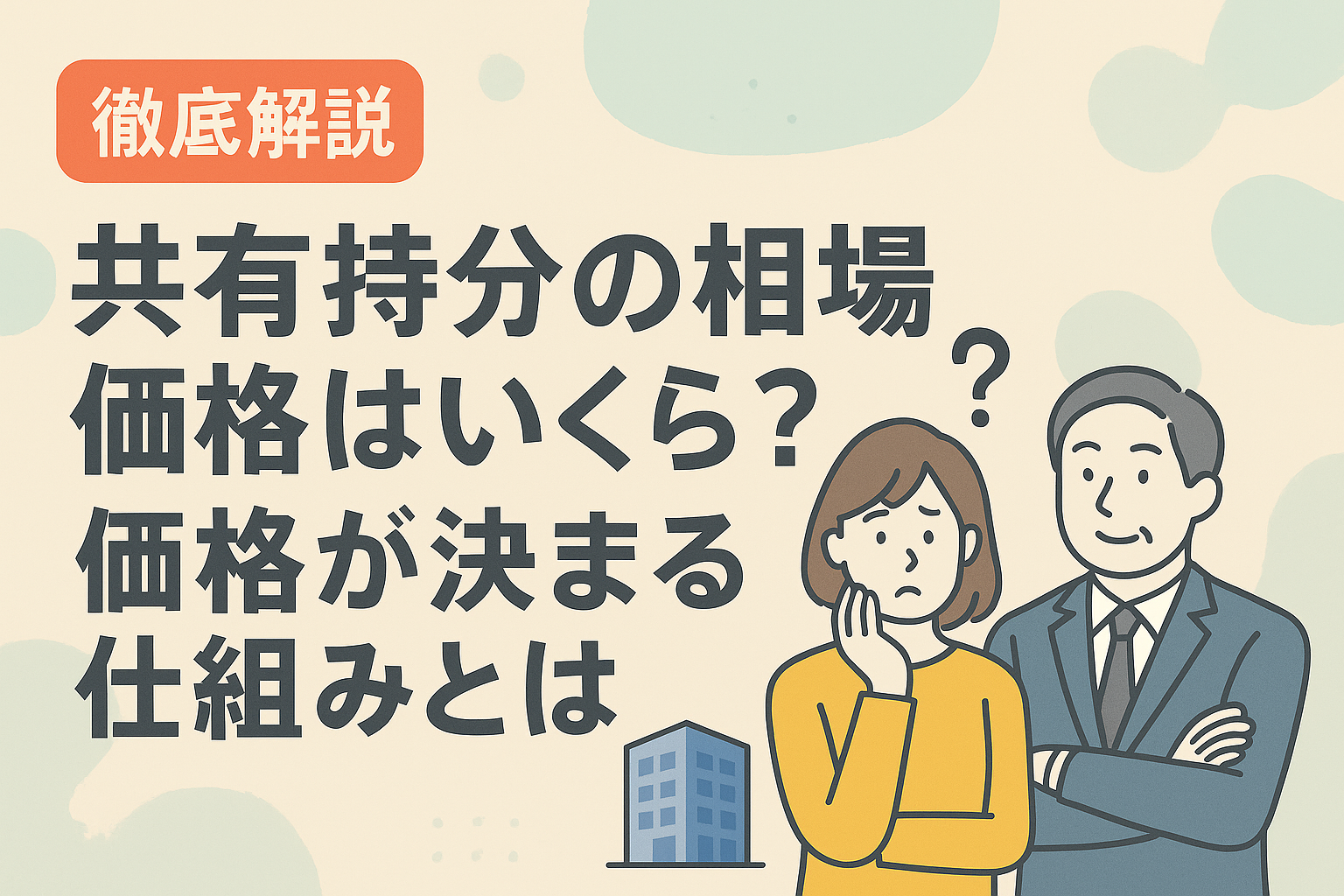





実家を兄弟3人で売却したんですが、どうやって分けたら公平になるのかわからなくて…