相続放棄したのに税金が請求される?誤解されがちな「共有持分」の落とし穴
不動産の相続において「相続放棄をすれば一切の責任がなくなる」と考えている方も少なくありません。しかし、実際には**「共有持分」**の存在によって、思わぬトラブルや税金の請求が発生するケースがあります。
とくに、相続した不動産に複数の相続人が存在し、それぞれが共有持分として所有していた場合、相続放棄と所有権の関係を正しく理解していないと、放棄したつもりが固定資産税の納付義務が残っていたなどの状況に陥る可能性もあるのです。
ここでは、実際に起こり得るトラブルを例に、「共有持分」と「相続放棄」の関係を整理しながら、なぜ税金請求が届くのか、どのように対応すべきかをわかりやすく解説します。
相続放棄の基本:全てを放棄すれば無関係?
まず前提として、相続放棄とは、被相続人の財産(プラス・マイナス問わず)を一切相続しない意思表示のことです。これは、家庭裁判所に申述し受理されることで効力を持ちます。
通常の相続放棄であれば、以下のような財産や責任も放棄の対象です。
-
不動産(土地・建物)
-
預貯金・有価証券
-
借金・連帯保証などの債務
-
固定資産税などの税金負担
しかし、実務ではこの「相続放棄」が完全には効力を持たない場合があり、なかでも問題になりやすいのが**「登記上の共有名義が残っている不動産」**です。
なぜ相続放棄しても税金が請求されるのか?
相続放棄が完了しているにもかかわらず、後日自治体から固定資産税の納付書が届くケースは珍しくありません。
その原因は、多くの場合、次のような流れにあります。
スクロールできます →
| 状況 | 内容 |
|---|---|
| 相続放棄済み | 家庭裁判所により正式に受理されている |
| 登記が未変更 | 不動産の共有名義に「放棄した人」の名前が残っている |
| 市区町村の情報源 | 法務局の登記簿に基づいて固定資産税の請求を行っている |
| 結果 | 放棄者のもとに税金通知が届く |
このように、自治体の税務情報は「登記簿上の名義」を基準にしているため、放棄の事実と税務処理が一致していないことが大きな原因です。

放棄していても登記名義に残っていると請求が来ることがあります。名義変更または相続登記未了が原因かもしれません。
税金以外にも?共有持分放置によるリスクとは
放棄したと思っていても、登記簿に名前がある限り「所有者」として扱われるリスクは他にも存在します。
-
空き家による近隣トラブル(管理責任)
-
所有者不明土地問題への該当
-
強制的な費用負担(解体、特定空き家指定 など)
共有持分を放置することは、金銭的・法的なリスクだけでなく、地域社会や他の共有者との関係にも悪影響を及ぼします。
共有持分放置によるトラブルの回避方法とは?
共有持分に関するトラブルは、正しい知識と早期の対応で予防できます。以下のようなステップを意識することで、相続放棄後の税金トラブルや法的リスクを軽減できます。
登記情報を確認する
相続放棄が受理されたとしても、登記情報が更新されていない限りは「所有者」として記録されたままです。
放棄後には以下のような確認をしましょう。
-
法務局で登記簿謄本(全部事項証明書)を取得する
-
自分の氏名が残っていないか確認する
-
必要があれば、相続人全体で相続登記の整理を行う
相続放棄=登記名義も自動で消える、というのは誤解です。登記と税務は別の仕組みで管理されています。
相続放棄後の対応パターン
以下に、相続放棄と名義に関する典型的な対応パターンをまとめます。
スクロールできます →
| 状況 | 対応策 |
|---|---|
| 放棄したのに名義が残っている | 相続登記の協議・抹消手続きが必要 |
| 共有者が他にいない(単独相続) | 不在者財産管理人などの法的手続きが必要 |
| 他の相続人も放棄 | 相続財産管理人を家庭裁判所に申し立てる必要あり |

うちの兄弟はみんな放棄しちゃって、空き家が放置されてる状態なんです…。

その場合は、家庭裁判所で「相続財産管理人」の選任を申し立て、第三者による処分を進めることが可能です。
相続放棄したのに支払い命令?誤認のリスクに要注意
まれに、税務署や市区町村が相続放棄を知らないまま請求書を送るケースもあります。こうした場合は、放棄の証明書類を添えて異議申し立てを行うことで、誤請求を取り下げてもらえることがあります。
対応時には以下の書類が有効です。
-
相続放棄申述受理証明書(家庭裁判所発行)
-
被相続人の戸籍謄本(除籍)
-
不動産の登記事項証明書(名義確認用)
共有持分の「処理」を放置しないことが最重要
相続放棄に限らず、共有不動産に関する権利関係は放置すればするほど問題が深刻化していきます。
-
管理者不在の物件が空き家認定され、行政指導・解体命令のリスク
-
他の相続人との対立が長期化し、法的トラブルに発展
-
固定資産税や損害賠償請求の当事者になる可能性
「放棄したはずだから自分には関係ない」と思い込むのは危険です。放棄後も名義や登記、共有者との関係を含めてチェックしておく必要があります。
誰に相談すればいい?信頼できる専門家を選ぶポイント
共有持分や相続登記に関しては、司法書士・不動産会社・弁護士など、ケースに応じた専門家への相談が効果的です。
スクロールできます →
| 専門家の種類 | 得意なサポート範囲 |
|---|---|
| 司法書士 | 相続放棄手続き、登記変更、法的書類作成 |
| 不動産会社(共有物専門) | 持分買取、残りの名義人との調整、査定 |
| 弁護士 | 相続トラブルの調停、訴訟対応、管理責任の整理 |
最初に誰に相談すべきか迷ったら、**「共有持分に対応している専門不動産会社」**への問い合わせがおすすめです。登記と売却の橋渡しを含めた提案が期待できます。
相続放棄をしたからといって、自動的にすべての責任から解放されるとは限りません。とくに不動産の共有持分が登記上に残っていると、税金や管理責任のトラブルが発生する可能性があります。放棄後は登記確認や名義の整理を行い、必要に応じて司法書士や専門業者に相談することが、安心かつ正しい対応への第一歩です。



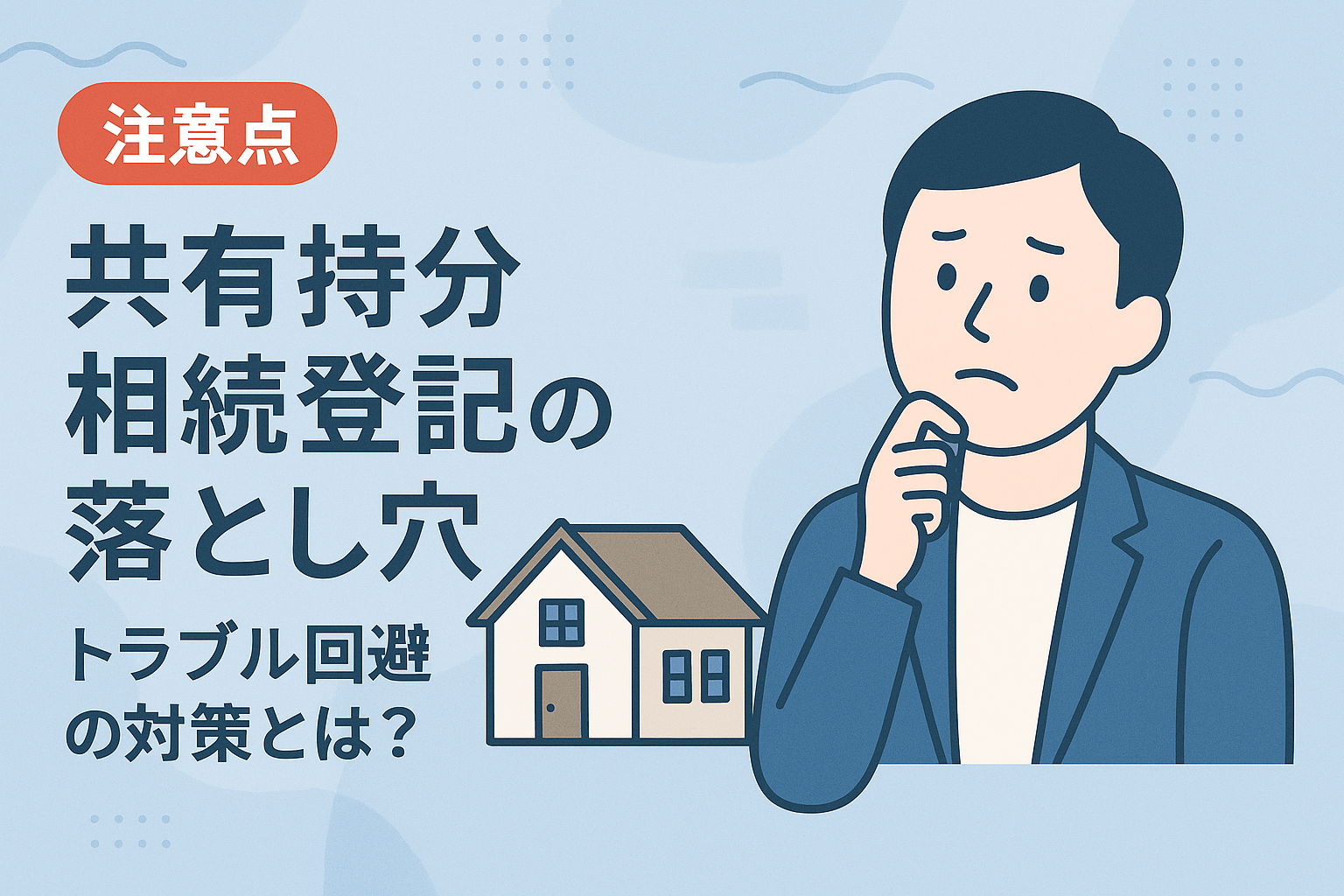


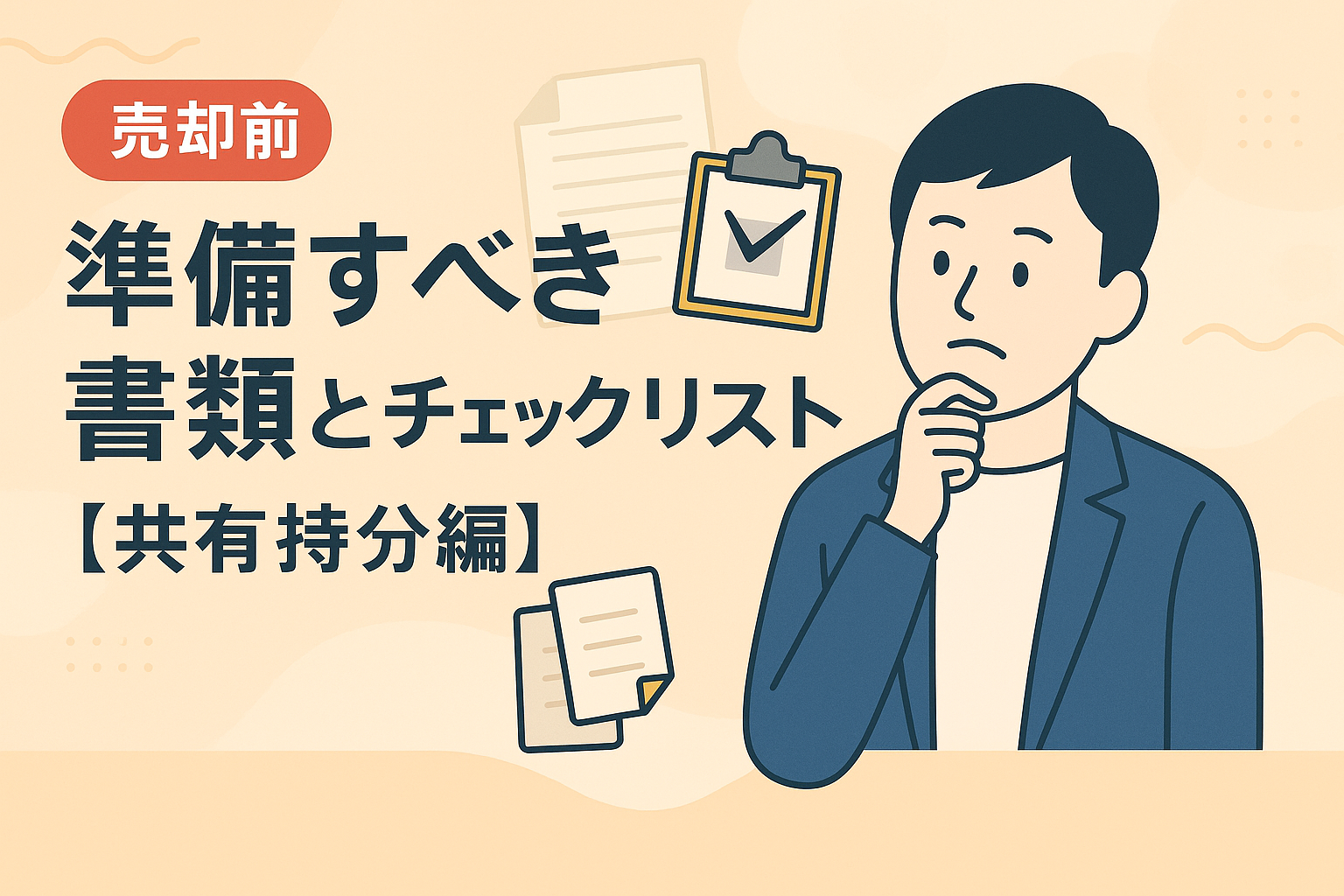



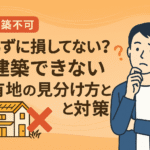
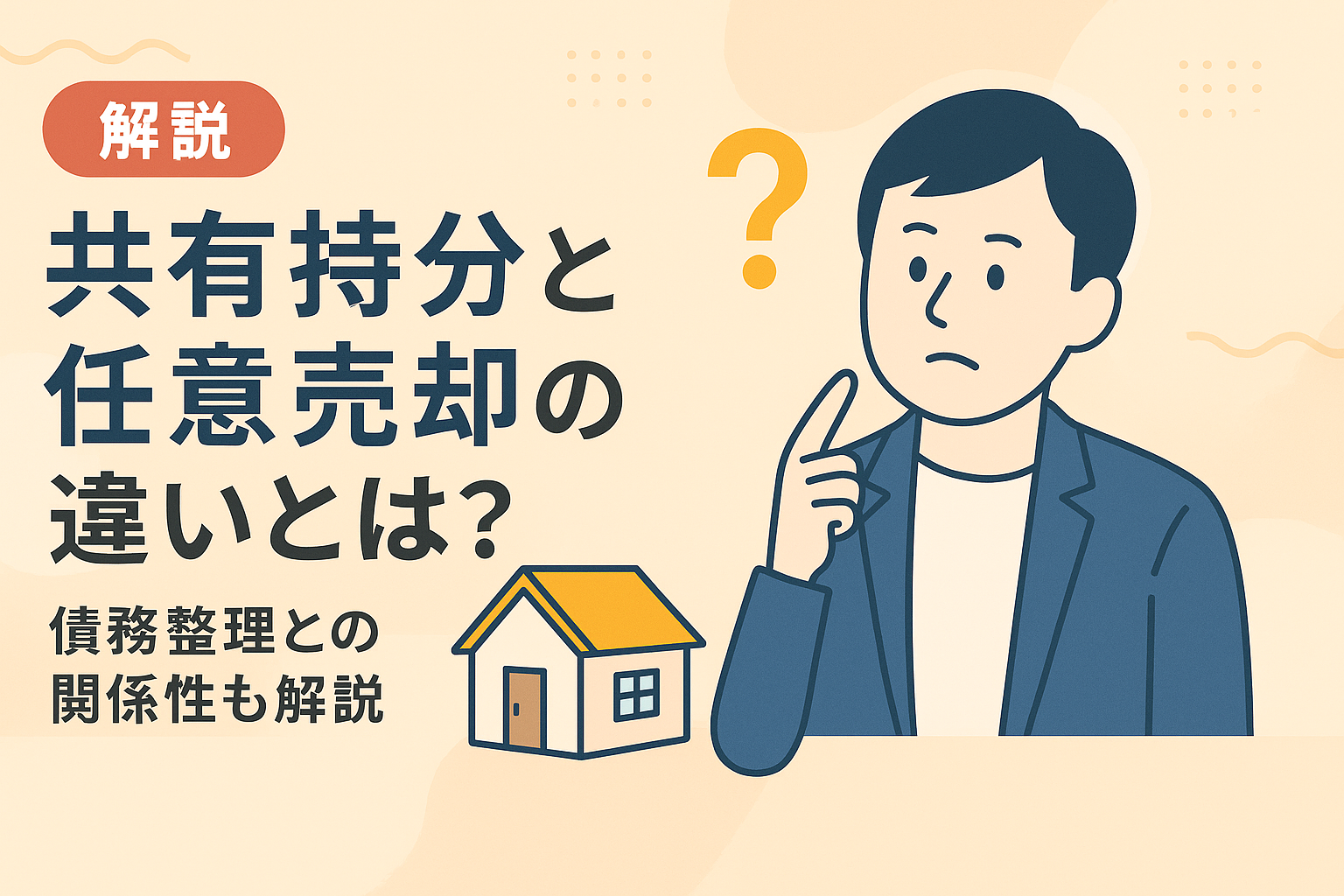




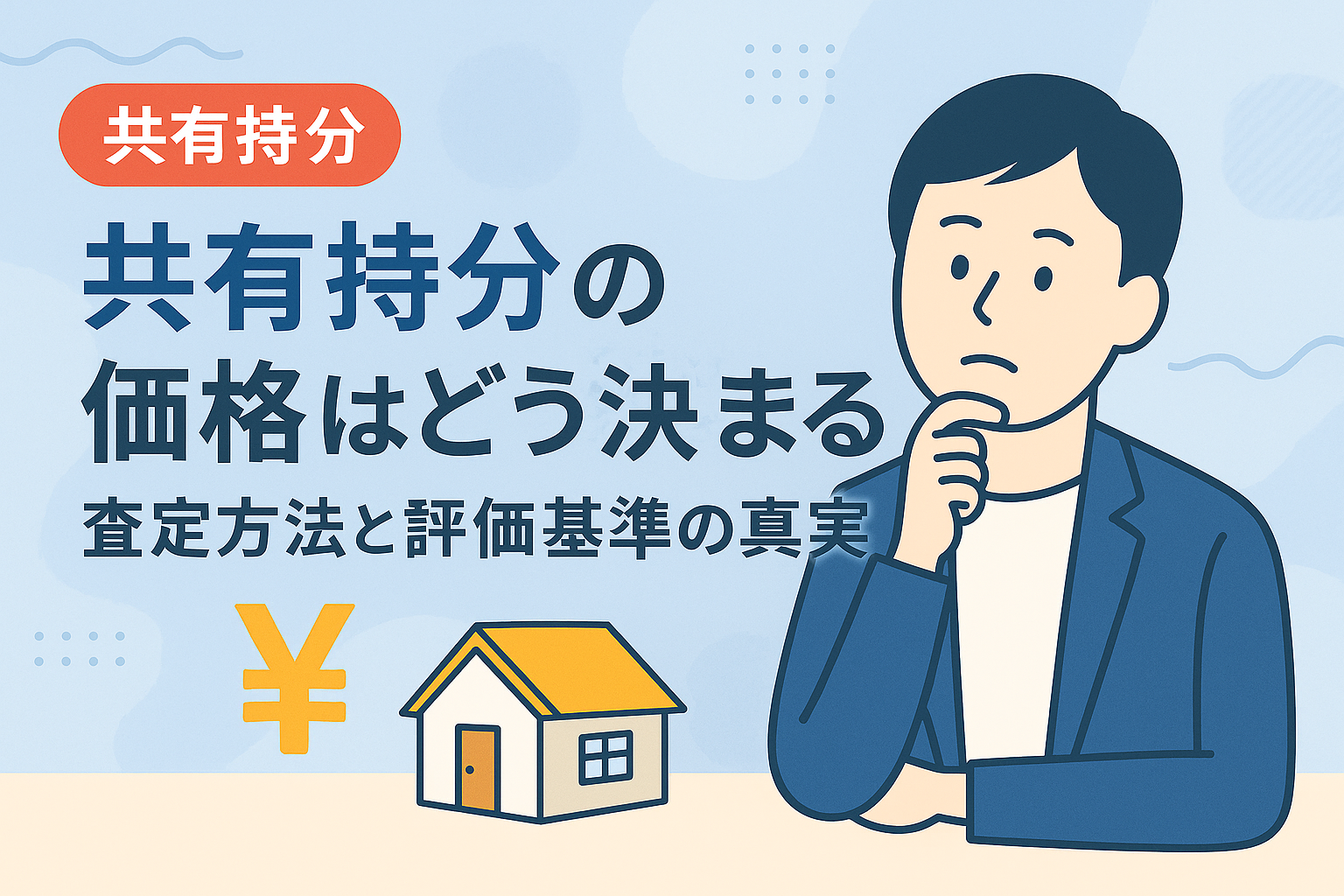






相続放棄したのに、なぜか私に税金の請求が届いていて困っています…。