税金はどうなる?共有持分売却で発生する税金とその対策
共有持分を売却すると税金がかかる?
不動産を売却する際、たとえ「一部分だけの共有持分」であっても、税金の発生を避けることはできません。
「相続で取得したから大丈夫」「持ち分だけだから課税対象外」といった誤解が多いですが、税法上は単独所有とほぼ同等に扱われるのが実情です。
まず最初に理解すべきなのは、売却益が出たかどうかで課税の有無が判断される点です。
では、どのようなケースで課税され、どのような対策を取るべきなのでしょうか。
売却により発生する代表的な税金とは?
共有持分の売却で発生する税金は主に次の3種類です。
-
譲渡所得税(所得税+住民税)
-
印紙税
-
登録免許税(名義変更時)
このうち最も負担が大きくなりやすいのが譲渡所得税です。
これは、不動産を売って得られた利益(譲渡所得)に対して課税されるもので、所得の区分によって税率も変動します。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は次のような計算式で求められます:
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
この譲渡所得が発生した場合、所有期間に応じて以下のような税率が適用されます。
スクロールできます →
| 所有期間 | 税率(所得税+住民税) |
|---|---|
| 5年以下の短期譲渡 | 約39%(所得税30%+住民税9%) |
| 5年超の長期譲渡 | 約20%(所得税15%+住民税5%) |
たとえば、相続などで取得してすぐに売却すると、短期譲渡となって税率が約2倍になることもあります。
特例が使える場合もある
譲渡所得税には以下のような特例制度があります。
-
3,000万円特別控除(居住用)
-
相続財産の取得費加算の特例
-
買換え特例(一定の要件下)
ただし、共有持分の売却では全ての特例が適用できるわけではありません。
たとえば、3,000万円控除は「売主が実際に居住していたこと」が条件となるため、持分のみの相続者などは対象外となるケースが多いです。

はい、たとえ持分だけでも「譲渡」にあたる場合は課税対象になります。取得時の費用や期間によって税額が大きく変わりますよ。
登録免許税・印紙税にも注意
売却に伴う名義変更では登録免許税が発生しますが、こちらは買主側が負担するのが通例です。
また、売買契約書を作成する場合には印紙税も必要で、金額に応じて数千〜数万円かかるケースもあります。
これらの税金は一見小さいようで、積み重ねると意外に負担になるため、あらかじめ確認しておくことが重要です。
とくに譲渡所得の算定に必要な「取得費」が不明な場合、税額が増えるリスクがあるため注意しましょう。
税金を抑えるために知っておきたい3つの対策
共有持分の売却によって税金が発生するのは避けられませんが、適切な対策を取ることで負担を最小限に抑えることは可能です。特に次の3つのポイントを押さえることで、節税効果が期待できます。
1. 「取得費」を正確に把握する
税額を計算する際、最も重要な要素のひとつが「取得費」です。これは過去の購入時の価格や相続評価額などをもとに計算されますが、証明書類がない場合は「概算取得費(売却額の5%)」で計算され、結果的に課税額が大きくなってしまうことがあります。
領収書や契約書、登記簿などを整理し、正確な取得費を把握することが節税の第一歩です。
2. 「譲渡費用」も忘れずに計上する
不動産の売却にかかった費用(仲介手数料・測量費・広告費など)は「譲渡費用」として譲渡所得から差し引くことができます。
これを見落とすと、本来より高い所得として扱われ、不要な税金を支払う可能性があるため注意が必要です。
3. 特例や控除制度の確認
先述の通り、共有持分であっても特定の条件を満たすことで控除や軽減措置が受けられる場合があります。
たとえば:
-
相続財産の取得費加算:相続開始日から3年以内の売却なら、相続時に支払った相続税額を取得費に加算可能。
-
居住用財産の特別控除:共有者のうち誰かが居住していた場合、持分に応じて特別控除の一部を適用できる場合も。

共有持分の売却って税金が複雑そうですが、何か有利になる制度はありますか?

相続から3年以内であれば「取得費加算の特例」が使える場合がありますし、仲介手数料などを経費に入れるのも忘れずに。節税には「書類の準備」が非常に重要です。
注意点①:税務署への申告は必要?
譲渡所得が発生しなかった場合(赤字や控除対象など)でも、確定申告を行うことが推奨されます。
理由は以下の通りです:
-
将来の税務調査リスクを回避できる
-
損失の繰越控除などの制度を活用できる
-
税金の過払いを防ぐことができる
とくに「相続や共有名義が絡む取引」は税務署からの注目度も高くなるため、念のため申告を行っておくほうが安全です。
注意点②:共有者間での「税金負担」に差が出る
持分を持つ人それぞれが異なる税率や控除対象であることも多く、「同じ売却でも納税額が人によって違う」ということは珍しくありません。
そのため、売却前には全共有者が自分の税務状況を確認し、必要に応じて税理士など専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。
共有持分の売却には、譲渡所得税・印紙税・登録免許税といった税金が発生しますが、取得費や譲渡費用を正確に計算し、特例を活用することで負担を減らすことが可能です。税額は売却時の状況や共有者の条件によって大きく異なるため、正しい知識と専門家のサポートが成功のカギとなります。


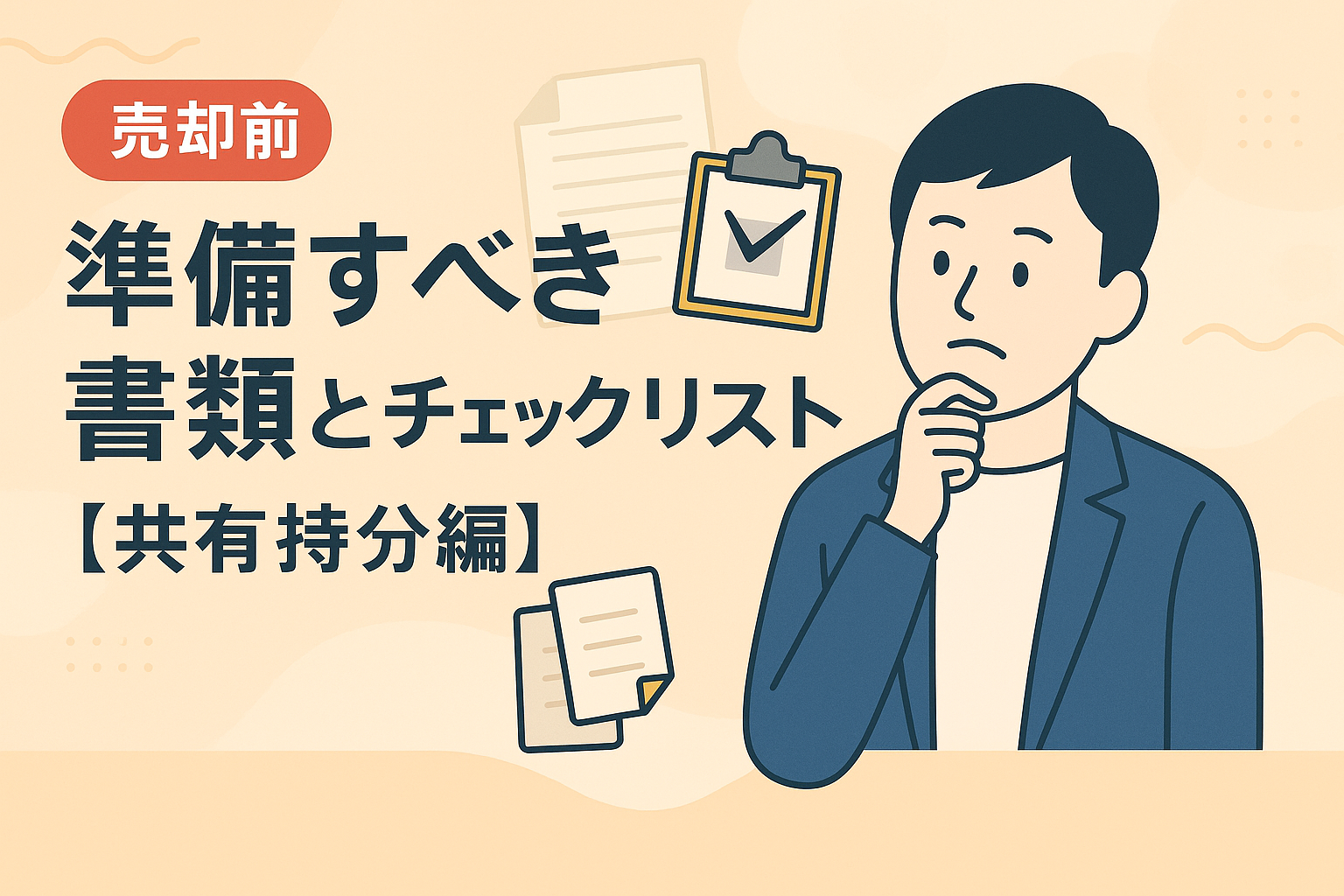

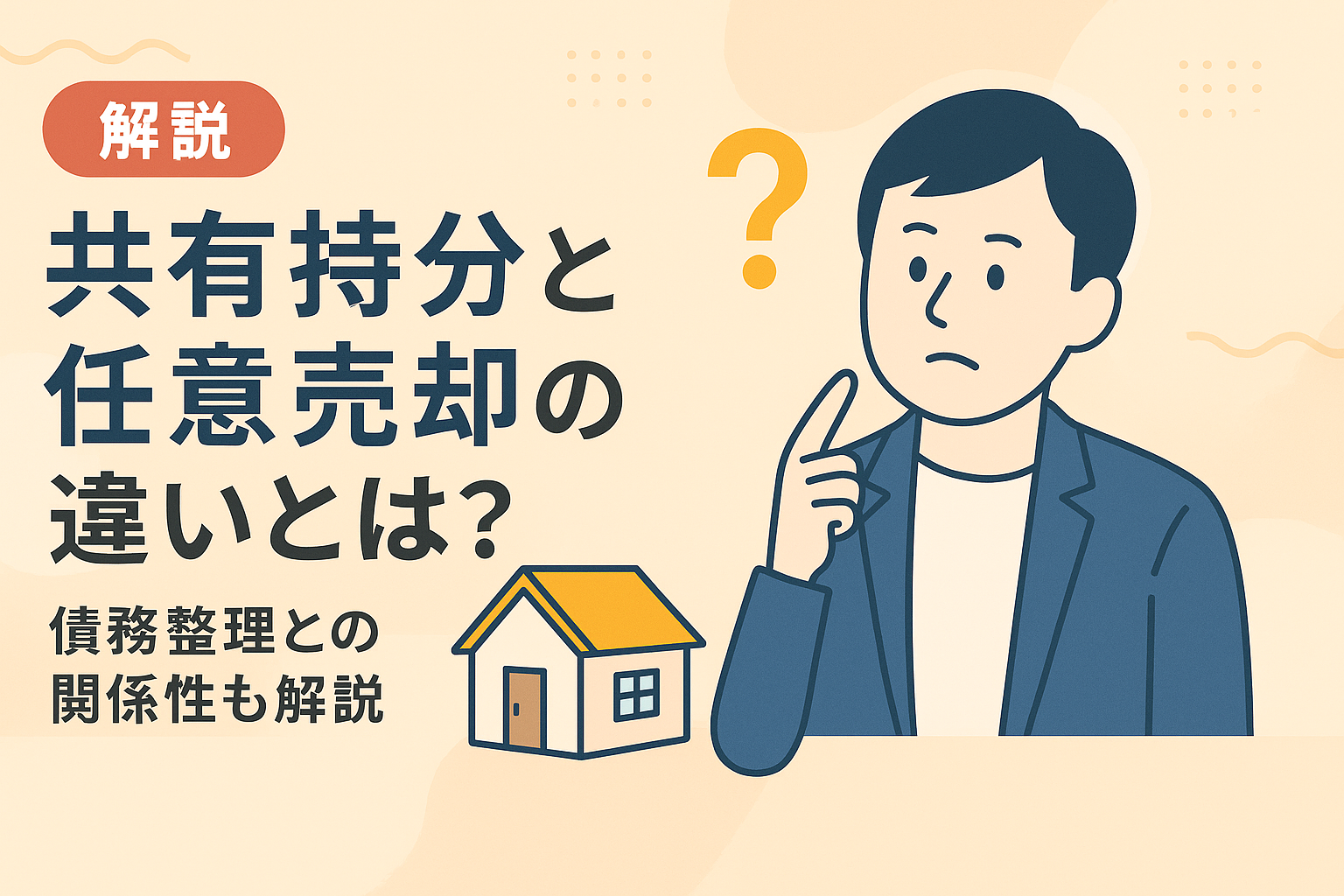


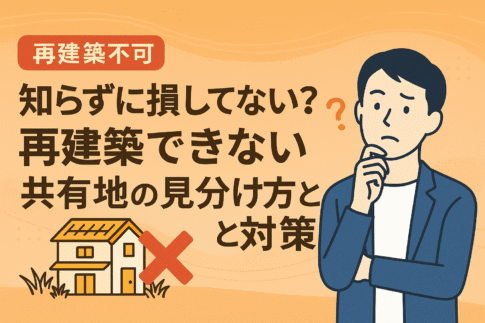



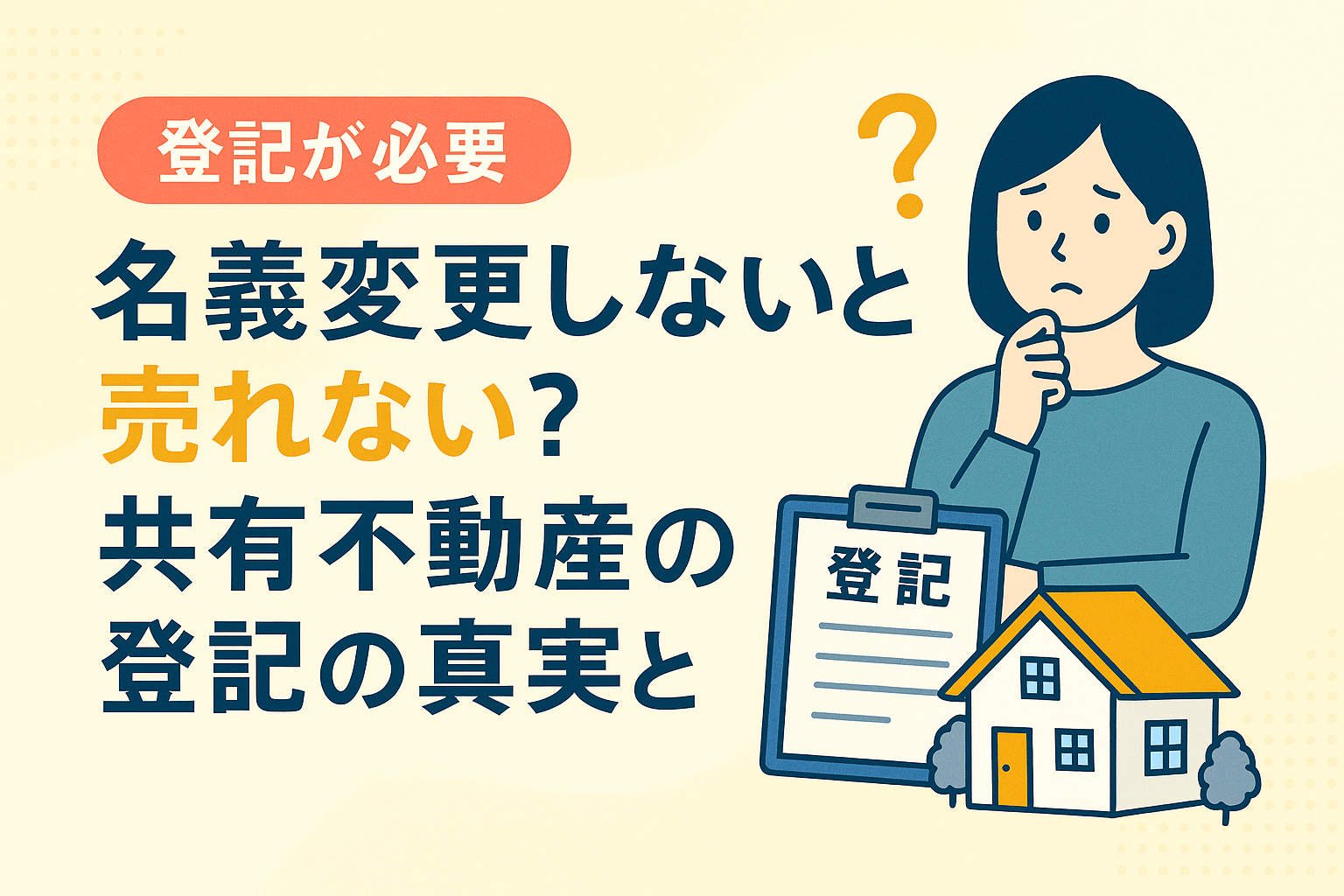







兄弟で共有していた不動産の一部を売ったんですが、税金ってやっぱりかかりますか?