遺産分割協議と共有持分の関係とは?失敗しない対策を解説
遺産分割協議とは何か?
遺産分割協議とは、被相続人が亡くなった後、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合って決める手続きです。相続財産が現金や預金のみであれば分割しやすいですが、不動産が含まれる場合、共有持分として相続されるケースが多くなります。
相続人が複数いる場合、1つの不動産を共有名義で相続することは一般的です。しかし、共有状態が続くとトラブルの火種になることも少なくありません。
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
なぜ共有持分になるのか?
不動産を法定相続分で分割する場合、現物分割が難しいため、共有持分という形式が取られます。たとえば父親の自宅を、母と子2人で相続する場合、以下のような比率になることが多いです。
| 相続人 | 法定相続分 | 共有持分の例 |
|---|---|---|
| 母 | 1/2 | 2分の1 |
| 長男 | 1/4 | 4分の1 |
| 長女 | 1/4 | 4分の1 |
このように、不動産の権利が複数人に分かれることで、自由に売却や活用ができなくなるリスクが発生します。
共有持分のまま放置するリスク
共有持分のまま不動産を放置することには重大なリスクがあります。
-
一人でも反対すると売却や賃貸ができない
-
固定資産税などの負担が平等でない
-
将来的に相続人が増えて分割がさらに複雑化
このような問題が複雑に絡むことで、不動産の活用価値が著しく低下することもあります。

それは「共有持分」で相続されたことが原因かもしれません。遺産分割協議の段階で適切に対応していれば、回避できるケースも多いんですよ。
遺産分割協議の不成立と家庭裁判所の関与
相続人同士で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所による調停や審判に発展することがあります。
-
調停:家庭裁判所で話し合いの場を設けて合意を目指す
-
審判:合意できない場合に、裁判所が一方的に分割方法を決定
どちらも時間と労力、そして費用がかかるため、できる限り遺産分割協議の段階で合意形成することが重要です。
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
遺産分割協議で失敗しないために
失敗しないためには、以下のような対策が有効です。
専門家を交える
相続に強い司法書士や弁護士に早期相談することで、公平かつ法的に正しい協議が可能になります。
代償分割や換価分割を活用する
現物をそのまま分けるのではなく、一部を売却して現金で分割する方法も検討しましょう。
将来的なトラブルを見越す
「将来誰が住むのか」「売却はいつ・誰が主導するのか」といった中長期的視点での取り決めも重要です。
遺産分割協議がまとまらなかった場合の対処法
もし遺産分割協議がうまくいかず、相続人間で合意できない場合は、家庭裁判所での調停や審判に進む必要があります。
家庭裁判所での調停・審判
-
調停は、家庭裁判所の調停委員が間に入り、相続人同士の合意形成をサポートする場です。
-
審判は、調停でも合意できなかった場合に、裁判官が最終的な分割方法を決定します。
このような手続きになると、半年〜1年以上の時間と弁護士費用などのコストがかかるため、できる限り協議段階で解決するのが理想です。
不動産の共有持分を解消する方法
遺産分割後に共有状態が続いてしまった場合も、次のような方法で解消を図ることが可能です。
方法1:共有者間での持分売買
相続人同士で話し合い、誰かが他の持分を買い取ることで単独名義にする方法です。親族間売買のため市場価格より柔軟に調整できる場合もあります。
方法2:共有者以外へ売却(持分売却)
共有者間の合意が難しい場合は、自分の持分だけを第三者へ売却することも可能です。JTRUSTのような専門業者を利用することで、スムーズに現金化できます。

共有者が全然話し合いに応じてくれなくて、どうにもできない状況です…

<br /> そのような場合でも、持分売却や調停などの選択肢があります。一人で悩まず、専門家にご相談ください。
方法3:不動産の分筆(物理的分割)
土地の場合は、境界を明確に区切って持分を物理的に分ける「分筆登記」という方法もあります。ただし、建物では現実的に困難なケースが多く、主に土地に限られる方法です。
よくあるトラブルと事前にできる防止策
共有持分の相続では、次のようなトラブルが頻出します。
ケース1:使わない不動産の維持費負担
遠方にある実家を誰も住まずに放置し、固定資産税や草刈り代だけが発生。費用負担が偏ることに不満が生まれ、相続人同士の関係が悪化。
ケース2:売却の意思が一致せず放置
売りたい人・住みたい人・保有していたい人など、意思がバラバラで、何も決まらず10年以上放置される例も。
防止策
-
協議段階で「将来の活用・売却方針」まで決める
-
代表者を決めて管理責任を明確にする
-
売却できる権利を事前に公正証書で定めておく
共有不動産の相談先はどこが最適?
複雑な共有状態の不動産は、一般の不動産会社では対応できないことが多いため、以下のような専門機関の利用が重要です。
| 相談先 | 特徴 |
|---|---|
| 司法書士 | 相続登記や名義変更、協議書作成の専門家 |
| 弁護士 | 調停・審判や持分売却時の法的交渉に強い |
| JTRUSTなどの専門業者 | 持分売却の実務経験が豊富、即時現金化が可能 |
共有持分を活かす・手放す判断ポイント
最終的には、以下の観点から**「持ち続けるか、手放すか」**を見極める必要があります。
-
維持管理の手間や費用に対してリターンが見合っているか
-
将来的な賃貸・売却が現実的か
-
他の相続人との関係性や協議の見通し
活用見込みがない場合、早期に売却を検討する方がコストも低く、トラブルも最小限で済みます。
遺産分割協議では、特に不動産の共有持分が絡むと将来的なトラブルを招くリスクが高まります。
相続時点で協議が成立しなければ家庭裁判所での調停や審判も避けられません。
共有状態が続いてしまった場合も、持分売却や分筆などの方法で解決策はあります。
放置せず、専門家に早めに相談することが、安心につながる第一歩です。



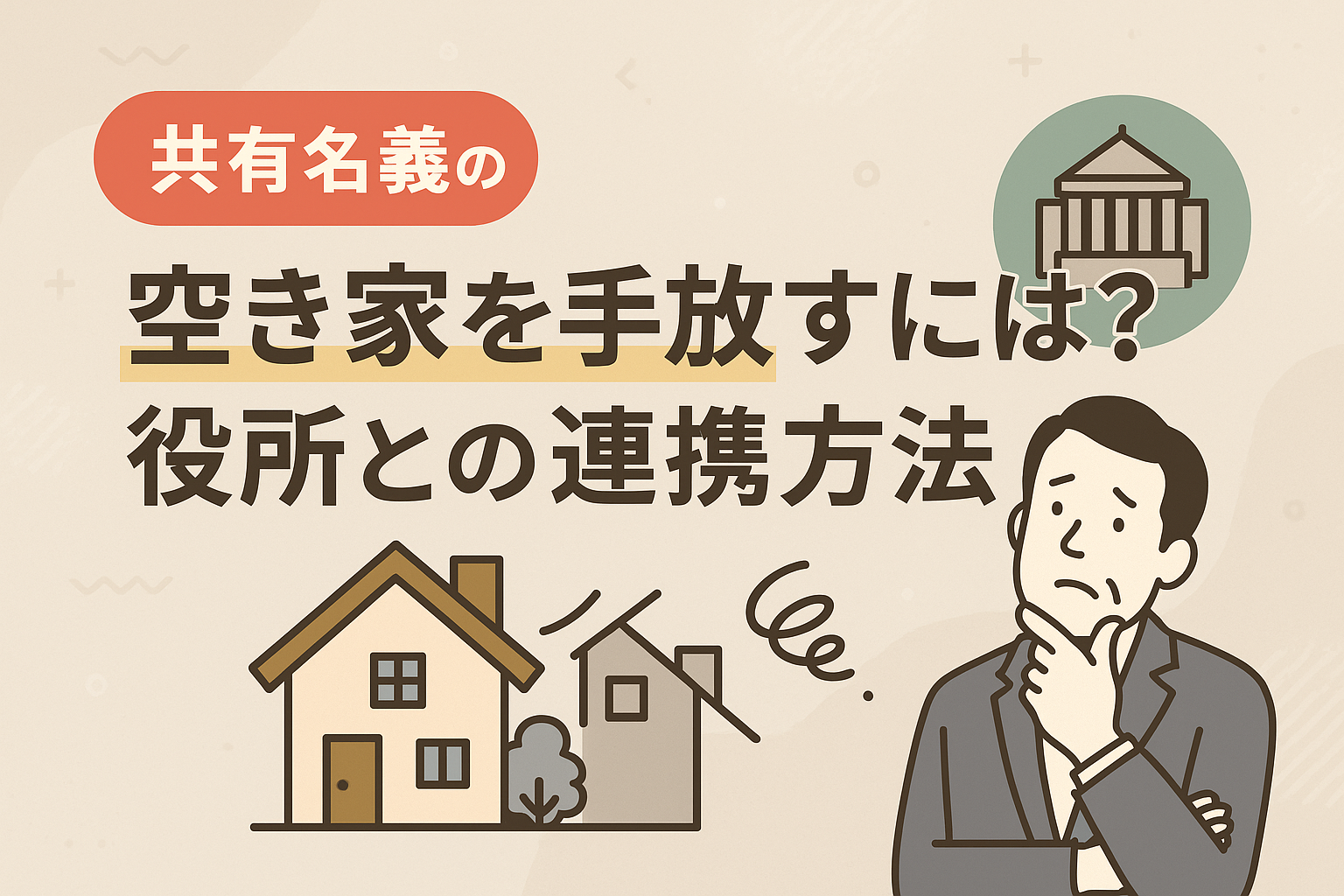


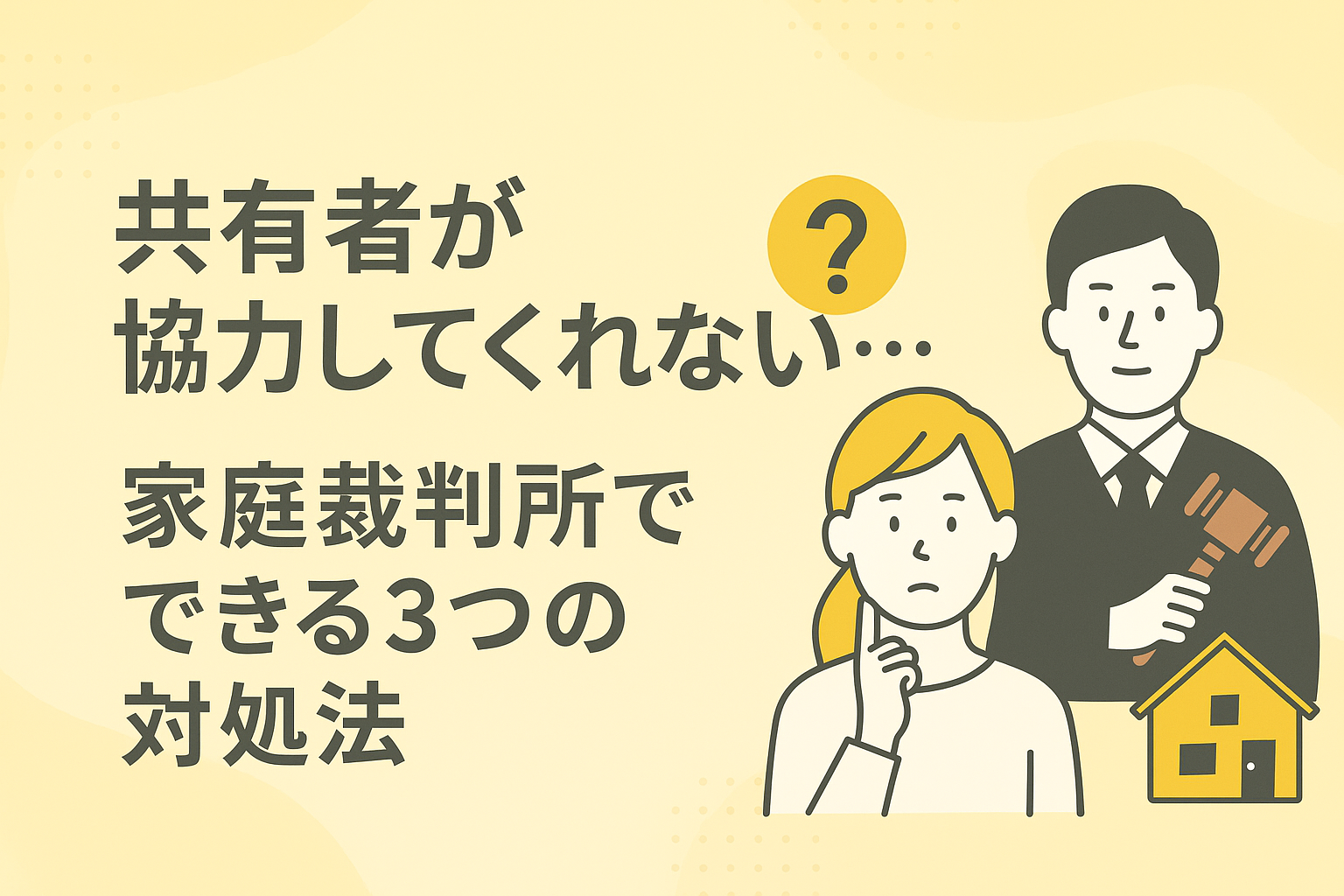





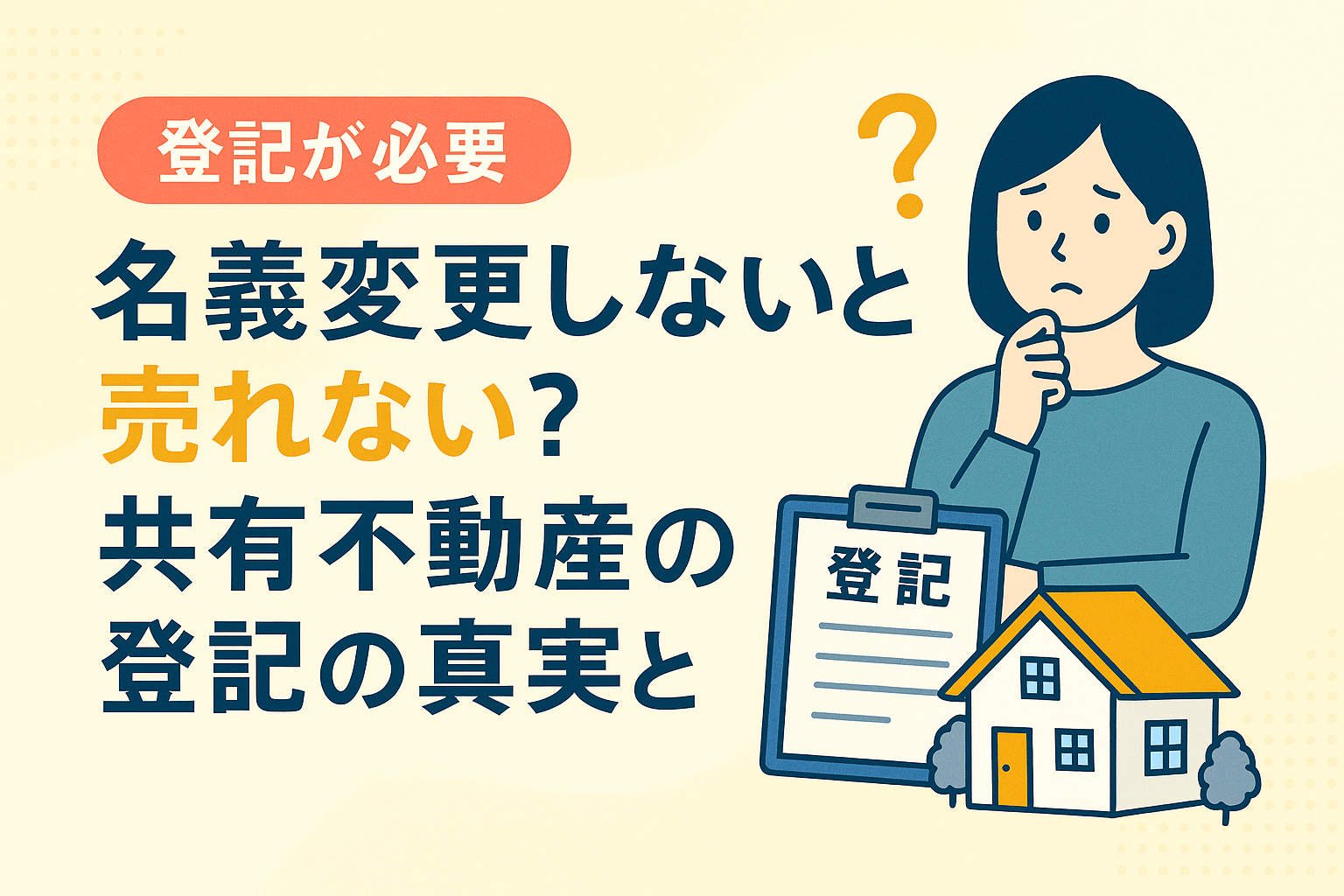


相続で不動産をもらったのに、自由に使えなくて困っています…