共有持分トラブル事例集【よくある揉めごとを防ぐ方法】
共有持分を相続・取得したあと、「思わぬトラブル」に巻き込まれるケースは少なくありません。ここでは実際にあった共有持分のトラブル事例をもとに、事前に取れる対策や防止策を紹介します。
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
よくあるトラブル事例と背景
ケース1:相手が音信不通で売却が進まない
→ 事前対策:相続後すぐに持分整理や登記を行い、所在を確認する体制を整える。
ケース2:感情的な対立から手続きが進まない

過去の相続や遺産分割の経緯に不満を持つ共有者が、売却や相談に非協力的になることもあります。
→ 事前対策:第三者である専門家(司法書士・不動産会社)を介入させることで冷静な交渉が可能になります。
トラブル発生前にしておくべき対策
事前の備えがあるかどうかで、共有持分トラブルの発生確率は大きく変わります。以下のような準備が効果的です。
法的対応を視野に入れるべきケース
長期間放置された共有持分
共有不動産が10年以上放置されている場合、固定資産税や維持管理費が一部共有者に偏っているなどの問題が発生します。
→ 家裁での持分分割調停や、不在者財産管理人の選任を検討する必要があります。
悪意ある第三者による持分取得
共有者の一人が外部の第三者に持分を売却し、その第三者が嫌がらせや立ち退き要求をするケースもあります。
→ 専門業者を介して早期の全体売却を進めることが防止策になります。
共有持分トラブル事例集【よくある揉めごとを防ぐ方法】
共有持分を相続・取得したあと、「思わぬトラブル」に巻き込まれるケースは少なくありません。ここでは実際にあった共有持分のトラブル事例をもとに、事前に取れる対策や防止策を紹介します。
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
よくあるトラブル事例と背景
ケース1:相手が音信不通で売却が進まない

共有者の一人が行方不明で連絡が取れず、売却に必要な同意が得られない……
→ 事前対策:相続後すぐに持分整理や登記を行い、所在を確認する体制を整える。
ケース2:感情的な対立から手続きが進まない

過去の相続や遺産分割の経緯に不満を持つ共有者が、売却や相談に非協力的になることもあります。
→ 事前対策:第三者である専門家(司法書士・不動産会社)を介入させることで冷静な交渉が可能になります。
トラブル発生前にしておくべき対策
事前の備えがあるかどうかで、共有持分トラブルの発生確率は大きく変わります。以下のような準備が効果的です。
法的対応を視野に入れるべきケース
長期間放置された共有持分
共有不動産が10年以上放置されている場合、固定資産税や維持管理費が一部共有者に偏っているなどの問題が発生します。
→ 家裁での持分分割調停や、不在者財産管理人の選任を検討する必要があります。
悪意ある第三者による持分取得
共有者の一人が外部の第三者に持分を売却し、その第三者が嫌がらせや立ち退き要求をするケースもあります。
→ 専門業者を介して早期の全体売却を進めることが防止策になります。
まとめと防止のポイント
共有持分トラブルは”起きてから”では遅いケースが多く、あらかじめリスクの洗い出しと対策が求められます。
防止ポイントの再確認:
- 相続後は速やかに登記と関係整理を行う
- 感情的になりやすい協議は、司法書士・行政書士など専門家に任せる
- 売却を希望する場合は、共有者間での話し合いだけに頼らず、共有持分の買取実績がある不動産業者への相談を検討する
共有持分に関するトラブルは、放置しておくと法的・経済的なリスクに発展することもあります。事前の情報収集と適切な専門家との連携によって、多くのトラブルは防ぐことが可能です。早めに行動し、冷静な対策を講じることが重要です。

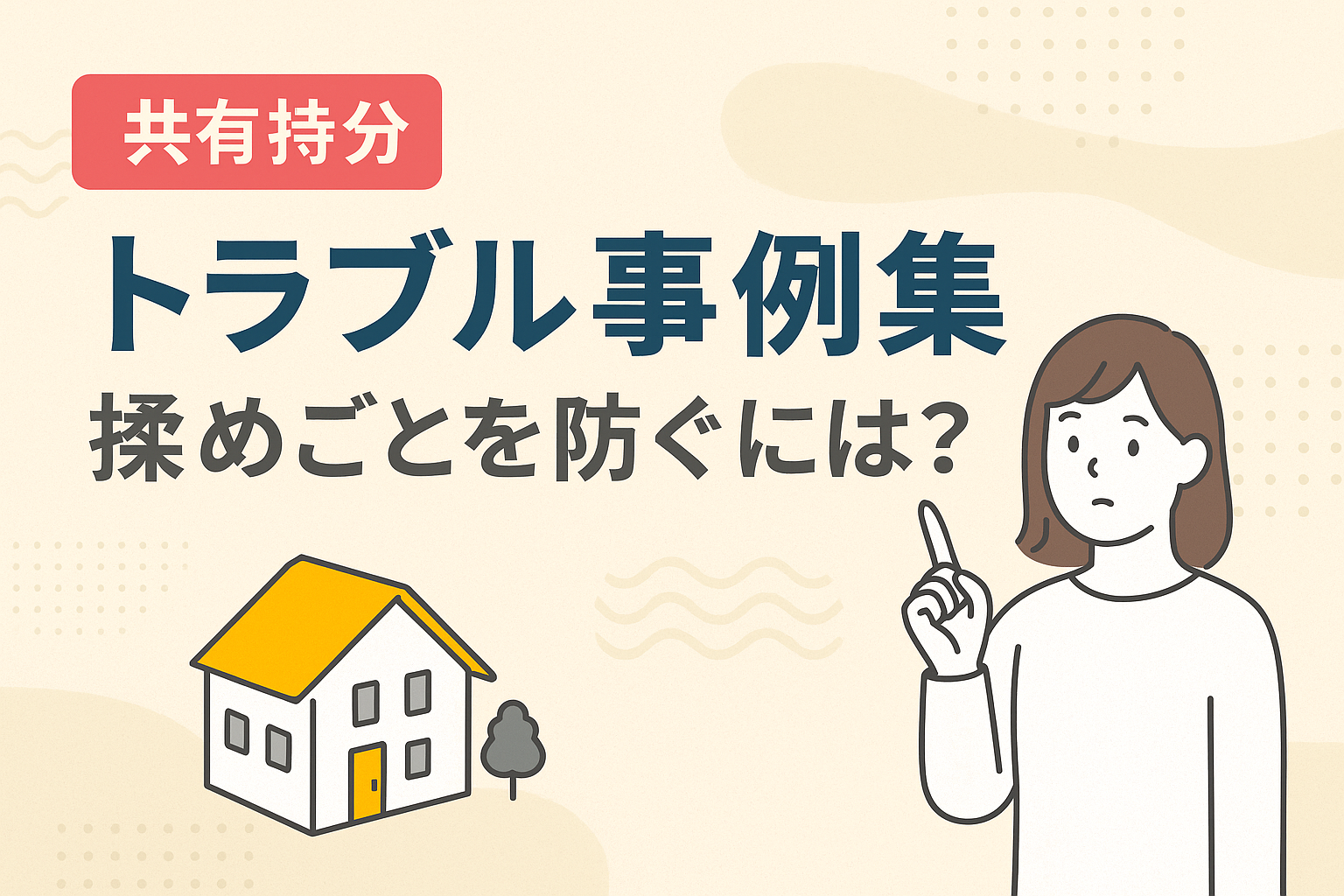
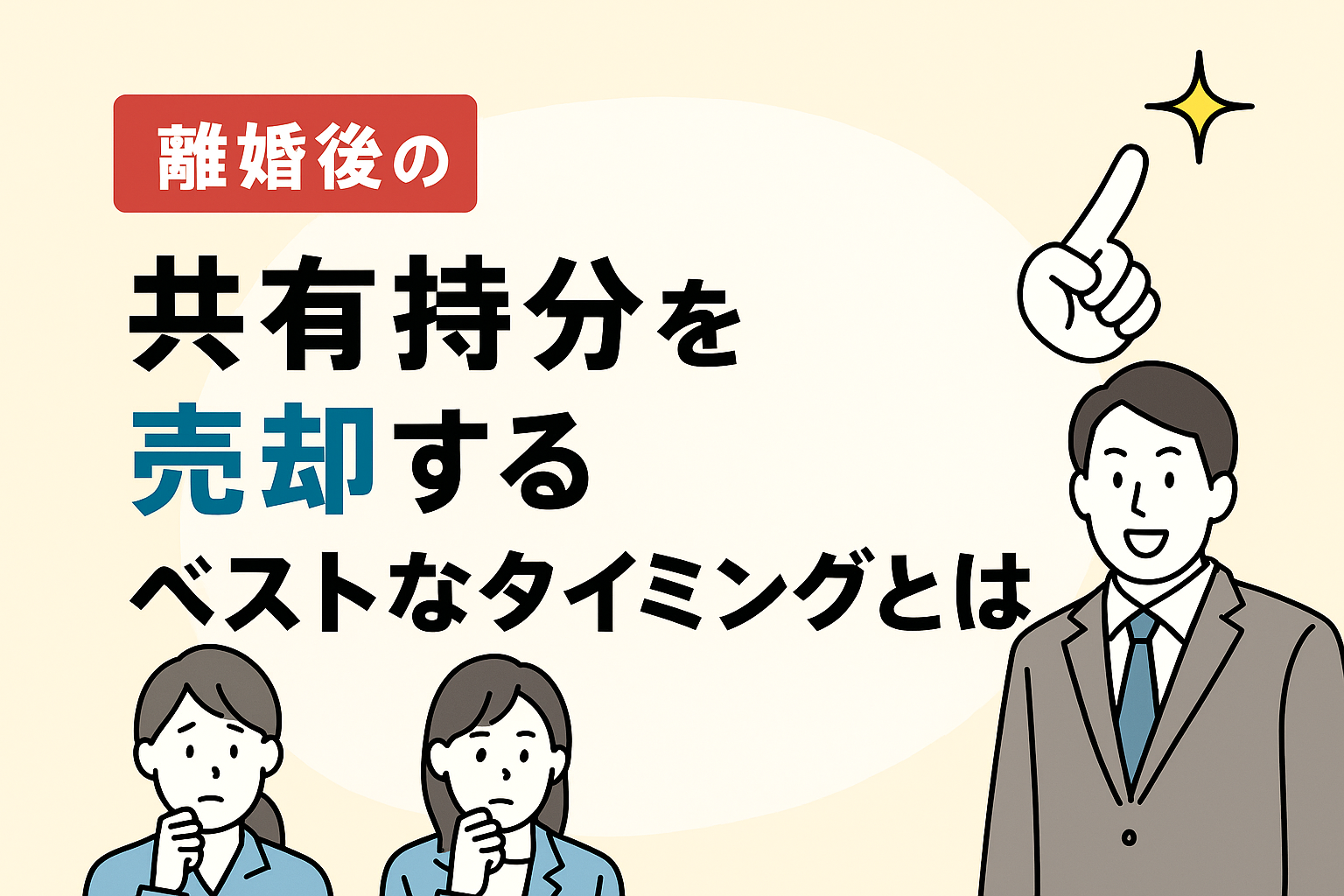
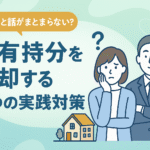
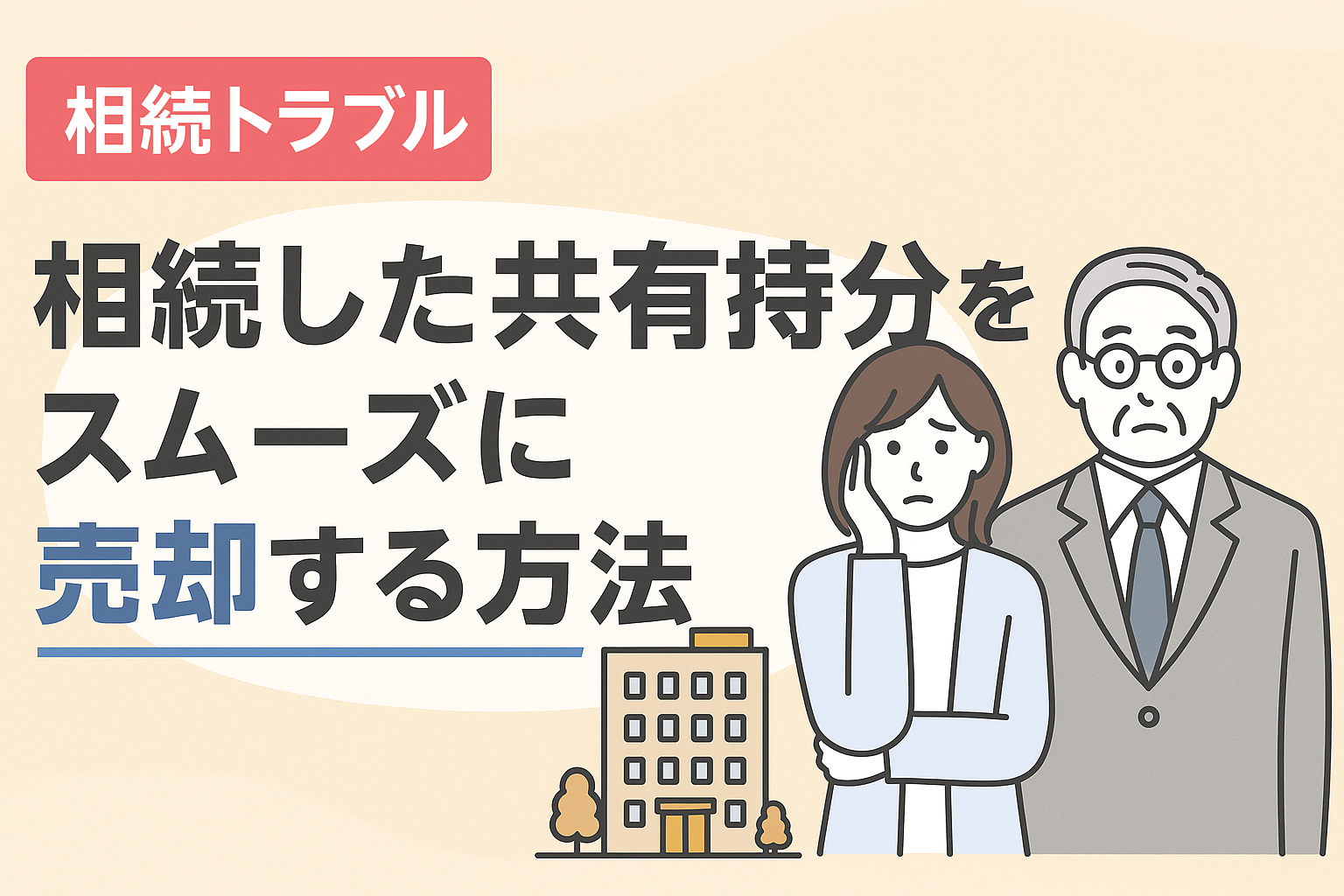




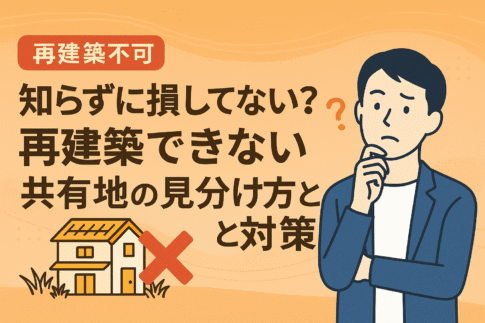
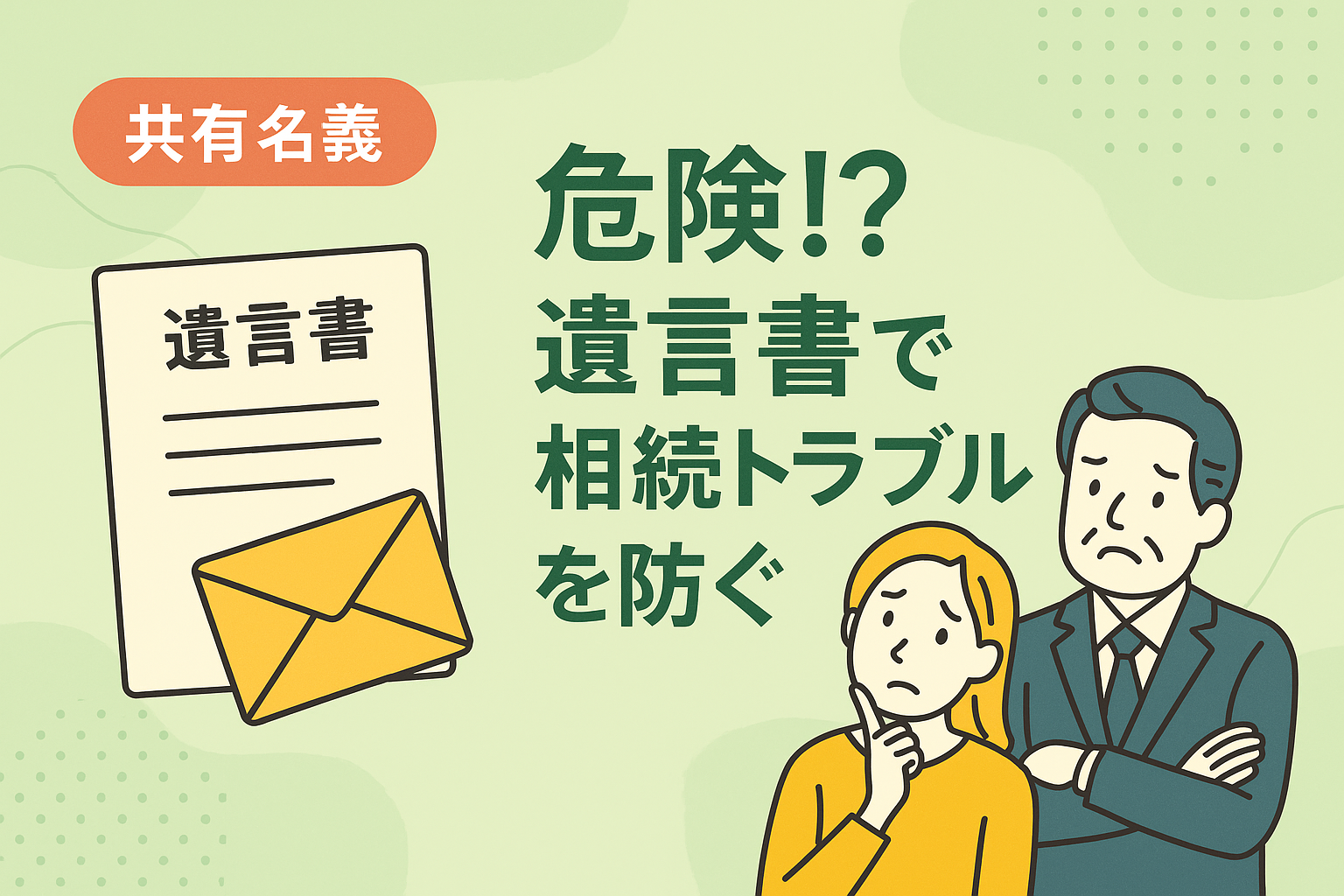
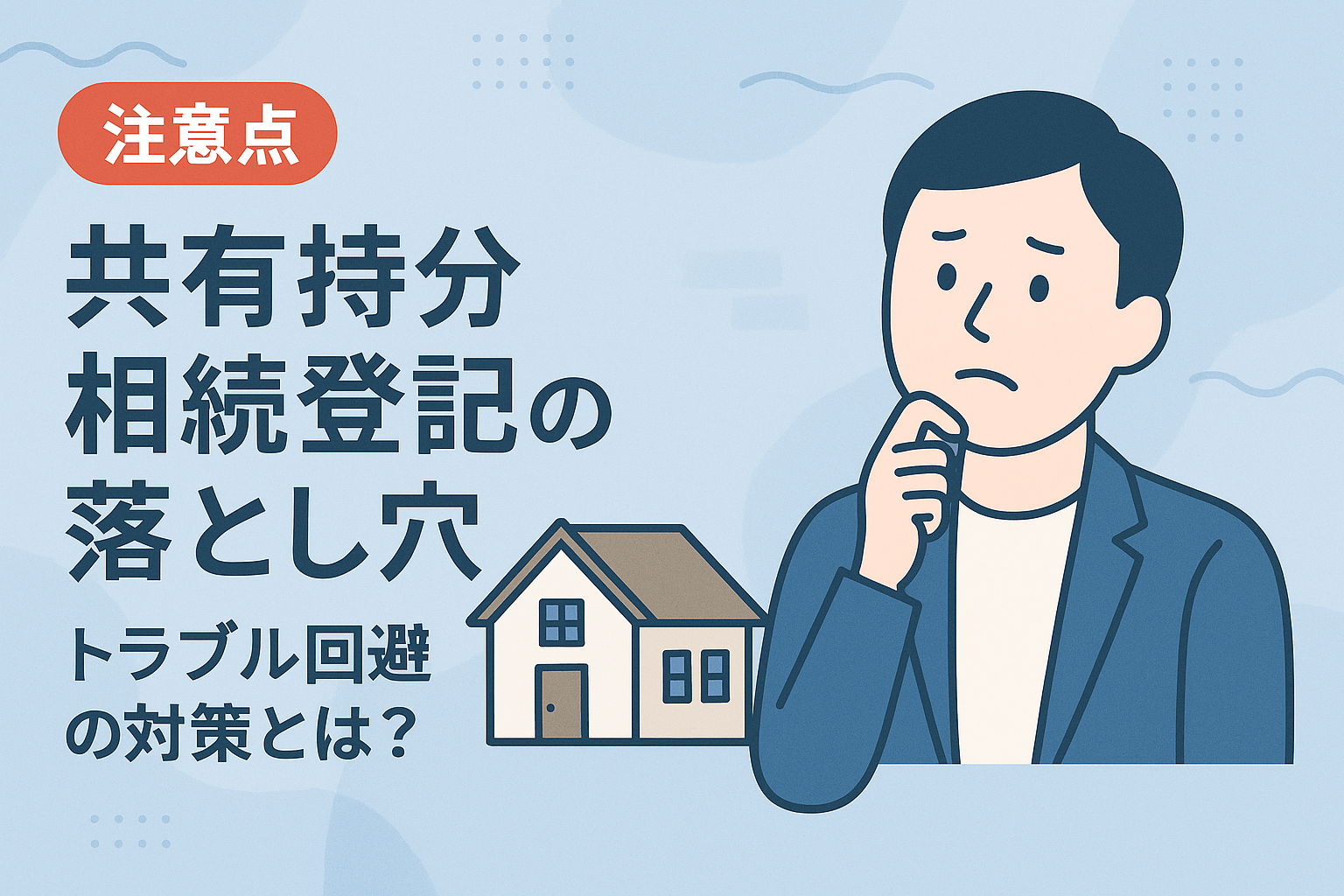





共有者の一人が行方不明で連絡が取れず、売却に必要な同意が得られない……