共有持分と共有名義の違いをわかりやすく解説
「共有持分」と「共有名義」は同じ意味ではない?
不動産に関する相談の中でよくある誤解が、「共有持分」と「共有名義」は同じものだという認識です。
確かに似た概念に見えますが、厳密には異なる意味を持つ用語です。違いを理解しておかないと、後々の売却や相続でトラブルに発展することもあります。
本記事では、共有持分と共有名義の違いを明確にしながら、それぞれの特徴・法律的な意味・実務上の注意点を解説していきます。
「共有名義」とは不動産登記における状態のこと
まず、「共有名義」とは登記簿に複数人の名義(所有者)が記載されている状態を指します。たとえば、夫婦が1つの不動産を共同購入した場合、それぞれの名義が登記に反映されていれば「共有名義」となります。
不動産登記簿の所有者欄に以下のように記載されるのが一般的です。
例:
-
甲:持分2分の1
-
乙:持分2分の1
つまり、登記上で複数人の名前が並んでいれば「共有名義」ですが、そこに記載された割合が「共有持分」です。
「共有持分」とは不動産に対する持ち分割合
一方で「共有持分」とは、不動産の所有権の中で、自分がどの程度の割合を持っているかを示す概念です。
つまり、「共有名義」が状態を示すのに対して、「共有持分」はその中身=権利の量を指します。
スクロールできます →
| 用語 | 意味 | 具体例 |
|---|---|---|
| 共有名義 | 登記簿に複数名が記載されている状態 | 夫婦の名前が両方登記されている |
| 共有持分 | 所有権の割合・権利の内容 | 妻が3分の1、夫が3分の2の持分を持つ |
登記簿に名前がある=所有者、という点は同じですが、持分の割合により行使できる権利に差が出るため、注意が必要です。
なぜ混同されやすいのか?
この2つが混同されがちな理由は、以下のような点にあります。
-
両方とも「複数人で所有している」状態を指している
-
どちらも不動産取引や相続の場面で登場する
-
法的には区別されるが、日常会話では使い分けされていない

共有名義は「名義上の状態」、共有持分は「所有している割合」です。名義に名前があっても、持分割合によって権利行使の範囲は異なります。
このように、登記の状態(名義)と、実際の権利割合(持分)をしっかり分けて理解することが重要です。
共有持分の割合で変わる「できること」「できないこと」
共有不動産は、単独で自由に扱えない点が大きな制約です。
とくに共有持分が少ないと、次のような制限を受けることがあります。
-
建物の売却や賃貸には、他の共有者の同意が必要
-
管理や修繕に関する意見の衝突が起こりやすい
-
大規模な変更や建て替えは全員の同意が必須
スクロールできます →
| 行動内容 | 単独で可能か? | 説明 |
|---|---|---|
| 自分の持分の売却 | ○ | 他の共有者の同意なく可能 |
| 共有物全体の売却 | × | 原則として全員の同意が必要 |
| 賃貸や建て替え | △ | 共有持分の過半数以上の同意が必要(ケースにより異なる) |
「共有名義だから自分のもの」と思っていても、実際は持分割合によって判断や行動に制限がある点に注意が必要です。
トラブルに発展しやすい代表的なケース
以下は、共有持分と共有名義を混同した結果、実際にトラブルに発展した事例です。
-
名義があるだけで売却できると誤解し、買主との契約が破談
-
相続による共有で親族同士が対立し、物件が「塩漬け」に
-
持分だけを第三者に売却され、知らない人物が権利者に

兄弟と共有名義の実家を持ってるのですが、自分の判断だけで売ることってできるんでしょうか?

ご自身の「持分」を売却することは可能です。ただし不動産全体を売却するには、他の共有者の同意が不可欠です。
売却や相続時は専門家に相談を
不動産の共有名義・共有持分の取り扱いは、法的にも実務的にも複雑な要素が絡みます。
とくに売却や相続が絡む場合には、以下のような相談先を早めに検討することをおすすめします。
-
不動産専門の司法書士
-
共有物の売却に強い不動産業者
-
共有トラブルの解決経験がある弁護士
「共有名義」と「共有持分」は同じではありません。名義上の状態と実際の権利割合には違いがあり、誤解すると売却・賃貸・相続などでトラブルが起きやすくなります。自身の権利を正しく理解し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが、安全かつスムーズな不動産取引につながります。




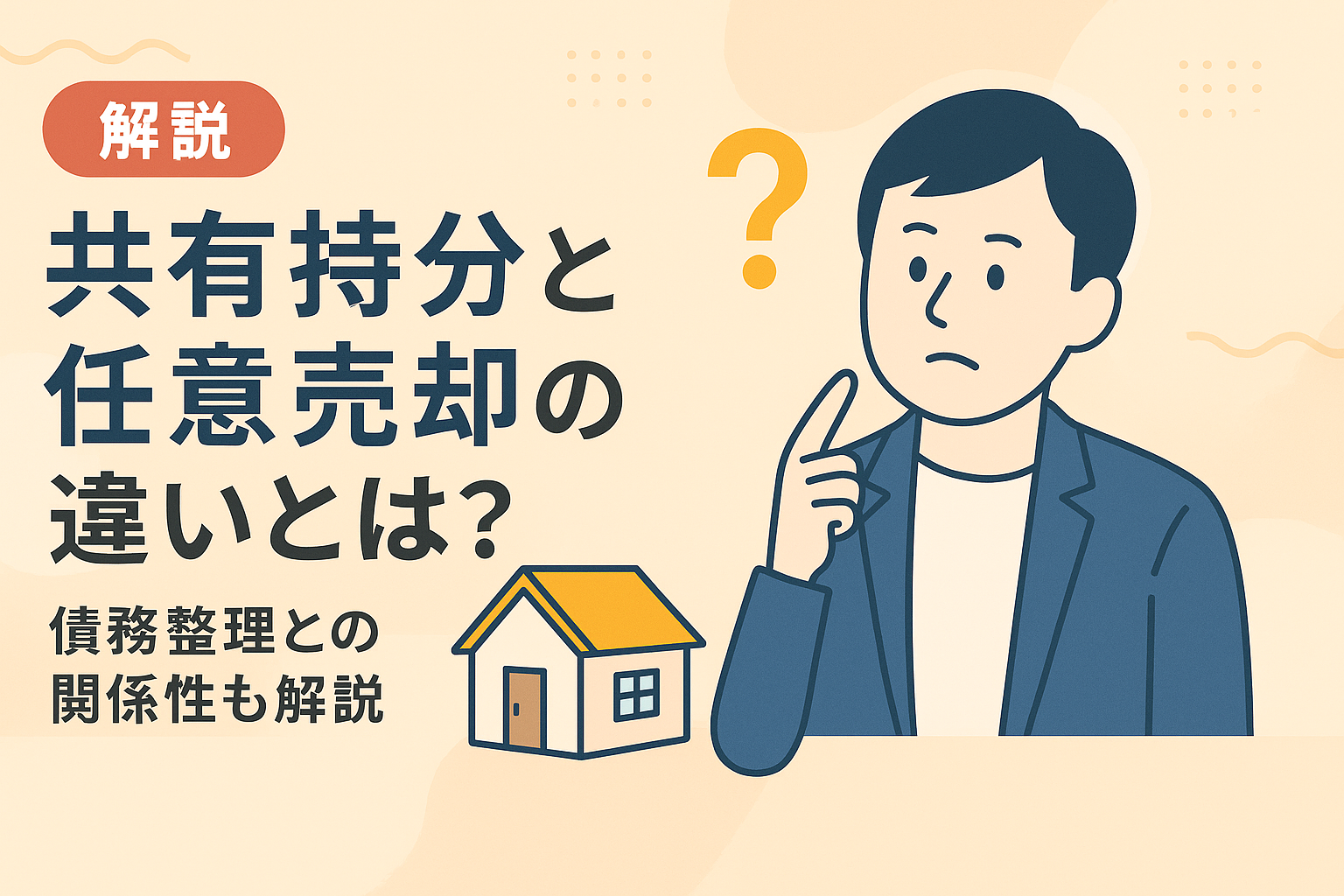


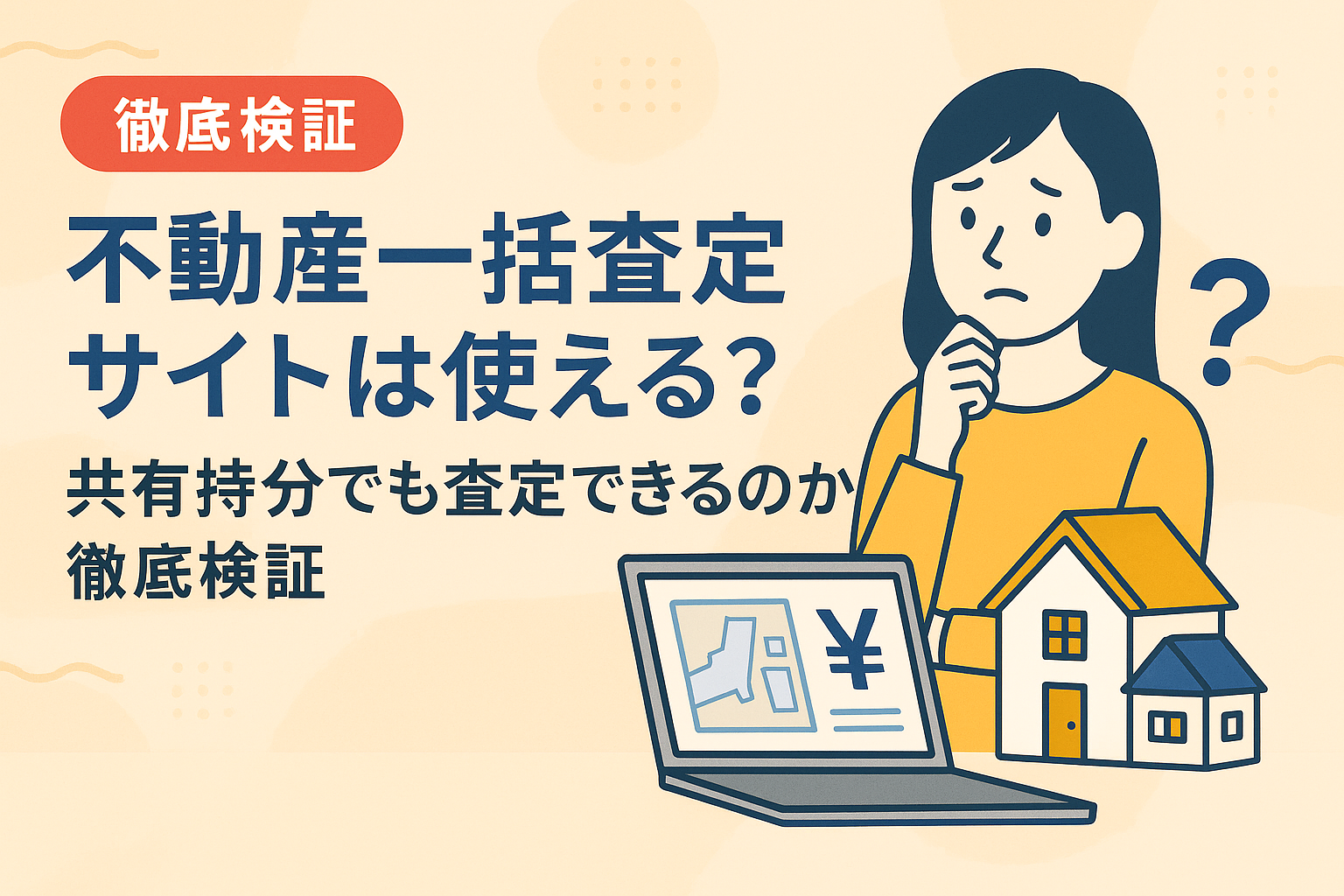
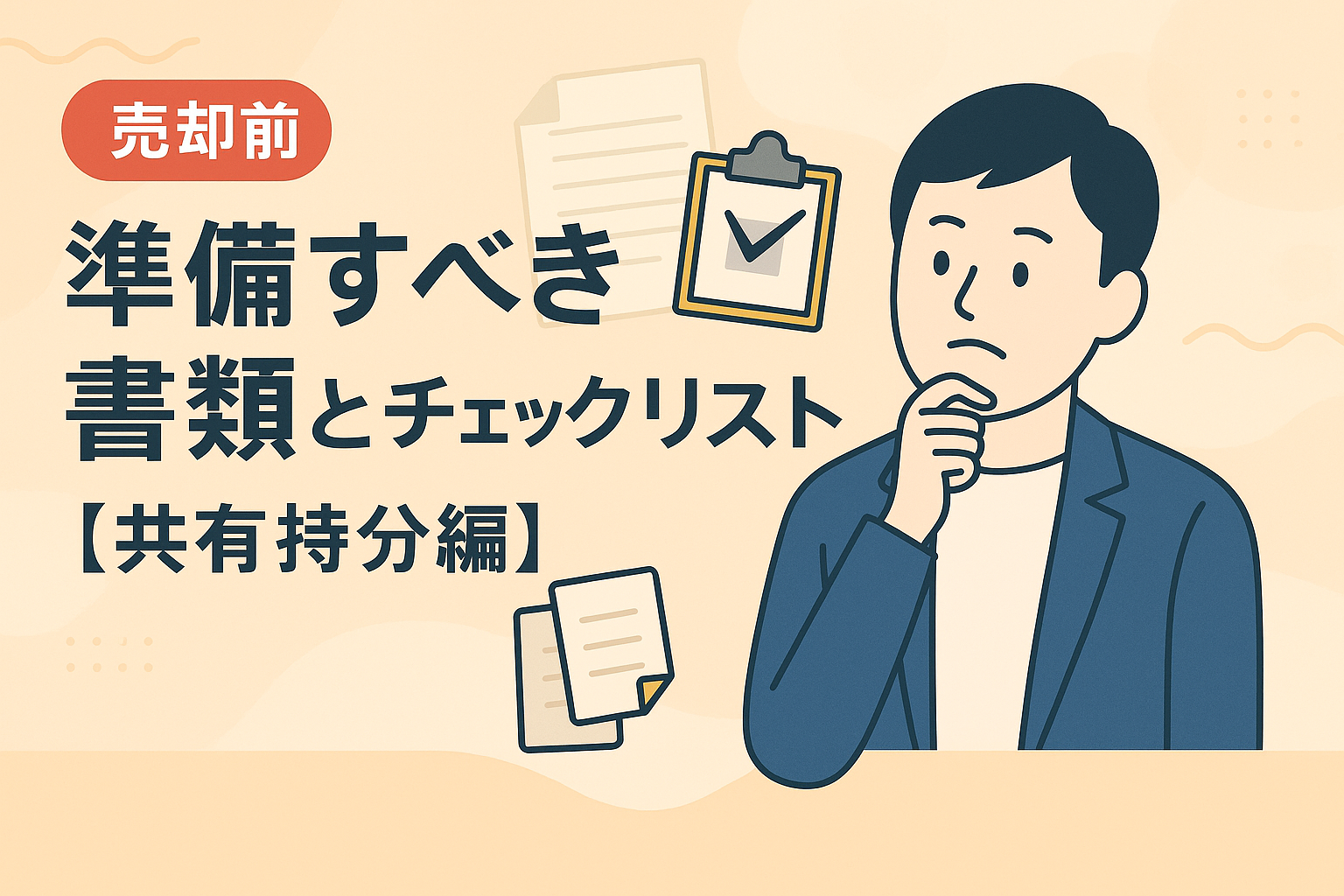




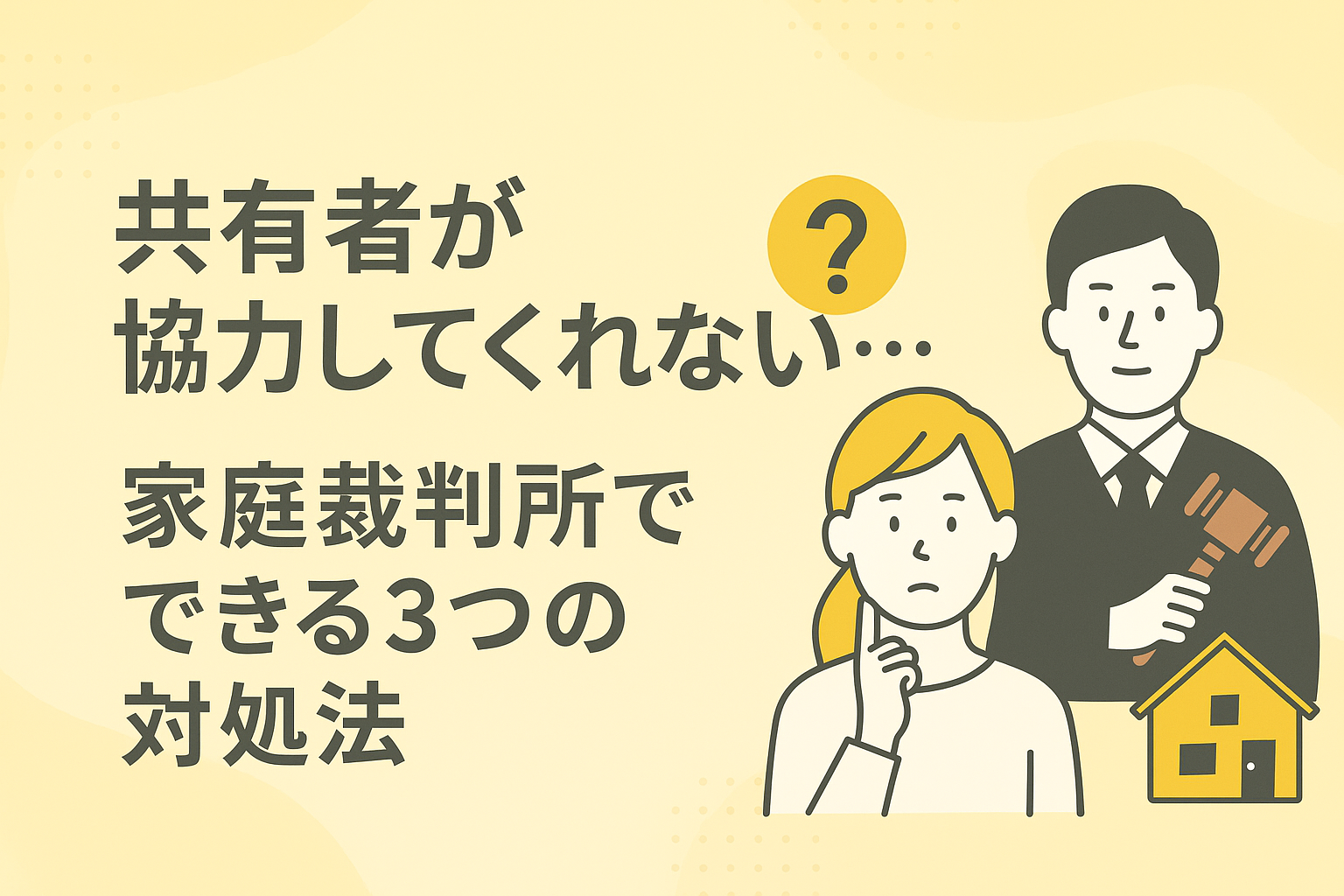
共有名義ってことは、私にも持分があるってことですよね?同じ意味なんでしょうか?