共有者が死亡したら売却できない?相続発生時の注意点
共有者の死が不動産売却に与える影響とは?
不動産を複数人で所有している「共有持分」の状態において、共有者の一人が死亡するという事態は決して珍しくありません。
しかし、このタイミングで不動産の売却を検討していた場合、「すぐに売れると思っていたのに進められない」という状況に陥ることがあります。

共有者が亡くなると、その持分は法定相続人に引き継がれます。誰がその権利を持つのかが確定しない限り、売却はできません。
死亡によって所有者の一人が不在となるだけでなく、新たに「相続人全員の合意」が必要となるため、状況は一層複雑化します。
なぜ「売却できなくなる」のか?法律的な仕組みを解説
不動産を売却するには、共有者全員の合意と署名・押印が必要です。
では、そのうちの一人が死亡してしまった場合、どのような状況になるのでしょうか?
結論として、亡くなった方の持分が「誰に相続されるか」が確定していなければ、売却そのものができません。
つまり、次のようなステップが必要になります。
-
被相続人(亡くなった共有者)の法定相続人を確定する
-
相続人間で遺産分割協議を行う
-
協議の内容に基づき、持分を登記に反映させる(相続登記)
これらが完了するまでは、売却の話を進めることはできないのです。
売却に影響する「相続トラブル」の事例とは?
相続において、次のようなトラブルが発生することが少なくありません。
スクロールできます →
| トラブルの内容 | 発生しやすい状況 |
|---|---|
| 相続人同士の意見不一致 | 誰が住むか、どう売るか、配分方法でもめる |
| 相続人が不明・連絡が取れない | 相続人の所在不明、海外在住などで連絡が取れない |
| 相続登記が放置されている | 数年〜数十年放置されている「未登記」の共有不動産 |
こうしたケースでは、物件全体の流動性が大きく低下し、「買いたい」という人がいても契約締結に至らないことも多々あります。
相続トラブルによる「リスク」とは?
放置された共有持分は、以下のようなリスクをもたらします。
-
不動産の売却が長期化し、管理費や固定資産税だけがかかり続ける
-
相続人の中に高齢者や認知症の方がいると、法的手続きに制限がかかる
-
相続人の死亡により、さらに「孫世代」まで関係者が増える(数十人規模になることも)
このように、時間が経てば経つほど、問題は複雑になりやすいのが特徴です。
相続が発生した場合の具体的な対応方法
相続登記は「義務化」されています
2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。
これは、亡くなった共有者の不動産を相続した際、原則として3年以内に相続登記を行う必要があるというルールです。
違反すると、最大で**10万円の過料(罰金)**が科される可能性もあります。

親が亡くなって不動産を相続しましたが、登記ってしないとダメなんですか?

はい。2024年からは義務化されており、登記をしないままだと罰則があるだけでなく、不動産の売却や名義変更ができません。
スムーズな売却のためにできる3つの対策
共有者が死亡した後、共有持分の売却を進めたい場合には、次の対策が効果的です。
1. 法定相続情報一覧図の取得
登記の際に便利なのが「法定相続情報一覧図」です。
これがあれば、戸籍謄本の束を何度も提出する必要がなくなり、手続きが円滑に進みます。
2. 遺産分割協議を公正証書に
相続人同士で話し合った内容を「公正証書遺産分割協議書」として作成しておくと、後々のトラブル防止になります。
署名・押印だけでなく、誰が何を相続するか明記しましょう。
3. 相続放棄の可能性も検討
借金が多い、権利関係が複雑で面倒、という理由で相続を放棄することも可能です。
ただし、不動産だけを放棄して他の財産を受け取ることはできないため、慎重な判断が必要です。
相続で名義が分散すると売却が困難に?
相続によって1つの持分が複数人に分割されると、売却に必要な同意を得るハードルが上がります。
スクロールできます →
| 状況 | 売却への影響 |
|---|---|
| 相続人が2〜3人程度 | 協議次第で売却可能。比較的スムーズ |
| 相続人が5人以上 | 合意形成が困難。感情のもつれが出やすい |
| 相続人に未成年・高齢者が含まれる | 特別代理人や後見人の選任が必要になる可能性あり |
このように、相続後の持分は時間と共に複雑化し、売却の障壁が高くなります。
専門家を頼ることで売却が可能になるケースも
不動産の相続トラブルは、素人だけでは対応が難しい場合が多いです。
そこで有効なのが、共有持分に特化した買取業者や不動産専門家のサポートを受けることです。
特に以下のような状況では、専門家による対応が不可欠です。
-
相続人の数が多く、意見が割れている
-
未登記のまま何年も経過している
-
一部の相続人と連絡が取れない
専門家は、相続登記の支援・買取の提案・調整役としてのサポートなど、包括的な支援が可能です。
「時間がかかりそう」と感じたら、すぐに相談することがスムーズな売却への近道です。
共有者が死亡すると、持分は相続人に引き継がれますが、それが確定しない限り売却はできません。2024年からは相続登記が義務化されており、放置すれば罰則やトラブルのリスクが高まります。複雑化を防ぐためには早期の登記対応や専門家の活用が効果的。相続による共有状態は「時間との勝負」でもあり、できるだけ早く動くことが成功へのカギです。


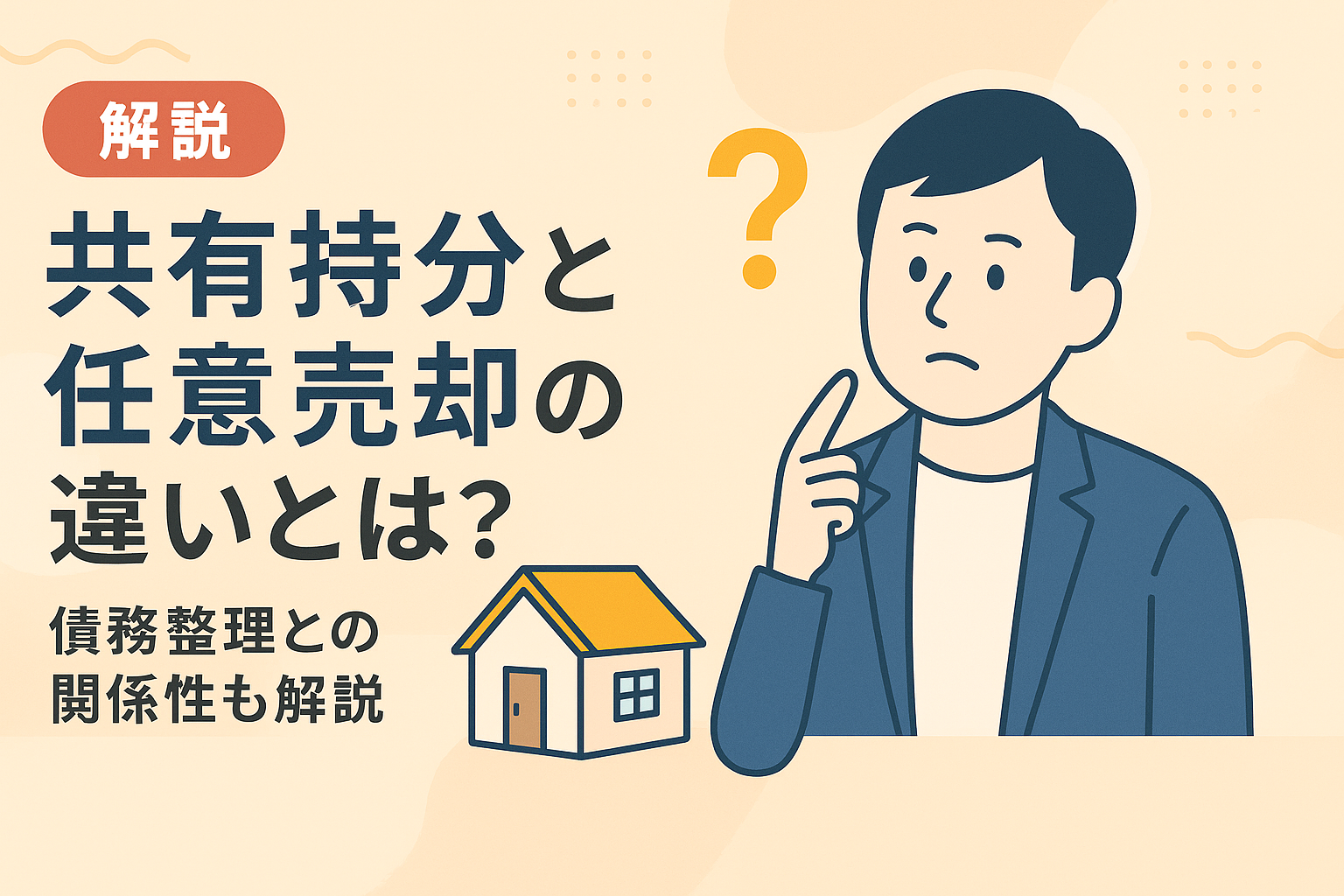

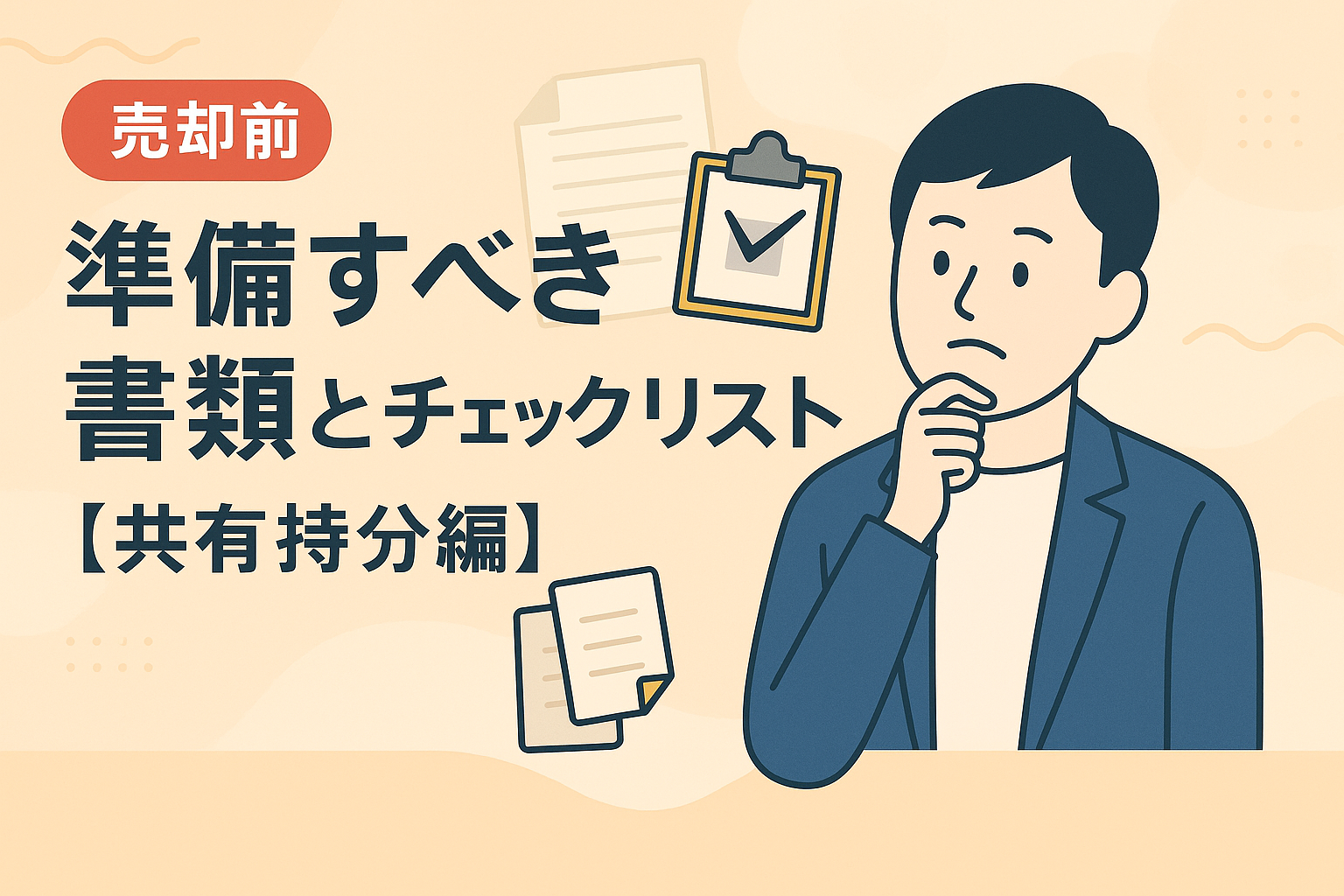

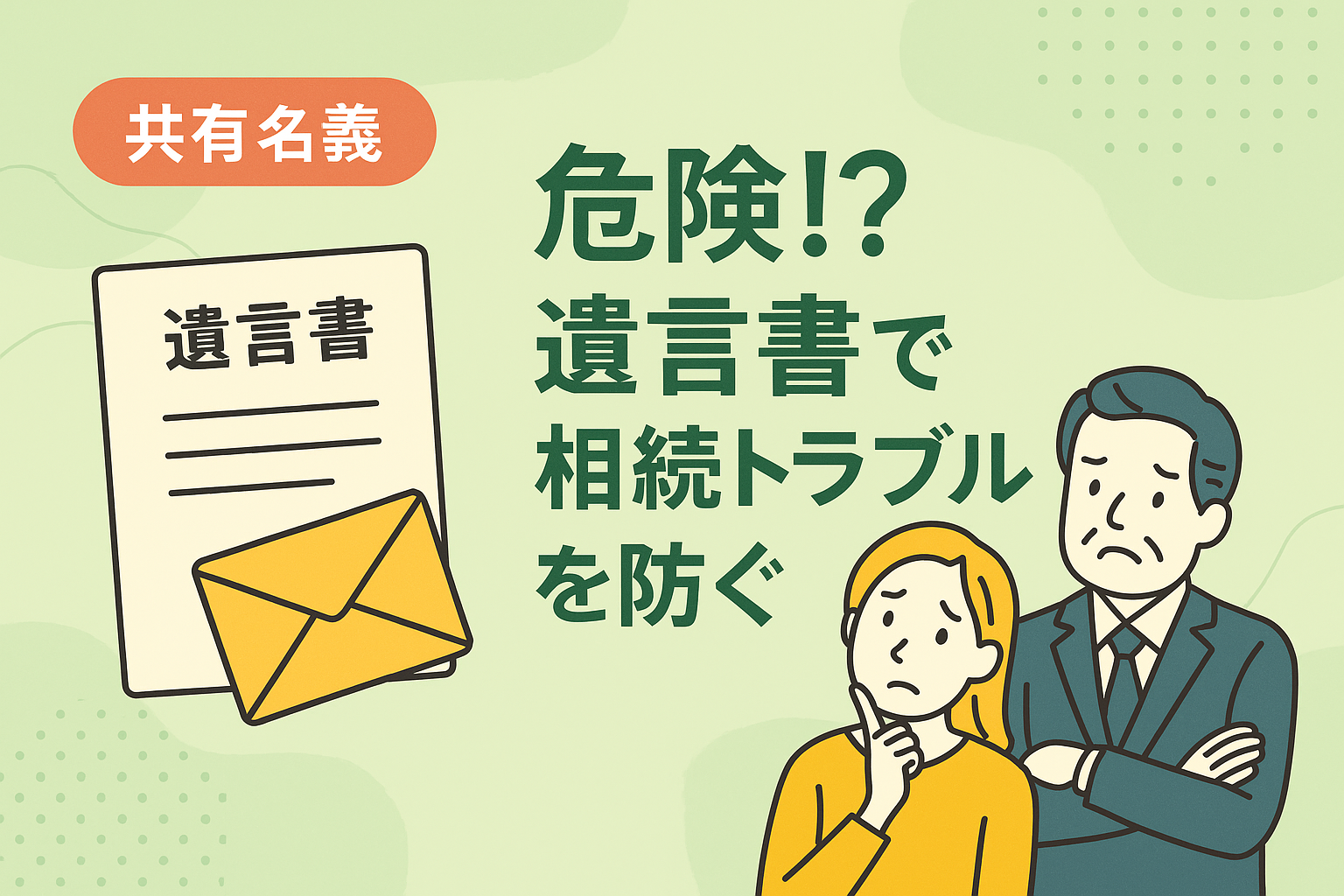
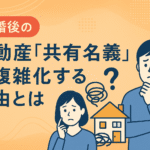
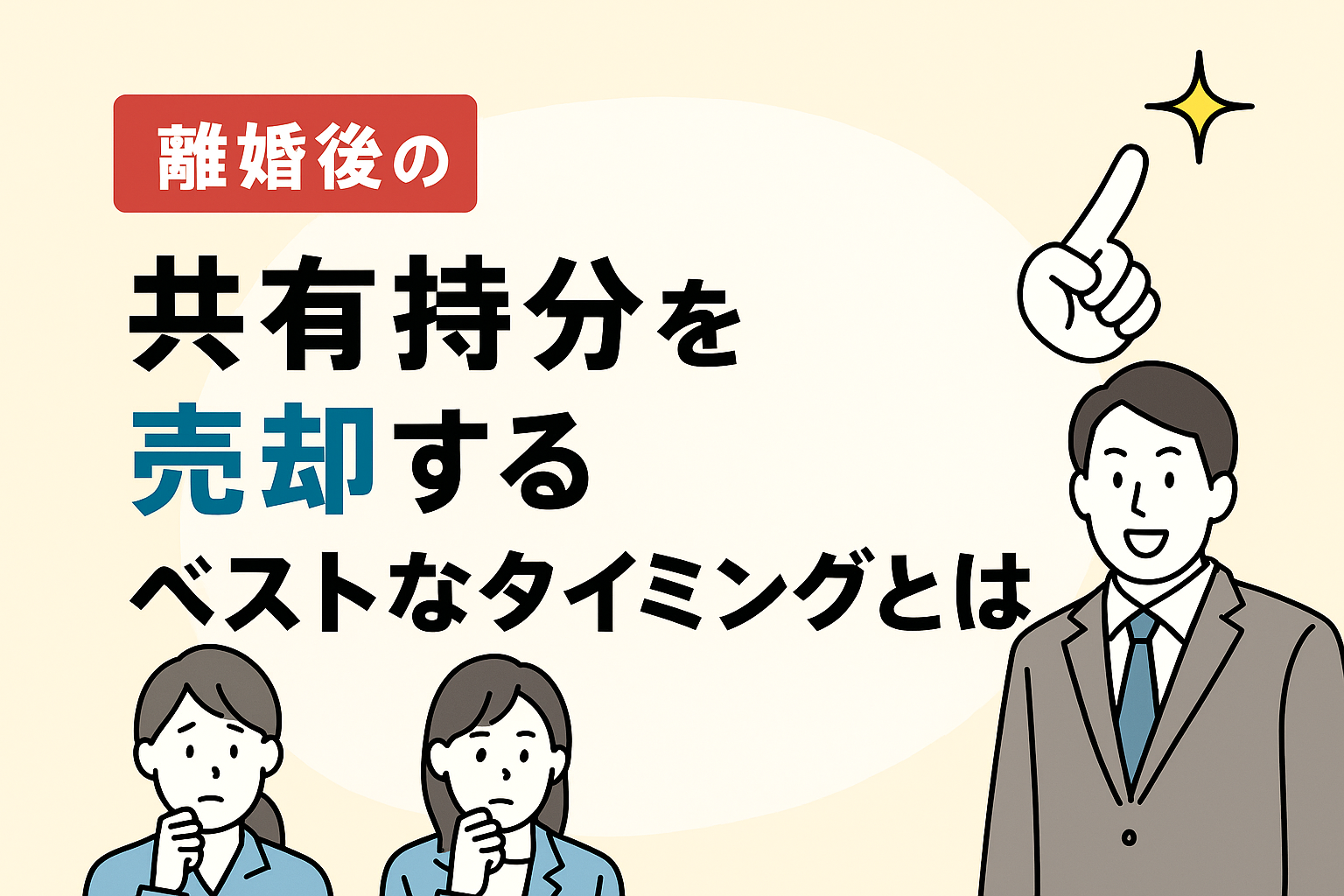





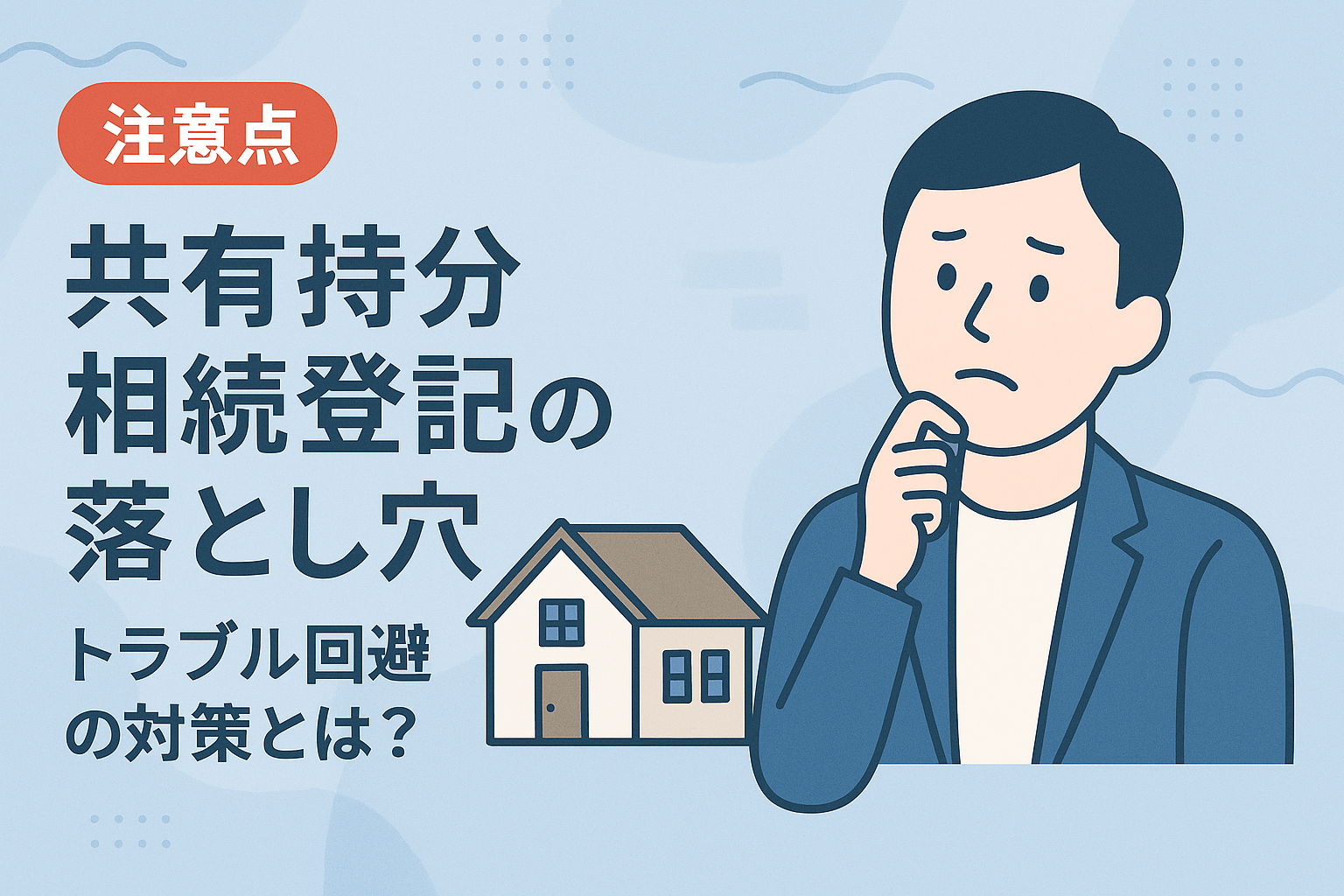





共有していた親族が亡くなってしまって…。不動産を売る話が進められないのはなぜですか?