売却と放棄、共有持分を手放す2つの選択肢とは?
不動産の共有名義でトラブルや負担を抱えている方の中には、「手放したい」「関わりたくない」と感じるケースも少なくありません。
そんなときに候補となるのが「売却」と「放棄」という2つの方法です。
一見似たように見えるこれらの手段ですが、法的な意味・手続き・リスクは大きく異なります。
本記事では、共有持分の売却と放棄の違いをわかりやすく比較しながら、それぞれのメリット・デメリットを解説していきます。
売却とは?対価を得て持分を譲る方法
「売却」とは、自分が保有している共有持分を第三者や共有者に対価(お金)と引き換えに譲渡する行為です。
不動産全体の売却とは異なり、一部の持分だけを売ることも可能で、実際には以下のようなケースで利用されます。
-
相続により持分を取得したが管理が煩雑なので手放したい
-
共有者との関係悪化で将来的なトラブルが不安
-
資金が必要で不動産の一部を現金化したい

はい、持分のみの売却も可能です。共有者に買い取ってもらう方法や、第三者に売却する方法があります。
放棄とは?所有権を一方的に捨てる行為
「放棄」は、共有持分を無償で手放す行為と認識されがちですが、民法上「放棄」という手段は明確に定められていません。
実務上、「放棄」は以下のいずれかの形で行われることが多くなります。
-
他の共有者に対し「持分の贈与」という形で譲渡する
-
相続放棄によって最初から権利を取得しない(相続前提)
-
何年も管理放棄することで「共有関係の解消」訴訟に発展する
ただし、どの形を取ったとしても「放棄=責任が完全になくなる」わけではないことに注意が必要です。
スクロールできます →
| 項目 | 売却 | 放棄 |
|---|---|---|
| 対価の有無 | あり(お金を得られる) | なし(贈与など) |
| 法的手続き | 契約・登記 | 贈与登記などが必要 |
| 他共有者への影響 | 所有者が変わる | 残った人に負担が集中 |
| リスク | 買い手がつかない場合あり | 管理責任が残る可能性 |
放棄はできない?注意すべき3つの誤解
「放棄すればラクになる」と思ってしまいがちですが、実際には以下のような誤解からトラブルに発展することもあります。
誤解①:「名義から外れれば責任がなくなる」
共有持分を贈与や譲渡で手放したとしても、固定資産税の通知や管理義務が残るケースがあります。
登記の変更まで行わなければ、法的には持分を保持しているとみなされます。
誤解②:「放棄すれば誰かが処理してくれる」
実際には、残った共有者が他人の持分まで管理する義務はありません。
放棄された不動産は誰も手を出せなくなり、売却も処分もできない「宙に浮いた財産」として残ってしまいます。
誤解③:「放棄は簡単にできる」
「放棄」は贈与や相続放棄という形をとる必要があり、専門家による手続きが必須です。
自己判断で名義を「放棄」してしまうと、後日責任問題が発生するリスクもあります。
売却と放棄、どちらを選ぶべきか?判断のポイント
実際に共有持分を手放す際に、「売却」と「放棄」のどちらを選ぶかは、状況によって大きく異なります。以下の基準をもとに判断することで、後悔のない選択が可能になります。
① 売却がおすすめなケース
-
現金化したい目的が明確にある場合
-
他の共有者と交渉が可能な関係性である
-
対象物件に市場価値がある
特に、共有持分専門の買取業者に依頼すれば、トラブルを回避しつつ短期間で手続きを進められる可能性があります。
② 放棄を検討すべきケース
-
維持費や管理の負担が大きく、将来的な利用予定もない
-
揉めごとが多く、関係性の悪化が著しい
-
感情的に関わりたくないなど、心理的な要因が強い
ただし放棄には手間とリスクが伴うため、感情的判断ではなく法的根拠に基づいた選択が必要です。
実際にあった放棄・売却の事例
ここでは、共有持分の放棄と売却に関して、実際に相談のあったケースを2つ紹介します。
ケース1:相続後に兄弟との話し合いが難航
状況:相続で不動産の1/4を共有持分として取得。遠方在住のため管理に関与できず、放棄を希望。
対応:専門家に相談し、他の共有者に贈与登記を実施。
結果:名義変更が完了し、税金や管理の負担も回避できた。
ケース2:共有者に買い取ってもらえず第三者に売却
状況:離婚後、元配偶者と不動産を共有していたが売却を希望。
対応:共有者が買取を拒否したため、第三者の専門業者に持分売却。
結果:持分のみの売却が成立し、現金を確保できた。

相手と話が通じなくて売却も放棄も進まないんです。どうしたらいいですか?

専門業者なら共有者との調整から対応可能です。感情的な対立がある場合も、第三者を介すことでスムーズに進むケースがあります。
売却・放棄の相談はどこにすべきか?
放棄も売却も、手続きや税務の観点で専門知識が求められる領域です。以下のような窓口に相談すると安心です。
-
不動産に強い司法書士
-
共有持分専門の買取業者
-
地域の不動産相談センター(行政窓口)
特に「売却か放棄か悩んでいる」場合には、両方の手段に詳しい専門家に相談することで、正しい選択ができるようになります。
共有持分を手放す方法には「売却」と「放棄」がありますが、それぞれに法的な意味と実務上の注意点があります。売却は資金化できるメリットがある一方、放棄は適切に手続きを行わなければ管理責任が残るリスクも。自身の状況に合わせて慎重に判断し、必要に応じて専門家の助言を得ましょう。


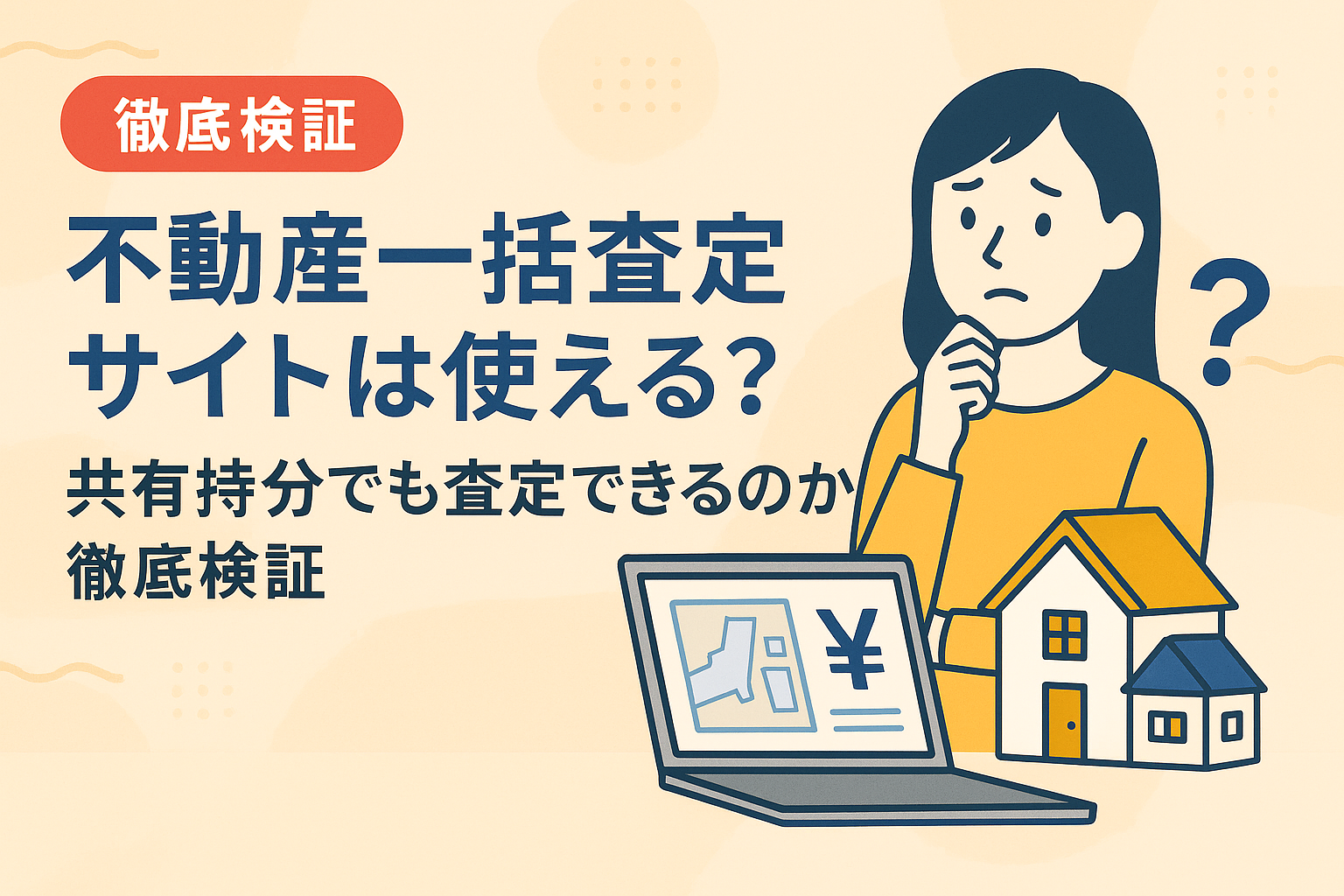





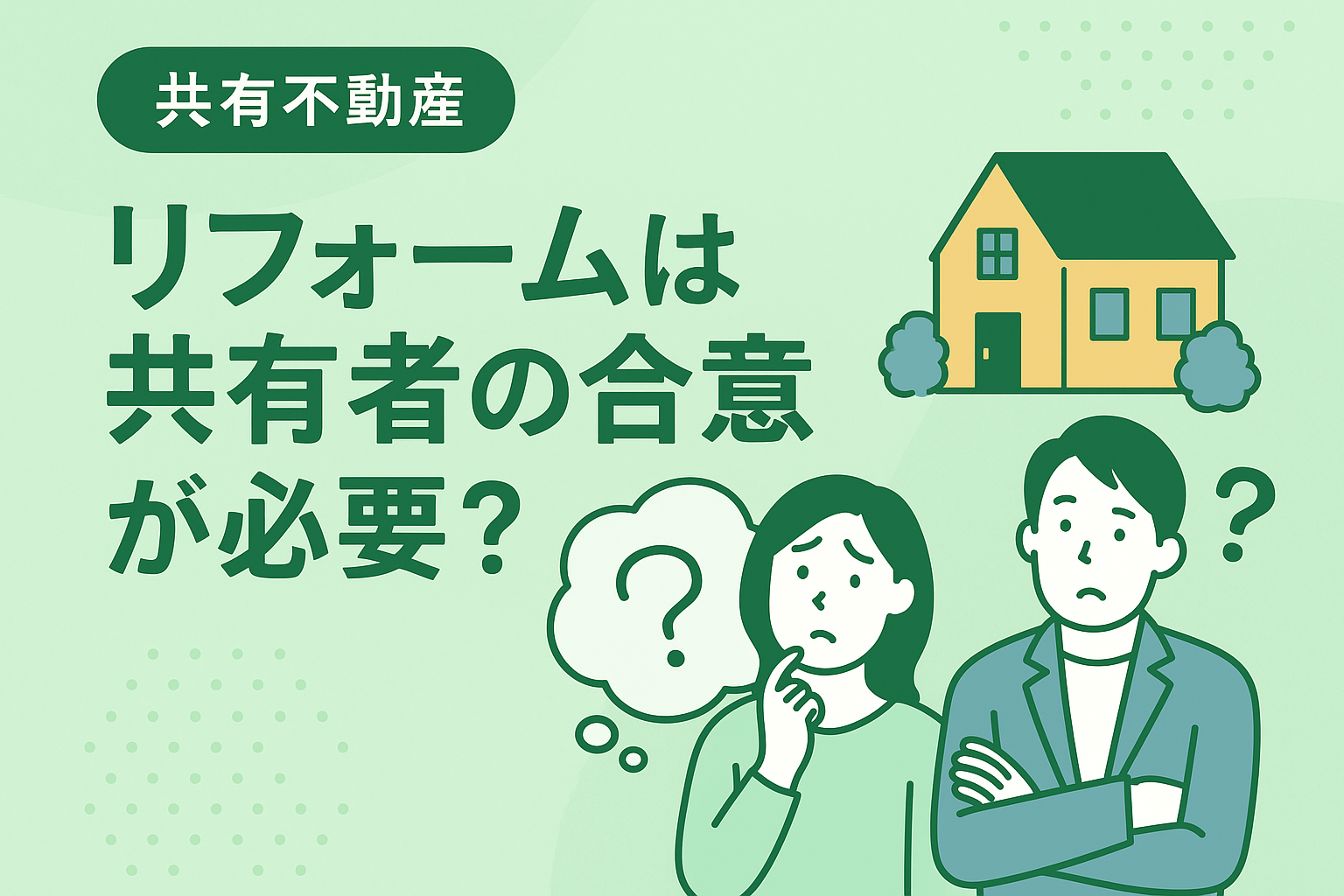










兄弟で相続した家の持分を持っていますが、遠方に住んでいて管理できないんです。売ってしまってもいいのでしょうか?