専門家に聞いた!共有持分をより高く売るための5つの工夫
共有持分でも「高く売る」は可能
共有名義の不動産は、売却時にトラブルや調整が発生しやすく、一般的に「安くしか売れない」と思われがちです。
たしかに全員の合意や名義整理などのハードルはありますが、戦略的にアプローチすることで想定より高値で売却できるケースも存在します。
実際に、不動産や相続の専門家が提案する「工夫次第で価格が変わる」テクニックは多数あります。
この記事では、共有持分を高く売るために有効な5つの工夫を、事例や交渉ポイントを交えて解説します。
売却金額に差を生む5つの工夫とは?
共有持分の売却では、単に価格交渉をするだけでは高値は引き出せません。
買い手の安心感・物件の魅力・取引のスムーズさなど、総合的な印象が査定額や提示額に反映されます。
以下は、専門家の視点で推奨されている5つの具体的な工夫です。
スクロールできます →
| 工夫の内容 | 解説 |
|---|---|
| 1. 全員で協議した売却方針の決定 | 意見の不一致が価格の足を引っ張るため、初動で全員の意思統一を図る |
| 2. 瑕疵やリスクの事前把握 | 物件に関するマイナス情報(越境、違法増築など)を事前に洗い出して整理 |
| 3. 売却タイミングの調整 | 不動産取引が活発な春・秋など、相場が高い時期を狙って売却を進める |
| 4. 相場よりやや強気の提示価格 | 値下げ交渉を見越した価格設定をすることで心理的な交渉余地を残す |
| 5. 専門業者への依頼 | 一般仲介では難しい共有不動産の売却を円滑に進めてくれるプロに任せる |
これらを複数組み合わせることで、数十万円以上の上乗せに成功した事例も多数あります。
共有者との調整は価格を左右する要因に
共有者が複数いる場合、売却方針にズレがあると買い手は不安を感じ、価格交渉も難航します。

全員が納得できる価格戦略を立てることが重要です。事前にプロの査定を提示して、感情論ではなくデータで話すことが効果的です。
とくに相続で得た共有持分は、「思い入れ」や「感情」が介入しやすいため、客観的な資料や第三者の意見を用いて交渉を進める工夫が有効です。
売却時の価格を下げてしまう一番の原因は、共有者間の意見の不一致です。
この部分をどう乗り越えるかが、高値売却の第一関門となります。
買い手の印象操作も「価格」に直結する
不動産売却において、買い手の第一印象は非常に重要です。共有持分というだけで敬遠される可能性があるため、あえてポジティブな要素を目立たせる努力が必要です。
たとえば、建物の清掃・整理をしたうえで、プロのカメラマンに物件写真を撮影してもらうだけでも問い合わせ率が大きく変わることがあります。

古い実家なんですが、少し掃除して写真を撮り直したら、問い合わせが急に増えて驚きました!

情報や見た目の整備だけでも、物件に対する心理的ハードルが下がるため、高値でも検討してもらえる可能性が上がります。
買い手は「買えるか」よりも「買っても問題ないか」を気にしています。
不安要素を払拭できれば、価格への抵抗感も少なくなるのです。
NG行動① 価格交渉を拒絶する
売却希望価格があったとしても、価格交渉の余地を完全に閉じてしまうと、買い手は一気に離れていきます。
「多少の値下げには応じる姿勢を見せる」ことが、高値を引き出す交渉術のひとつです。
NG行動② 感情的な対応をする
とくに相続による共有不動産では、感情的なやり取りが価格交渉の場面にも影響を与えがちです。
売却時はビジネスとして捉え、第三者(専門家)を介して冷静に進めることが大切です。
共有持分専門の業者を活用する利点
一般的な仲介業者では、共有名義や持分割合の扱いに慣れていないケースが多く、「高く売りたい」という意向に応えられないことがあります。
共有不動産に特化した専門業者であれば、問題点を理解したうえで価格に反映してくれるため、納得できる形での高値売却がしやすくなります。
さらに、「すぐに現金化したい」「遠方に住んでいて調整ができない」などの要望にも対応してくれるケースが多いため、スピード重視の売却にも向いています。
共有持分を高く売却するには、事前準備・共有者との調整・買い手の印象戦略・価格設定・専門業者選びの5つがカギです。これらを意識することで、価格交渉の主導権を握りやすくなり、通常よりも有利な条件での売却が可能になります。特に共有者の合意形成と買い手への安心感の提供は、成功に直結する要素です。


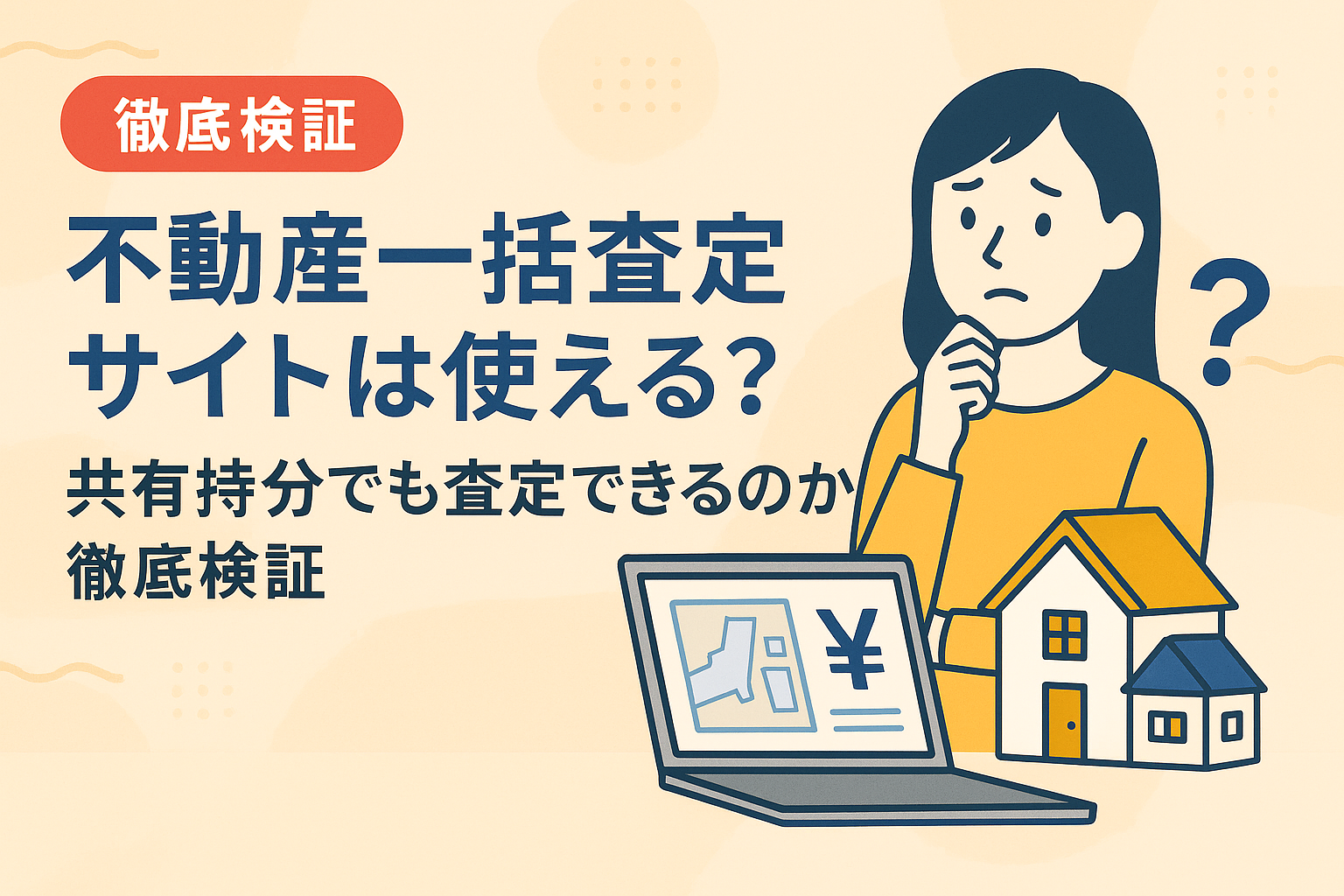





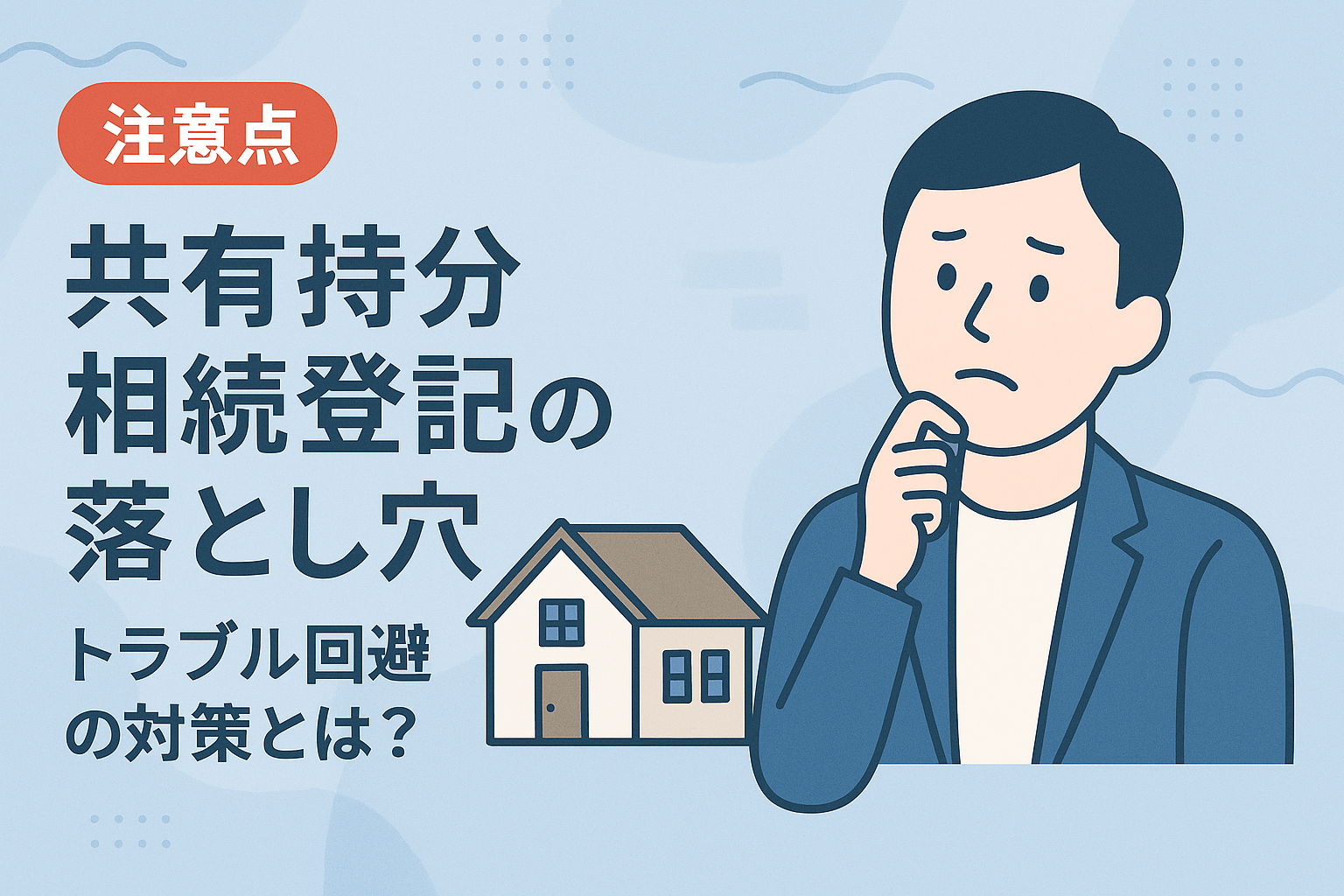
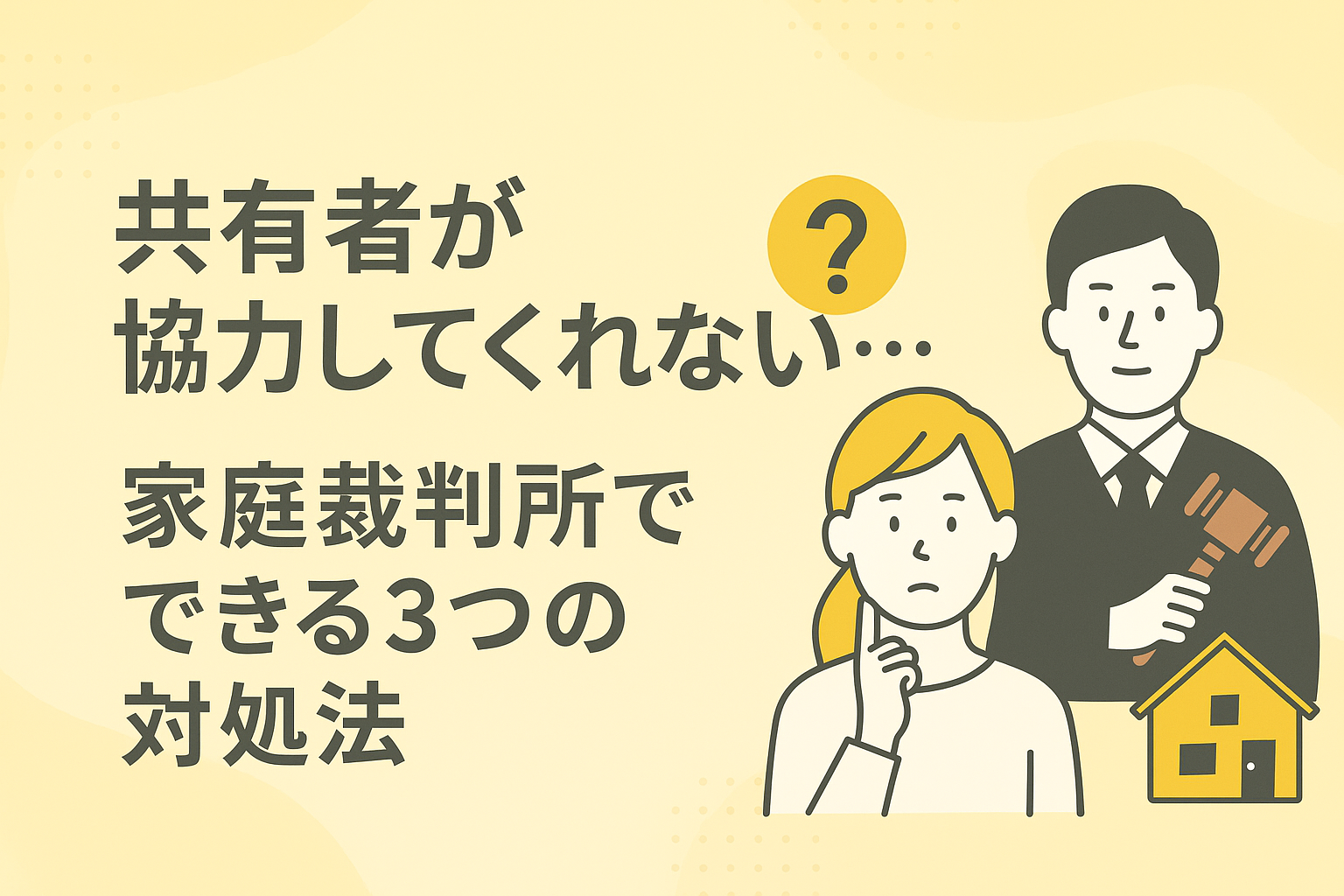
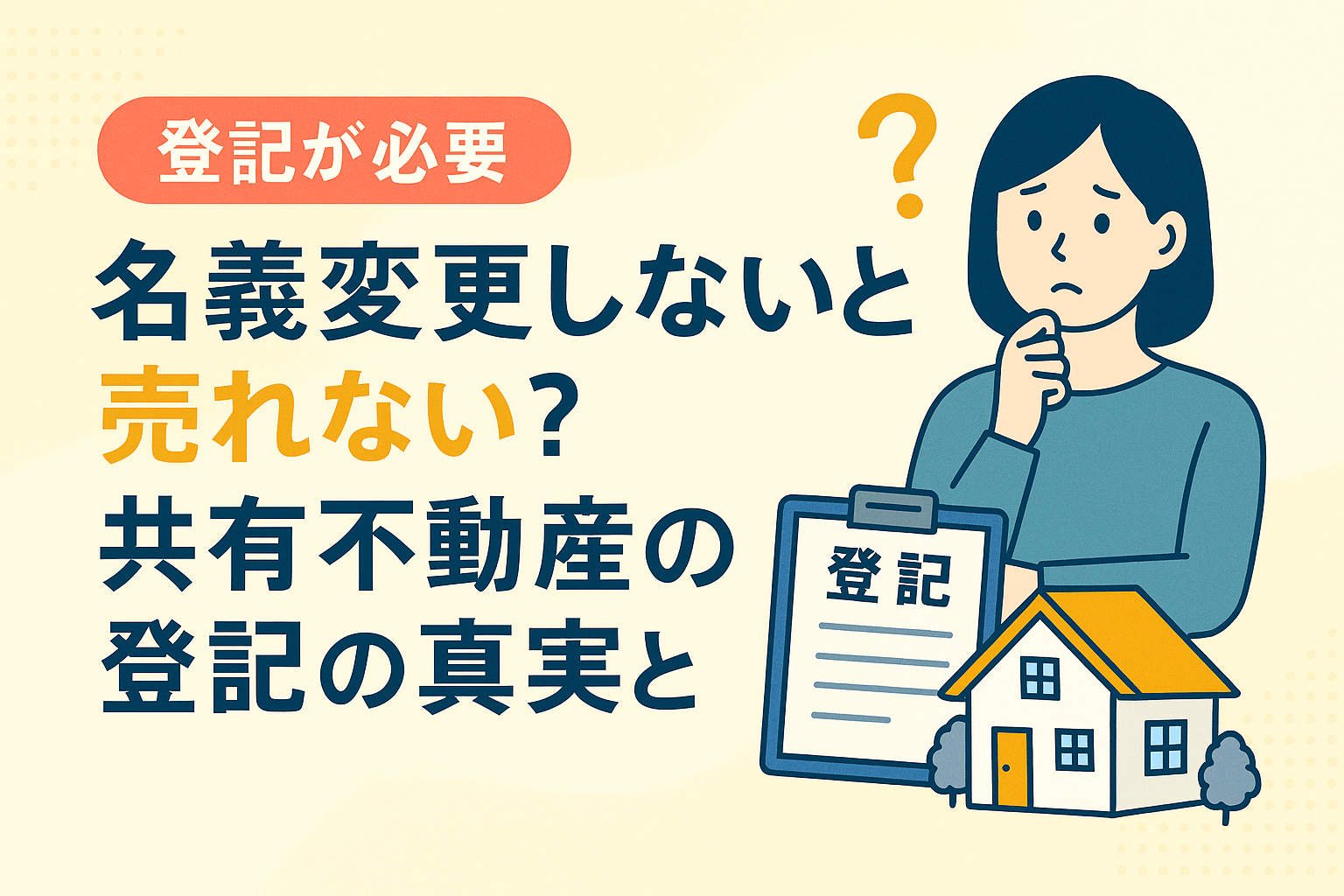
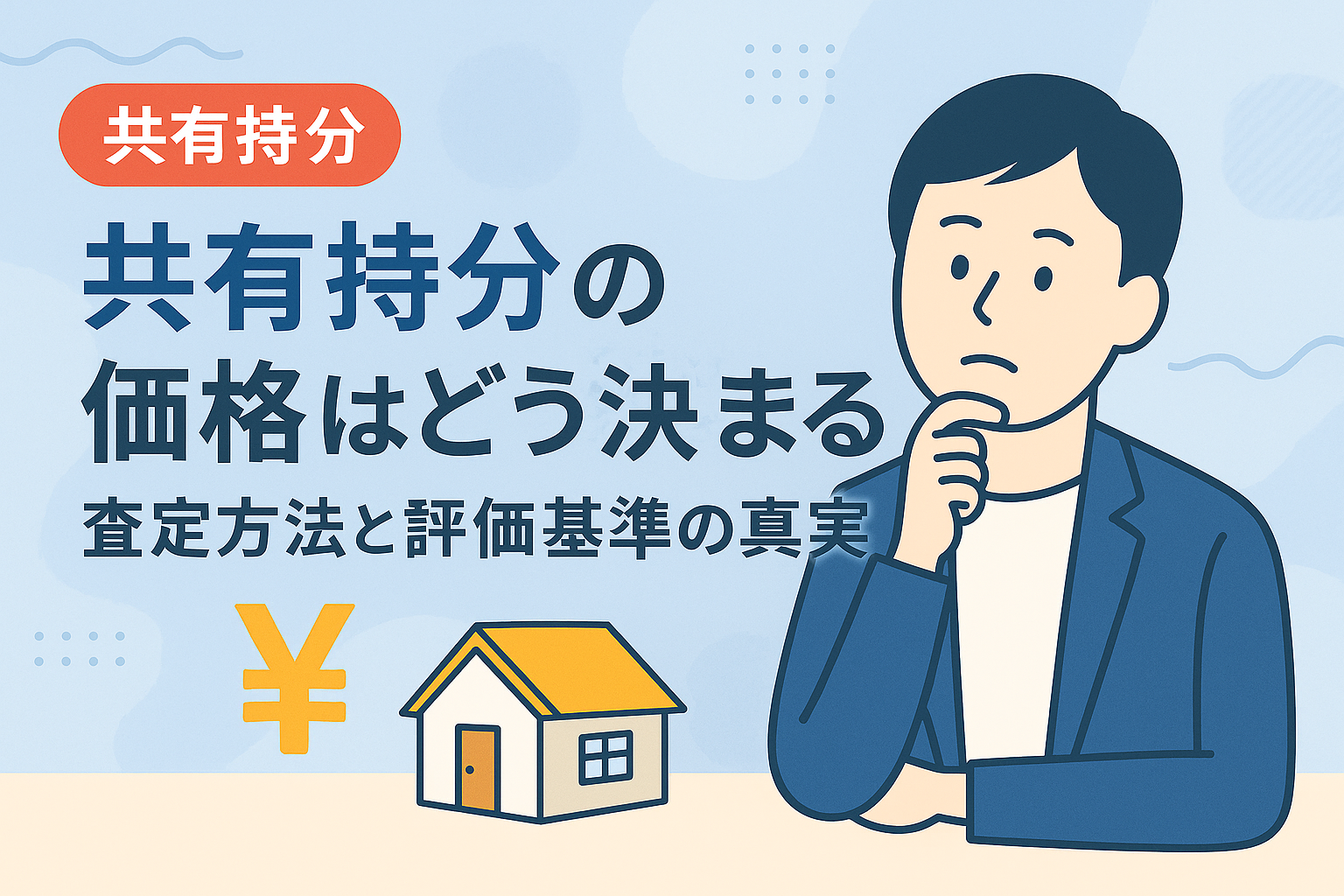
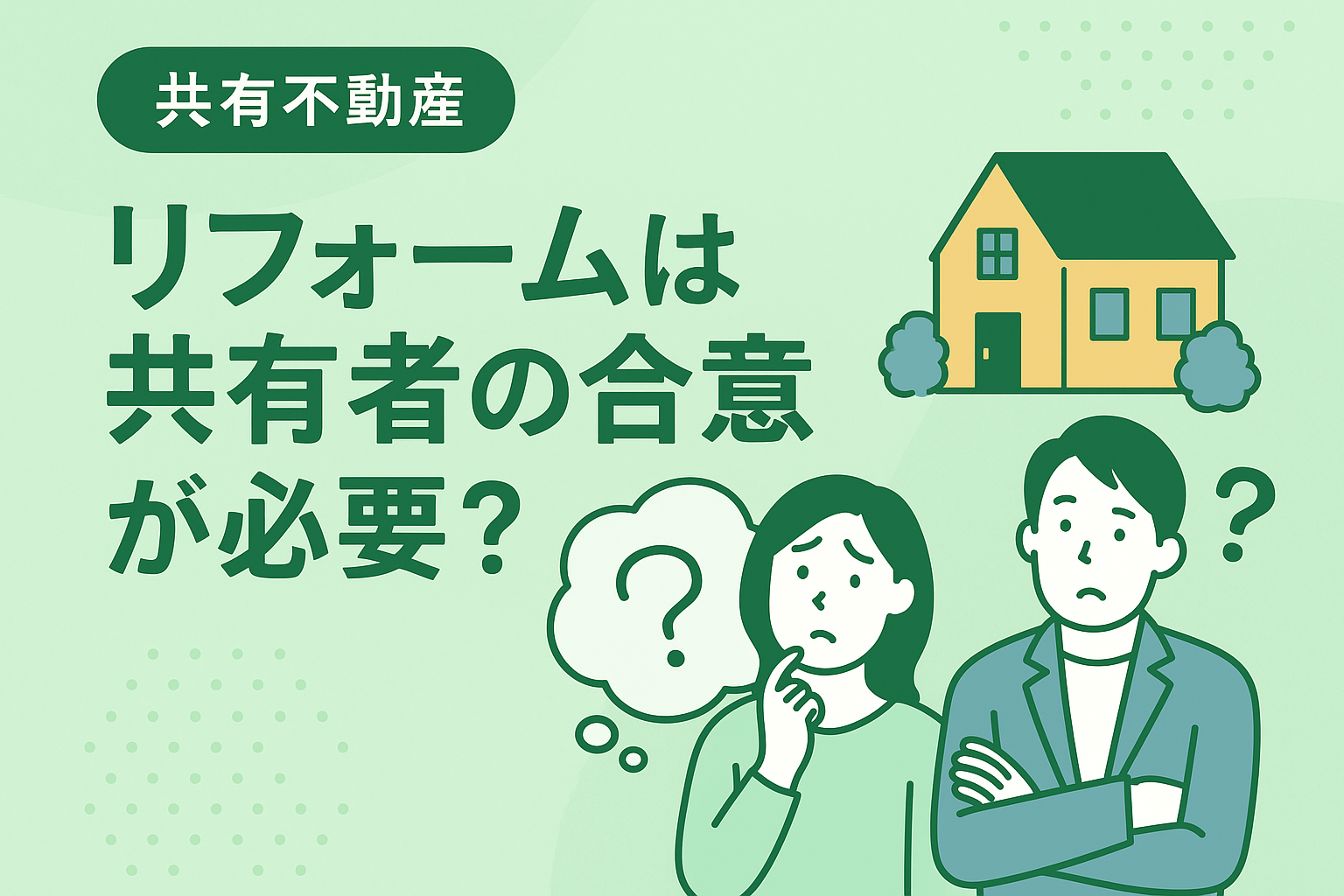
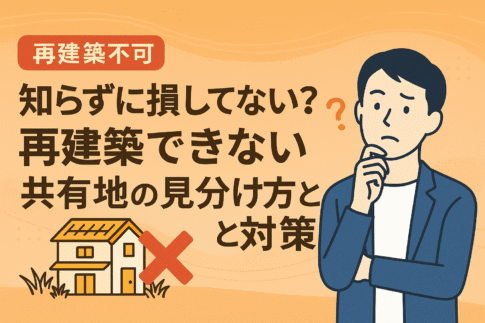
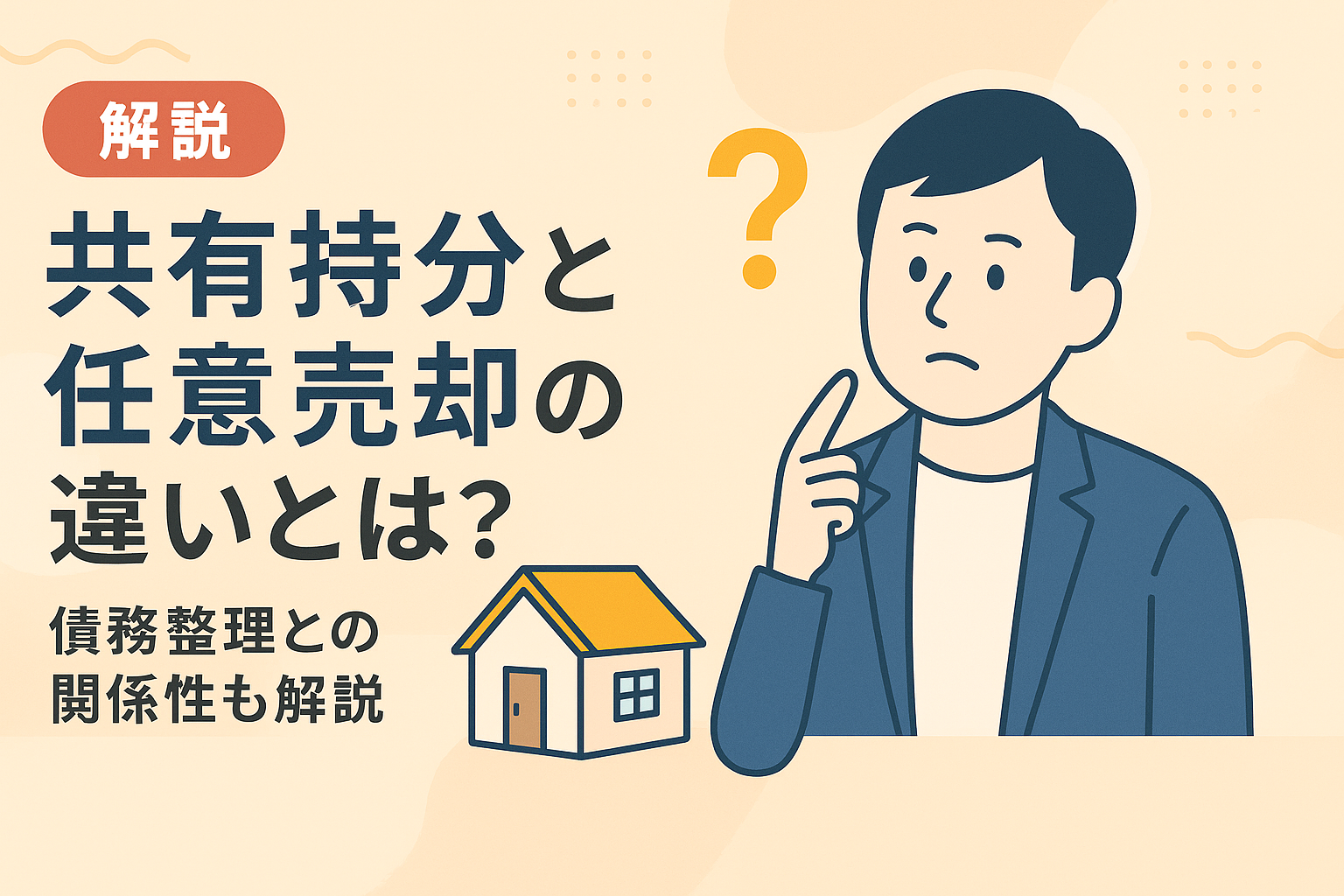





兄と共同名義の家を売りたいのですが、相場より安くてもいいと言い出して困っています…