共有持分の売却でトラブルになりやすい「隠れた瑕疵」とは?
共有持分の売却では、法的・実務的な注意点が多く存在しますが、中でも見落としがちなのが 「隠れた瑕疵」 の存在です。共有不動産の売却において、後々トラブルの原因となることが多いこの問題について、事例とともに詳しく解説します。
隠れた瑕疵とは何か?
隠れた瑕疵とは、売却時に一見してわからないが、後々発覚することでトラブルの原因となる問題を指します。共有持分においては、不動産全体の使用状況や法的制約が関係してくるため、一般の不動産売却よりもこのリスクが高まります。
実際にあったトラブル例

売却前に建築確認書や用途地域のチェックをしておくことが大切です。共有持分では共有者全体での合意が必要になることもあります。
共有持分売却の際に注意すべきポイントは「見えないリスクをいかに事前に洗い出すか」です。
共有物件に多い「隠れた瑕疵」の例
スクロールできます →
| 問題の種類 | 内容 |
|---|---|
| 境界トラブル | 測量が不完全・越境問題など |
| 違法建築 | 建ぺい率・容積率オーバーなど |
| 私道問題 | 接道義務を満たしていないケース |
| 利用制限 | 文化財・用途地域・市街化調整区域など |
なぜトラブルが起きやすいのか?
共有名義の場合、全員の合意が必要であるにもかかわらず、事前にトラブルの芽に気づいていないことが多いためです。また、売却後に新たな共有者が問題に気づき、損害賠償請求につながることもあります。
売却前に行うべき「隠れた瑕疵」のチェックリスト
事前に以下のような項目を確認しておくことで、売却後のクレームや損害賠償請求を避けることができます。
-
境界確定図・測量図の有無
-
建築確認申請・完了検査済証の確認
-
接道義務を満たしているか(私道か公道か)
-
利用制限(市街化調整区域・文化財指定など)の有無
-
共有者間の合意文書の有無(売却に必要)

売却した後に「建物が違法だった」と言われてトラブルにならないか不安です…。

そうした瑕疵は売却前に専門家が調査することで回避可能です。共有者間での確認と情報共有も重要ですね。
対策① 専門家による事前調査
司法書士や不動産会社、土地家屋調査士などの専門家に依頼することで、法的リスクや物理的瑕疵を洗い出すことができます。費用はかかりますが、後々のトラブル防止の保険と考えれば非常に効果的です。
「知らなかった」「見落としていた」が通用しないのが不動産取引の現実です。
対策② 共有者同士での認識合わせ
売却する前に、共有者全員で物件の状態を確認し、合意形成を図ることも大切です。情報格差がトラブルの原因になるため、全員がリスクを把握しておくことが信頼関係の維持にもつながります。
対策③ 告知書の記載を正確に
売却時には「物件状況報告書」や「告知書」の提出が求められることが一般的です。ここに意図的な未記載や曖昧な記述があると、後々大きなトラブルに。認識している瑕疵がある場合は、正確に・具体的に記述する姿勢が重要です。
共有持分の売却では、表面化していない「隠れた瑕疵」がトラブルの原因となるケースが多く存在します。違法建築や境界未確定といった問題は、事前の確認と専門家の調査で回避可能です。売却後の後悔を防ぐためにも、事前のチェックと誠実な開示が何よりの対策となります。






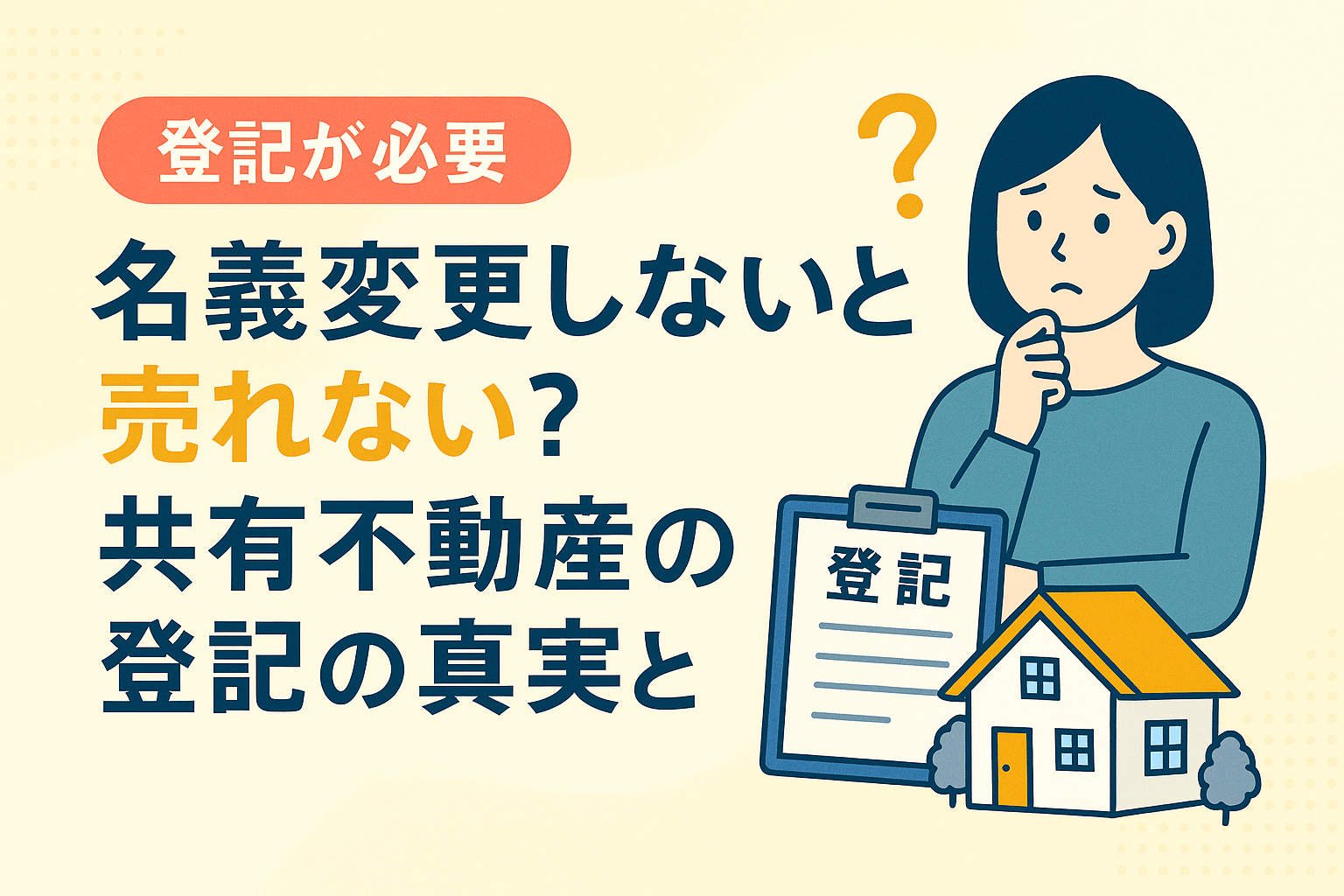


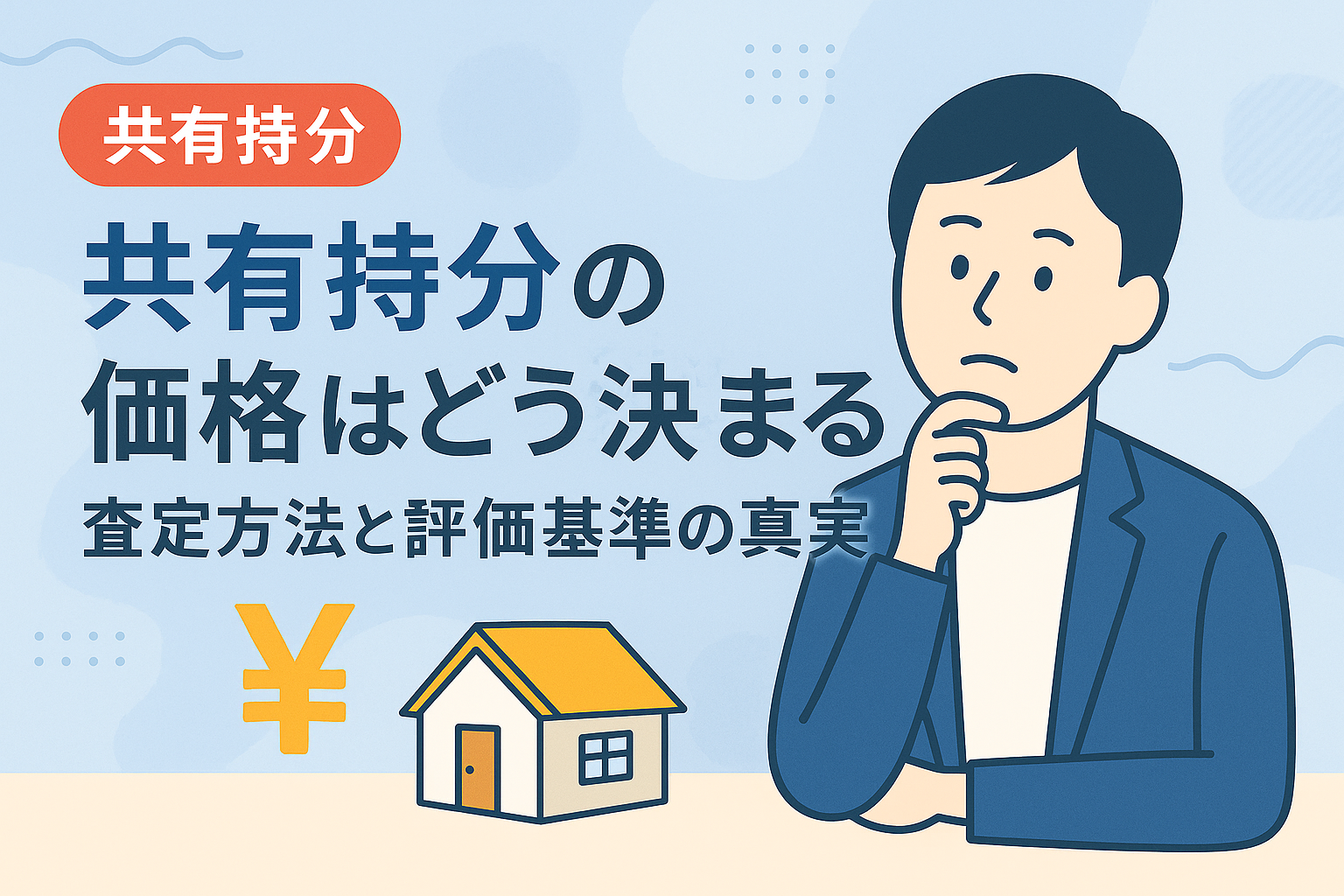


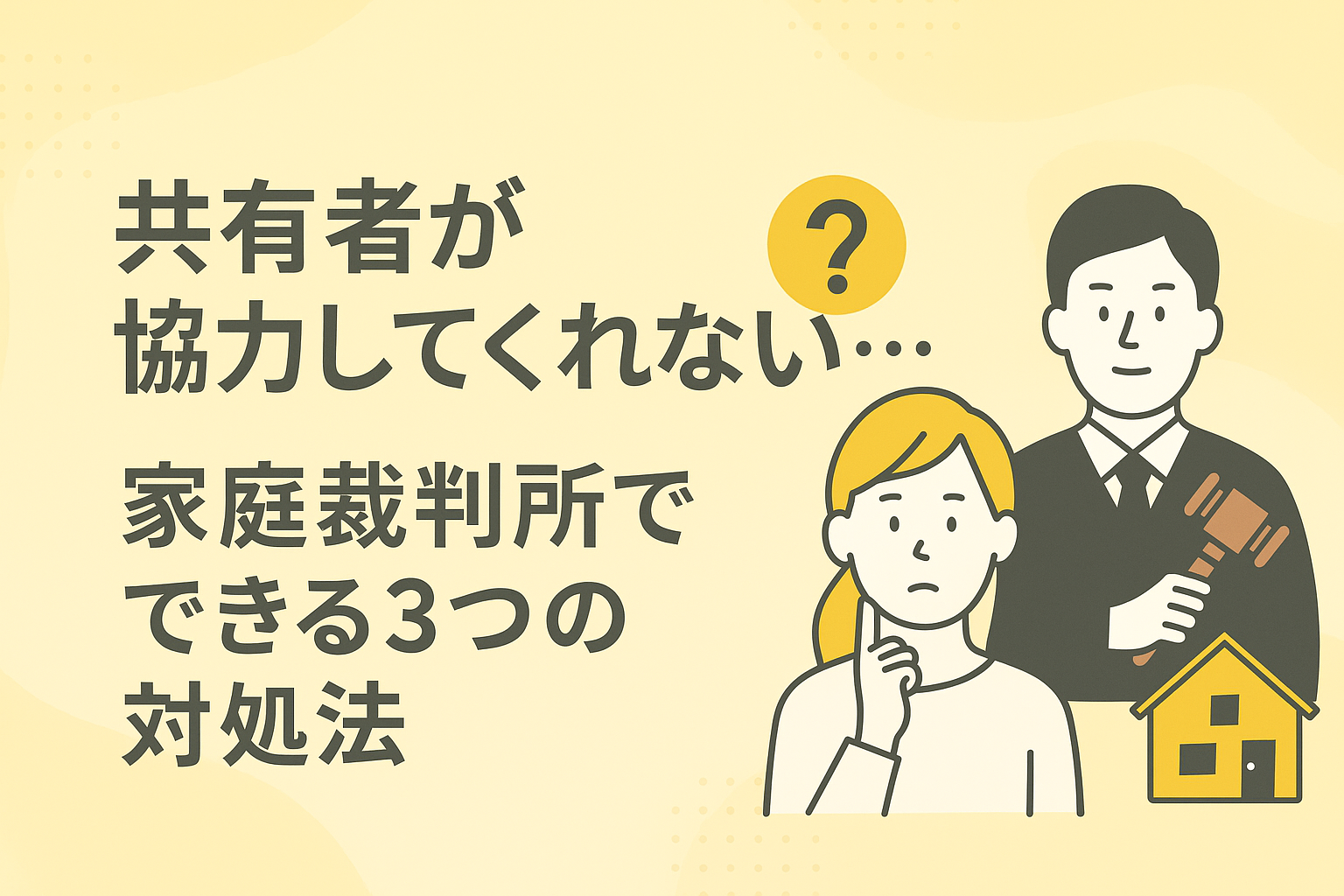

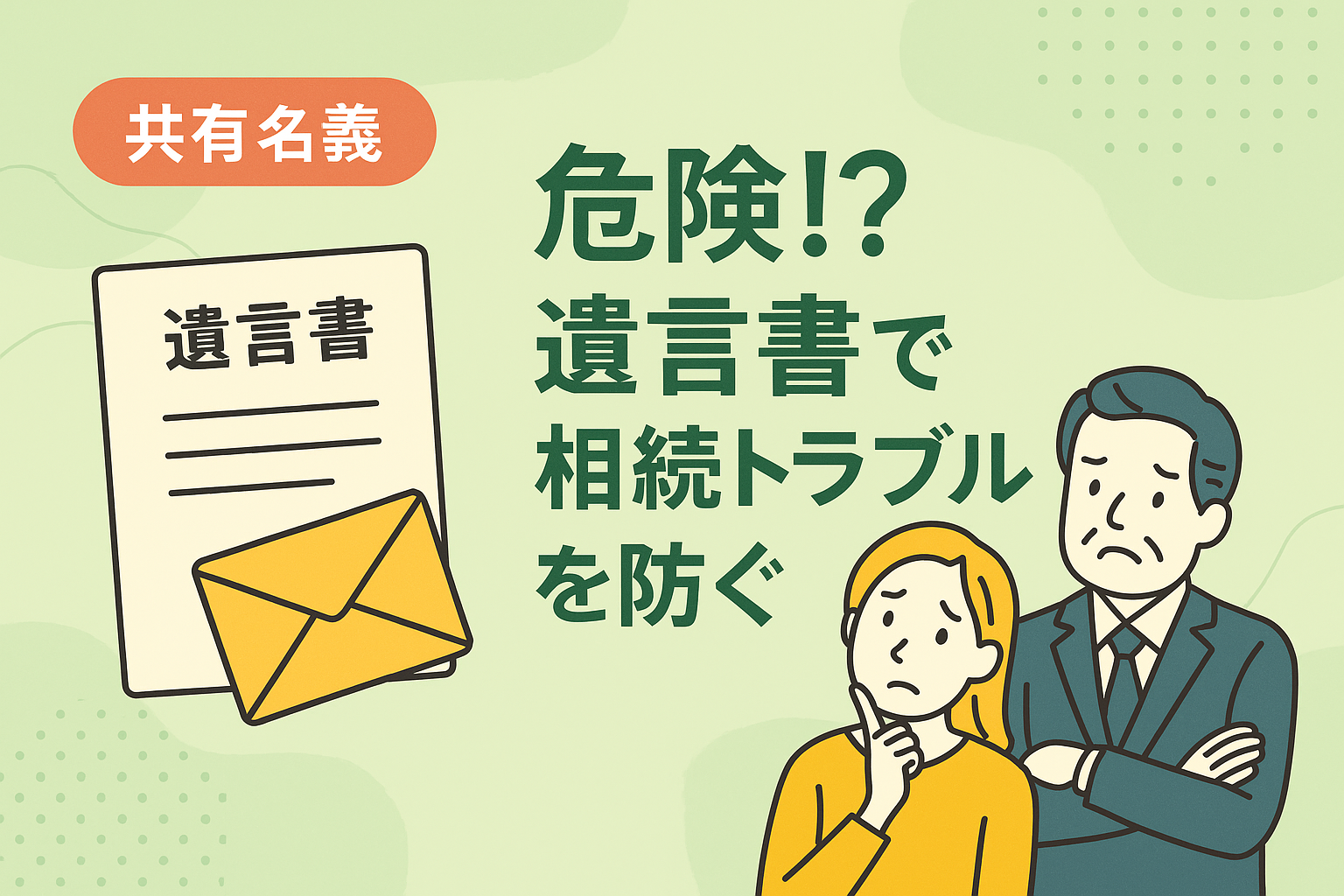





売却してから「違法建築部分がある」と言われてトラブルになりました…。