共有持分を売却する際に注意すべき5つのポイント
共有持分とは?再確認しよう
共有持分とは、一つの不動産に対して複数人が権利を持っている状態を指します。
相続や共同購入などで発生することが多く、各自が持つ割合に応じて利用や売却の権利が存在します。
一見自由に売却できるように思えますが、注意すべき点が多く、慎重な対応が求められます。

共有持分は売却できますが、事前に押さえるべき注意点があるのでしっかり確認しましょう!
売却時に注意すべき5つのポイント
1. 他の共有者への通知義務を理解する
共有持分の売却において、他の共有者へ事前に通知する義務が発生する場合があります。
これを怠ると、後からトラブルに発展するリスクもあります。
売却を進める前に、共有者間の取り決めを確認しましょう。
2. 買い手との合意が必要なケースもある
特に第三者に売却する場合、買主との間で「利用制限がある物件」という認識を共有しておく必要があります。
通常の不動産売買とは異なり、共有持分のみの売却には独特のリスクが伴うため、慎重な交渉が求められます。
3. 法律上の制限を確認する
共有持分の売却には、民法や不動産登記法に基づく制約が存在します。
特に、持分放棄と売却は異なる行為であることに注意しましょう。
法律的な問題が不安な場合は、司法書士や弁護士に相談するのが賢明です。
4. 価格設定に注意する
共有持分は「市場価値」ではなく、「権利割合」や「利用制限の影響」を踏まえて価格が決定されます。
単純な坪単価計算では通用しないため、専門業者に査定を依頼することをおすすめします。

価格って、普通の不動産と同じ計算じゃないの?

共有持分は特殊なため、割安に見積もられるケースもあります。<br data-start="1171" data-end="1174" />しっかりとした査定で相場を把握してから動きましょう!
5. 複数社に査定依頼して比較検討する
1社の査定だけで売却を進めるのは危険です。
必ず複数社から見積もりを取得し、比較検討しましょう。
共有持分の売却に強い業者かどうかも重要な判断ポイントとなります。
売却時によくあるトラブル例とその回避法
-
共有者間で価格について揉める
-
買主との間で権利範囲の誤解が生じる
-
契約後に共有者から異議が出る
-
相場より大幅に安い金額で売却してしまう
これらのトラブルを防ぐには、事前確認と専門家のサポートが不可欠です。
共有持分売却の流れ【簡易版】
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 他の共有者に売却意思を通知 |
| 2 | 売却先を探し、条件交渉 |
| 3 | 売買契約書の作成 |
| 4 | 登記手続き |
| 5 | 代金受け取り・引き渡し |
※スマホでも横スクロール対応済みテーブルです。

どこから相談すればいいんだろう…?

共有持分の売却に不安がある方は、専門家への無料相談を活用しましょう!<br data-start="1838" data-end="1841" />最適なサポートが受けられますよ!
共有持分の売却は通常の不動産売買と異なり、独自のリスクや注意点が多数存在します。
売却成功のカギは、事前に注意事項を理解し、共有者や専門家と連携を図ることです。
適切な準備を整えて、安心して取引を進めましょう。



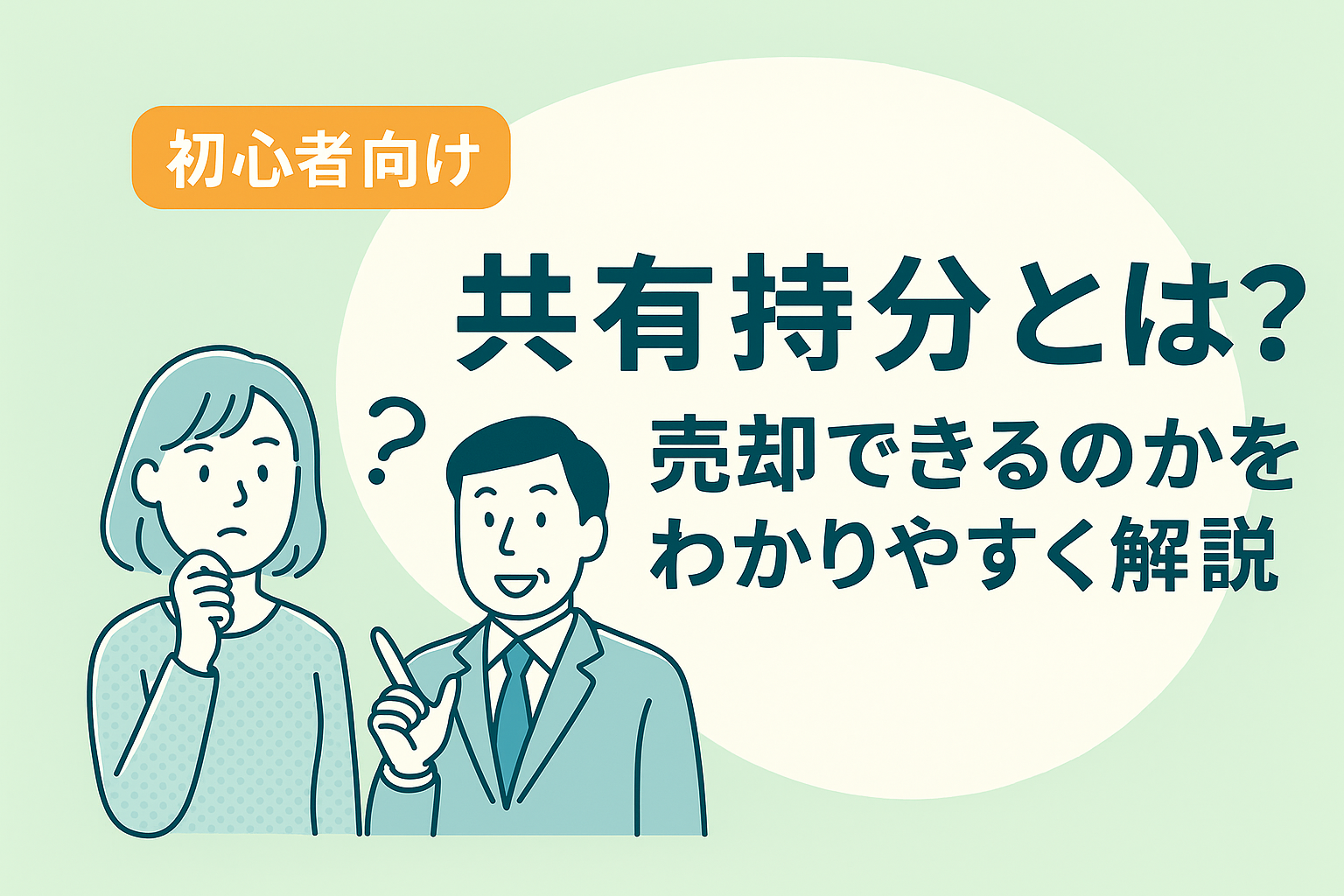
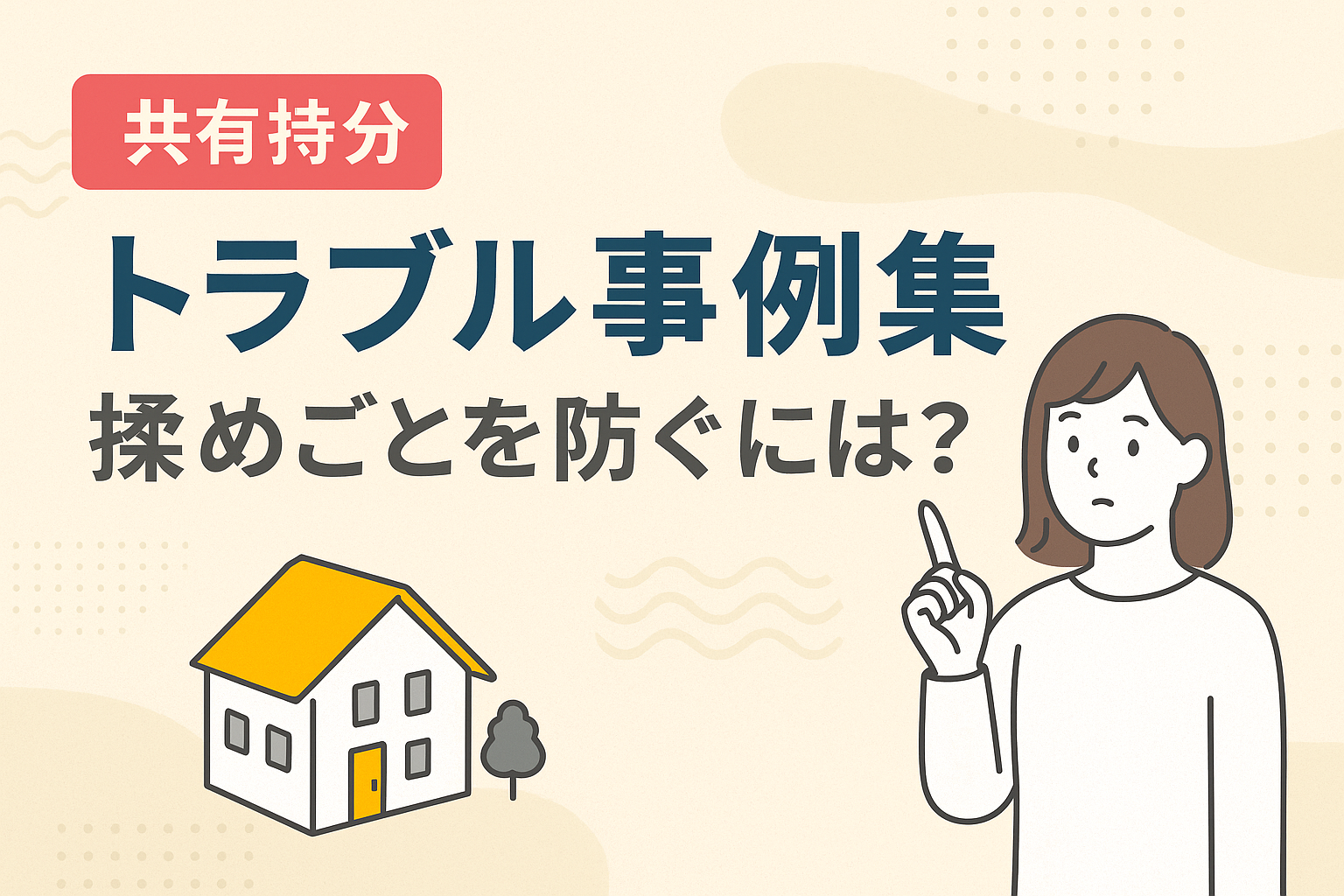




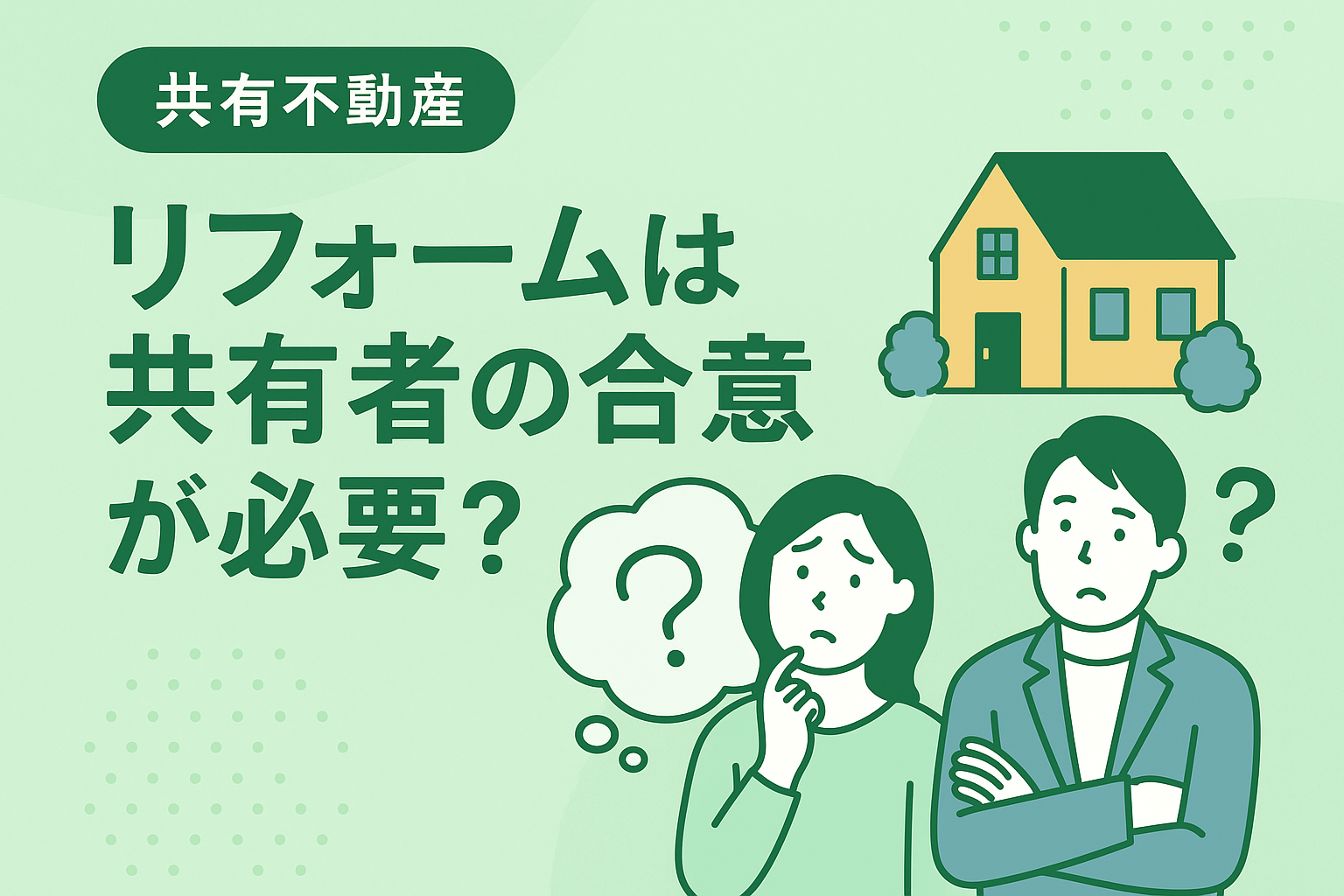
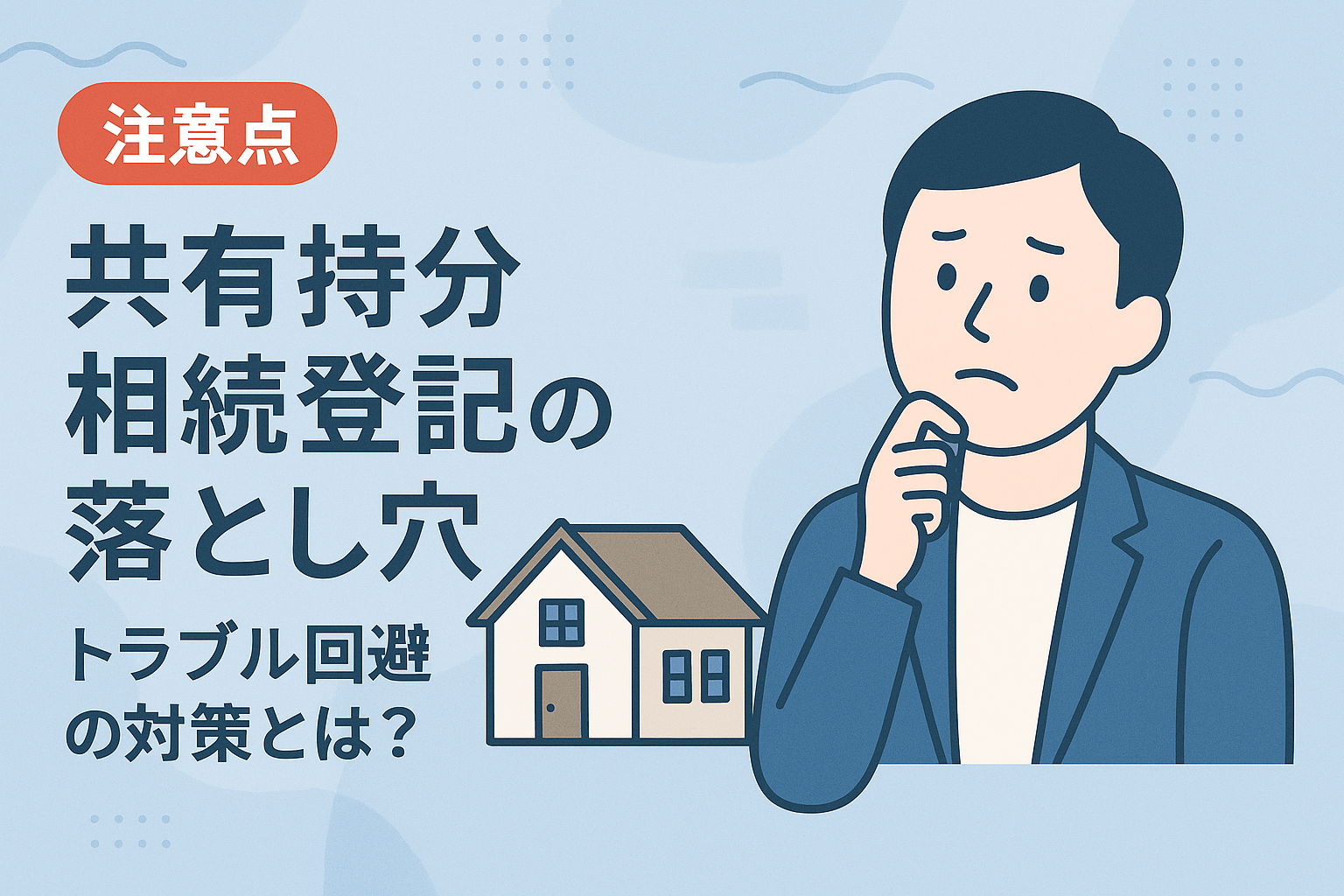
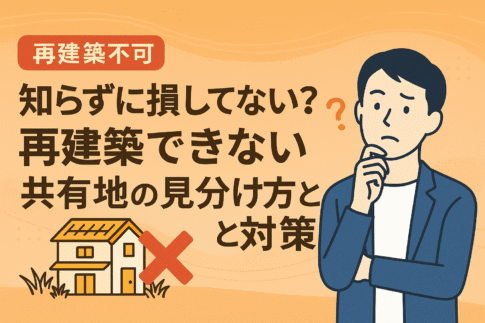




共有持分って簡単に売れるのかな…?